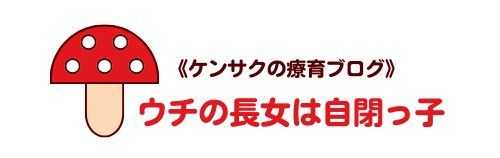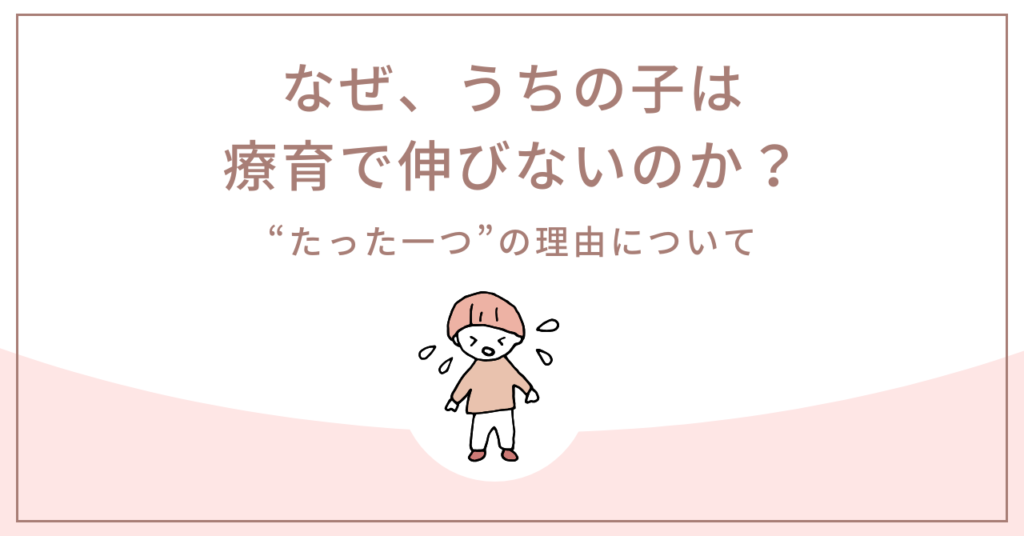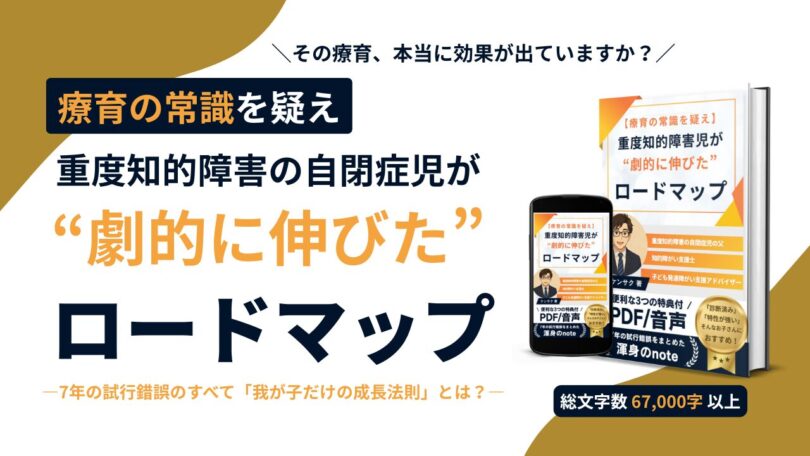発達障害の子の「盗み食い」。頭を悩ませている親御さんは少なくないはずです。見ていて気持ちの良いものでもありません。
この問題の本質は「親のしつけが悪い」わけではなく、子どもの特性からくる「課題」。親がすべきなのは、その仕組みを冷静に理解し、具体的な「対策」を立てて実行することです。
- 発達障害の子が盗み食いをしてしまう理由
- 盗み食いへの対策
- 親のメンタル管理、親が今できること
このブログ記事では、発達障害の子が盗み食いをしてしまう原因の理解から、明日から試せる具体的なテクニック、そして意外と見過ごされがちな親自身のメンタルケアまで、順を追って紹介していきます。

目次
発達障害の子が盗み食いをしてしまう「3つのメカニズム」

まず「なぜ、発達障害の子は盗み食いをしてしまうのか」を知ることがスタートです。
理由がわかると、親の気持ちも少し楽になります。
主に3つのメカニズムが関係していると言われています。
メカニズム①「衝動性」
ADHD(注意欠如・多動症)などの特性が背景にある場合、「食べたい」と思った瞬間に、脳が「待って」とブレーキをかけるのが苦手です。
結果を考える前に、体が動いてしまう。
「見たら食べる」という、非常にシンプルな脳の回路が働いている、とイメージすると分かりやすいかもしれません。
メカニズム②「感覚ニーズ」
ASD(自閉スペクトラム症)などの特性が背景にある場合、特定の感覚を求める行動として現れることがあります。
「常に口を動かしていたい」「カリカリ、パリパリした食感が好き」といった、体からのニーズを満たそうとしているのです。
空腹とは別の、「感覚遊び」に近い動機になります。
メカニズム③「内的感覚のズレ」
自分の体の内部の状態を認識する感覚(内受容感覚)が、うまく機能していないケースです。
たとえば、「お腹がいっぱい」という満腹のサインをキャッチしにくいため、物理的な限界がくるまで食べ続けてしまうことがあります。

これらのメカニズムは、一つだけではなく、複数絡み合っていることも多いです。
重要なのは、「本人のわがままや意地悪でやっているわけではない」と理解することです。
盗み食いをしてしまう現状分析【すべては「記録」から】

効果的な対策は、正確な現状分析なくしてありえません。
まずは1週間程度、「行動の記録」を取ってみてください。
そのためのツールとしておすすめなのが、行動療法の基本フレームワーク「ABC分析」です。
| A (Antecedent) 先行事象(直前に何があったか) | B (Behavior) 行動(何をしたか) | C (Consequence) 直後の結果(何が起きたか) |
|---|---|---|
| (例) ・親が電話で長話 ・テレビCMでお菓子の映像 ・宿題が終わって手持ち無沙汰 | (例) ・戸棚のパンを食べる ・冷蔵庫のジュースを飲む | (例) ・空腹が満たされた ・親に叱られた(=注目を得られた) ・美味しいと感じた |
この記録の場合、「盗み食いは、夕食前の手持ち無沙汰な時間(A)に、手軽な満足感(C)を求めて発生する傾向がある」といった、客観的なパターンが見えてきます。
このパターンこそが、叩くべき真のターゲットです。
盗み食いへの対策【環境・コミュニケーション・身体】

原因が分かったら、具体的な対策です。
「環境」「コミュニケーション」「成功体験」の3つの方向からアプローチします。
【環境編】衝動のトリガーを物理的に減らす
意志の力で我慢させるのではなく、そもそも衝動が起きにくい「環境」を整えることが最も効果的で、即効性があります。
テクニック①:食品の管理
お菓子など、特に衝動を引き起こしやすいものは、鍵付きのボックスや、子どもの手の届かない高い棚の上に保管します。
冷蔵庫や戸棚に、開けると音が鳴るチャイムを取り付けるのも有効です。
行動が可視化され、本人も親も気づきやすくなります。
また、お菓子のストックは持たず、その日に食べる分だけを買うようにすると、誘惑の総量を減らせます。
テクニック②:食事スケジュールの徹底
1日3食+おやつの時間を決め、できるだけ毎日同じ時間に出します。
血糖値が安定し、極端な空腹状態を作らないことが、衝動的な行動の予防になります。
テクニック③:「安全な逃げ道」の用意
「どうしても何か食べたくなったら、これを食べていいよ」というルールで、野菜スティックや固いおせんべい、あたりめなど、低カロリーで噛みごたえのある「安全なスナック」をカゴに入れて常備しておきます。
「禁止」ではなく「代替案」を示すことがポイントです。
【コミュニケーション編】行動ではなく「本人の状態」に焦点を当てる
問題が起きたとき、つい行動そのものを責めてしまいがちですが、一歩引いて「本人の内側で何が起きているか」に焦点を当ててみましょう。
- NGワード「また食べたの!?」
これは本人を問い詰める言葉であり、反発や隠蔽につながるだけです。 - OKワード:「お腹の感じ、今どんな感じ?」「何か、そわそわする気持ちだった?」
行動ではなく、本人の「体の感覚」や「気持ち」についてたずねます。
本人が自分の状態に気づくきっかけになります。 - 感情のラベリング支援
発達障害の子どもは、自分の感情を言葉にするのが苦手です。
「もしかして、今ちょっと退屈だった?」「学校で何か嫌なことあった?」と、親が気持ちを代弁してあげましょう。
子どもは「そうか、自分は今、不安だったんだ」と学び、食欲以外の対処法を考える第一歩になります。
娘が小学校で、隣の席の子の給食のおかず(エビフライ)に手を出してしまったことがありました。
そもそも、エビフライは娘の好物ではありましたが、「なんでそんなことを……」と落ち込みました。
ただ、その日は苦手な課題があった後で、娘が精神的に不安定だったとのこと。
そのモヤモヤした気持ちをどうにかしたくて、目の前の魅力的なものに手を出してしまったのではないかと。
なので、家でも行動そのものを叱るのではなく、「何が原因だったんだろう?」と分析することを、より意識するようになりました。
【身体戦略】エネルギーを健全な形で消費させる
有り余る衝動性のエネルギーは、別の形で発散させる必要があります。
- 運動のタスク化:
夕方のリスクが高まる時間帯の前に、「トランポリンを5分飛ぶ」「一緒に家の周りを一周ダッシュする」など、エネルギーを発散させる活動を日課に組み込む。 - 栄養学的な視点:
一般的に血糖値が安定しやすい食事(白米を玄米に混ぜるなど)や、タンパク質を意識した食事は、心の安定に寄与すると言われています。
小さな成功を積み重ね、定着させるコツ
高い目標は、親子ともに挫折のもと。
大切なのは、小さな成功体験です。
- スモールステップの原則
目標は「盗み食いをゼロにする」ではありません。
「お菓子が置いてある前を、今日は一回だけ我慢して通り過ぎられた」で100点満点です。
ハードルはできるだけ下げましょう。 - 成功の可視化
我慢できたとき、本人が好きなキャラクターのシールをカレンダーに貼る、ホワイトボードに花丸を描くなど、達成感が目に見える形になると、本人のモチベーションにつながります。
親自身のメンタル管理

子どもの対応に追われていると、親自身のメンタルがすり減っていきます。
持続的に関わっていくためには、親の心の管理も不可欠です。
発見した瞬間の「6秒ルール」
盗み食いの現場を発見すると、カッと頭に血が上ることもあるでしょう。
怒りのピークは6秒と言われます。
その瞬間、一度何も言わずにその場を離れる、ゆっくり6秒数えながら深呼吸するなど、衝動的に叱るのを防ぐ自分なりのルールを決めておきましょう。
「まあ、いっか」を増やす思考法
100点満点の完璧な対応を目指す必要はありません。
命に関わることや、健康を著しく害するものでなければ、「まあ、いっか」「長い目で見よう」と、良い意味で諦めることも立派な戦略です。
親の心の負担を軽くすることを最優先に考えましょう。
自分のための「ガス抜き」を予定に組み込む
「子どもが寝た後の15分だけは、好きなドラマを見る」
「週末の30分は、一人で散歩に出かける」
など、意識的に自分のための時間をスケジュールに組み込みましょう。
これは贅沢ではなく、明日また子どもと向き合うための、大事なメンテナンスです。
メンタルケアの方法については、私たち夫婦の実体験にもとづいて、以下の記事で詳しく紹介しています。

子どもの5年後、10年後のために今できること

今の対応は、目先の行動を抑えるだけでなく、子どもの未来への投資でもあります。
今の対応は、将来の「自己管理スキル」の土台作り
環境を調整するのは、子どもを管理するためではありません。
子どもが、衝動に振り回されずに済む成功体験を積み、いずれ自分で自分をコントロールする方法を学ぶための「補助輪」です。
年齢と共に「行動の意味」は変わっていく
今は衝動性や感覚ニーズが主な理由でも、思春期になれば、友人関係のストレスや自己肯定感の低さなど、より複雑な要因が絡んできます。
今のうちから、「行動の裏にある気持ち」について親子で話す習慣をつけておくことが、将来の親子関係の土台になります。
「食」への強い興味をポジティブに活かす道
これだけ「食」に強いエネルギーがあるということは、将来、その興味をポジティブな方向に転換できる可能性も秘めています。
一緒に料理をする、栄養について調べるなど、探求心を満たす方向へ導いてあげるのも一つの視点です。

発達障害の子どもの将来については、以下の記事で詳しく解説しています。
よくある質問(Q&A)
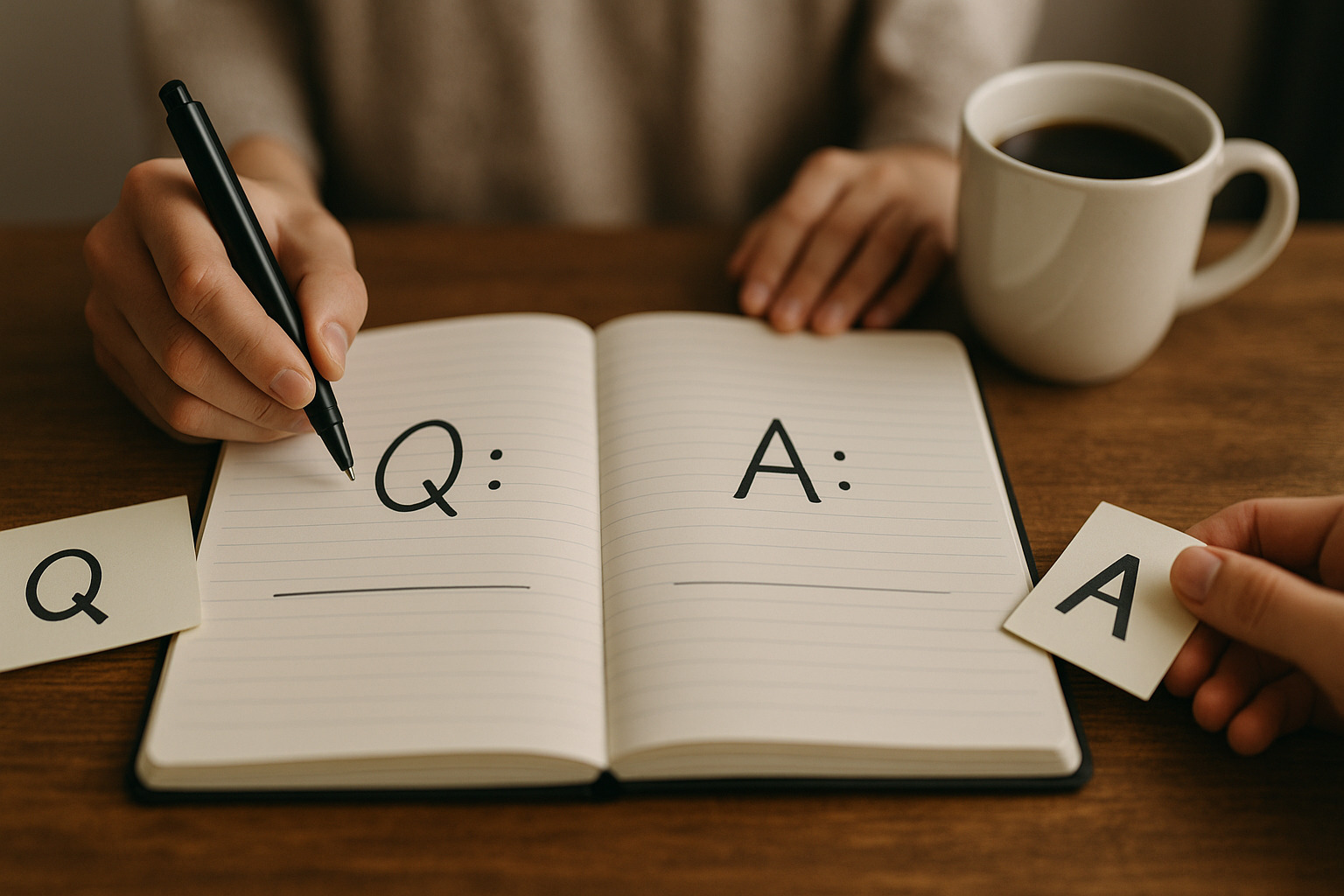
以下、よくある質問をまとめました。
Q
盗み食いは、親の愛情不足やしつけが原因なのでしょうか?
A
いいえ、まったく違います。
発達障害の子どもの盗み食いは、親の関わり方や家庭環境が直接の原因ではありません。
その多くは、ADHDなどの「衝動性のコントロールの困難さ」や、ASDなどの「感覚的なニーズ」、あるいは「満腹を感じにくい」といった、脳機能や身体感覚の特性に起因する行動です。
まずは「これは本人の特性からくる課題である」と捉え、冷静に対策を考えることが第一歩です。
Q
つい感情的に叱ってしまいます。やはり、やめたほうがいいですか?
A
はい。気持ちは非常によく分かりますが、得策ではありません。
なぜなら、叱責や罰は子どもにとって強いストレスとなり、そのストレスを解消するために、さらに盗み食いという手軽な代償行動に走りやすくなる……という悪循環を生むからです。
また、本人も「悪いこと」と分かっている場合が多く、叱られることで自己肯定感が下がり、隠れて食べる、嘘をつくといった二次的な問題に発展するリスクもあります。
叱る代わりに、「何があったの?」と背景にある感情や状態に目を向け、環境調整などの物理的な対策を進めるほうが、はるかに建設的です。
Q
これは「摂食障害」なのでしょうか? 違いが分かりません。
A
非常に重要なご質問です。両者は重なる部分もありますが、根本的な動機が異なる場合があります。発達障害の特性からくる盗み食いは、「衝動性」や「感覚探求」が主な動機であることが多いです。一方で、思春期以降に見られる摂食障害(特に過食症)は、「太ることへの強い恐怖」や「体型へのこだわり」「極端なダイエットの反動」といった心理的な葛藤が背景にあることが多いとされます。ただし、衝動性が摂食障害のリスクを高めることも事実です。行動がエスカレートする場合や、体重の極端な増減、食べた後に吐く(排出行動)などの様子が見られる場合は、境界が曖昧なことも多いため、速やかに児童精神科や心療内科などの専門医に相談してください。
Q
家での盗み食いが、お店での万引きに発展しないか心配です。
A
衝動性のコントロールが難しいという根本的な課題が未解決のままだと、その行動が別の形で現れる「般化」という現象が起きる可能性はゼロではありません。
家庭内の「盗み食い」というルール違反が、社会的な「万引き」というルール違反へとエスカレートするリスクは、理論的には存在します。
だからこそ、「家庭内のことだから」と問題を軽視せず、この記事で紹介したような行動分析や環境調整、スキル育成といった早期の対策が、将来のより大きなリスクを防ぐための「予防的介入」として極めて重要になるのです。
Q
薬でこの行動は治りますか?
A
「盗み食い」そのものに直接効く、という魔法のような薬は残念ながら存在しません。
薬物療法は、あくまで背景にある発達障害の特性、特にADHDの「衝動性」や「多動性」を緩和することを目的に処方されます。
薬によって衝動の波が穏やかになることで、本人が一瞬立ち止まって考える余裕が生まれたり、行動療法やカウンセリングの効果が出やすくなったりします。
薬は、あくまで本人がスキルを学びやすくなるための「土台を整える」役割と考えるのが適切です。
治療の選択肢として検討する場合は、必ず専門の医師と相談し、その効果と副作用について十分に説明を受けてください。
まとめ:試行錯誤こそが、わが家だけの「正解」になる
今回紹介した方法は、あくまで一般的なヒント集です。
お子さんの特性や家庭環境によって、合う・合わないが必ずあります。
大切なのは、いろいろな方法を試してみることです。
そして、うまくいかなくても自分や子どもを責めず、「じゃあ、次はこうしてみようか」と工夫を続けること。
その試行錯誤のプロセス自体が、親子関係を深め、わが家だけの「最適解」を見つける唯一の道なのだと思います。
それでも一人で抱えるのが難しいと感じたら、決して無理はしないでください。
かかりつけの小児科医や、お住まいの地域にある発達障害者支援センター、児童発達支援事業所など、専門家の力を借りましょう。
今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。