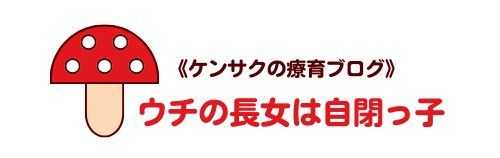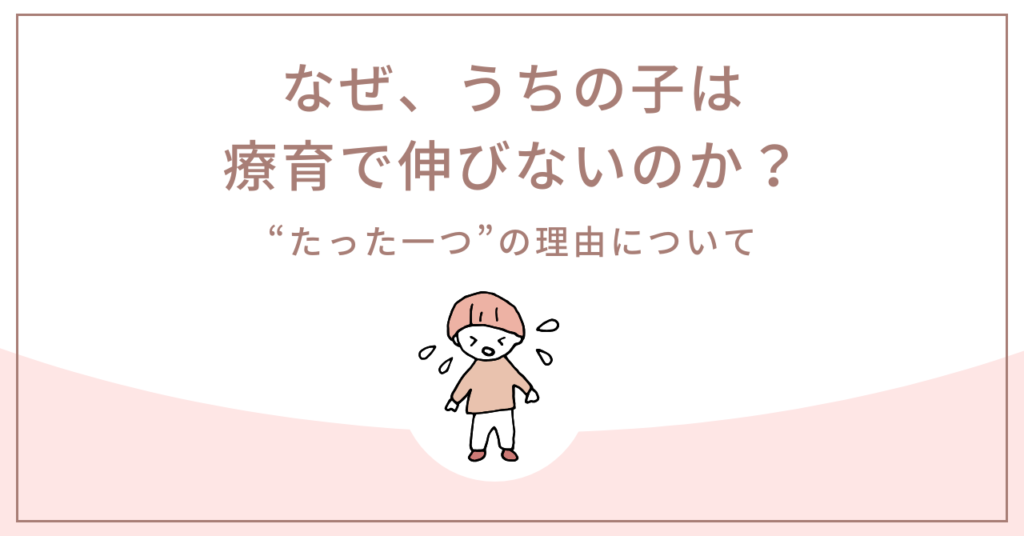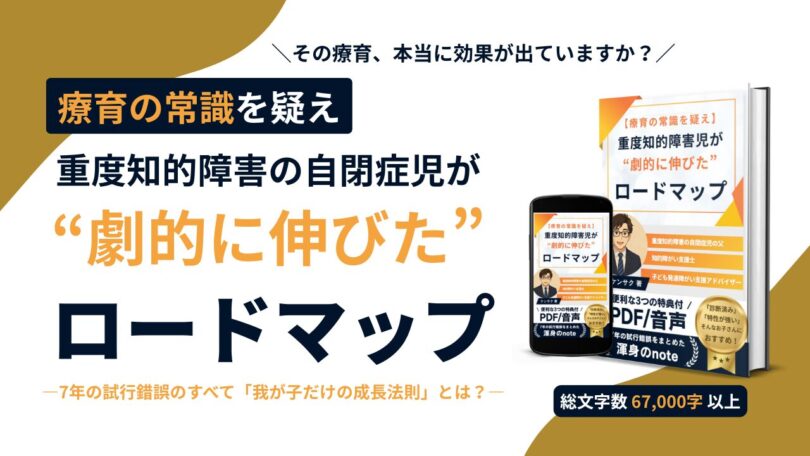子どもの成長を支えるために始めた「療育」。
通い続ける中で、ふと気になるのが「卒業のタイミング」です。
特に年長の3月や小学校入学を控える頃になると、「いつまで続ければいいの?」「卒業して大丈夫なのかな?」と迷う親御さんも少なくないでしょう。
実際、療育の卒業は一律のルールで決められるものではなく、制度上の目安と、子ども一人ひとりの発達や環境によって判断が分かれます。
生活スキルや社会性がどの程度身についているか、専門家の評価や家庭での様子などを総合的に見極めることが大切です。
また、「卒業=支援が終わり」ではありません。
むしろ、放課後等デイサービスや特別支援学級など、次のステージにつなぐ準備を意識することが安心につながります。
実は、発語のない娘を持つ私も、療育の卒業時には「この先、本当に大丈夫だろうか」と大きな不安を抱えていました。
- 療育の卒業を考える際、まず知っておきたいこと
- 療育卒業の判断基準・タイミング
- 療育卒業後にやるべきこと
このブログ記事では、制度や一般的な基準に加え、そんな我が家がどうやって不安を乗り越え、次の一歩を踏み出したのか、具体的な体験談も交えてお届けします。

目次
療育卒業のタイミング【基本ルールと制度的目安】

療育の卒業を考える際、まず知っておきたいのが「制度上の区切り」と「実際の判断のされ方」です。
療育には法律上の対象年齢や利用期間が定められており[1]、そのルールに沿って卒業を迎えるケースが多い一方で、子どもの発達や家庭の事情によって調整が可能な場合もあります。
ここでは制度的な目安と、現場でよく見られる卒業の形を解説します。
制度上の卒業タイミングとは?
療育(児童発達支援)は、発達に特性のある未就学児が利用できる福祉サービスです。
原則として、小学校入学を迎える年長の3月末で利用が終了となるのが一般的となっています[2]。
この「年長の3月卒業」が、多くのご家庭が意識する最初の区切りになります。
たとえば保育園や幼稚園を卒園するのと同じ時期に療育も終了することで、「就学準備」として気持ちの切り替えがしやすいというメリットもあります。

ただし一律ではなく、地域や事業所によっては多少の柔軟性があります[3]。
たとえば「小学校生活に慣れるまでの数か月だけ利用を延長できる」といったケースや、「就学後は放課後等デイサービスにスムーズに移行できるように調整する」といった対応。
つまり制度は目安であって、必ずしもその日を境に完全に終了というわけではないんです。

フェードアウト型の卒業もある
療育を卒業する際に、いきなりゼロにするのではなく「フェードアウト型」で進めるケースも少なくありません[3]。
たとえば、それまで週3回通っていた子が、卒業前の数か月は週1回に減らし、徐々に利用を減らしていきます。
こうすることで、子ども自身も生活リズムの変化に無理なく適応でき、保護者も安心して見守ることができます。
また、自治体によっては「就学準備支援」という名目で、入学直後の数週間〜数か月だけ療育を続けられる制度を設けているところもあります。
特に集団生活が苦手なお子さんや、新しい環境に不安を感じやすいタイプのお子さんにとっては、この移行期間がとても重要になんです。
制度の目安はあくまで参考、実際は個別判断
大切なのは、制度上の年齢制限や卒業時期はあくまで「目安」であり、実際には子どもの発達段階や家庭の状況に応じた判断が必要だということです。
たとえば同じ年長児でも、ひらがなや数字がスムーズに理解できている子もいれば、まだ身の回りの支度にサポートが必要な子もいます。
制度だけで卒業を区切ると、「まだ支援が必要なのに終わってしまった」という不安につながりかねません。

そのため、実際には、療育事業所のスタッフや医師、心理士などの専門家と保護者が相談しながら「このタイミングで卒業しても良いかどうか」を判断します[4]。
また、就学先の小学校との連携も欠かせません[12]。
支援学級や通級指導を利用するかどうか、放課後等デイサービスとどうつなぐかといった「次のステップ」を視野に入れた卒業判断が求められます。
卒業は「制度」+「子どもに合わせた柔軟さ」
療育の卒業には、確かに「年長の3月まで」という制度的な区切りがあります。
しかし、それはあくまでスタート地点にすぎません。
本当に大切なのは、子どもが安心して次の生活に移れるかどうか、そして保護者が納得して卒業を迎えられるかどうかです。

「制度に合わせて急いで卒業する」のではなく、子どもの成長に寄り添いながら、専門家や学校と相談して決めること。
それが、後悔のない卒業につながる第一歩といえるでしょう。
療育卒業を判断するための「主な基準」

療育の卒業は「年齢」や「制度」だけで一律に決まるものではありません。
実際には、子どもの発達状況や日常生活での自立度合いを確認しながら、保護者と専門家が一緒に見極めていくことが大切です。
ここでは、卒業の判断材料としてよく挙げられる3つの基準を紹介します[5]。
生活スキルと自立性が備わっているか
まず重要なのは、日常生活の基本的なスキルがどの程度身についているかという点です。
- 着替えや歯みがき、片づけといった「身辺自立」
- 食事や排泄が一人でできるか
- 毎日の生活リズムを自分で整えられるか
こうしたスキルが安定して身についていると、小学校生活でも安心して集団活動に参加しやすくなります。

逆に、まだ大人の手助けが必要なことが多い場合は、卒業を急がずにサポートを続けるほうが子どもにとって無理がありません。
療育では「自立に向けたスモールステップ」が重視されます。
たとえば、歯みがきであれば「歯ブラシを持つ→磨き始める→仕上げ磨きを減らす」といった段階を確認し、できることが増えているかを見ていくのがポイントです。
対人関係やソーシャルスキルの獲得状況
次に見ておきたいのが、他者との関わり方や集団生活への適応力です。
小学校に進学すると、同年代の子どもたちと長時間一緒に過ごすことになります。
そのため、以下のような力がどの程度育っているかが判断基準になります。
- 相手の話を聞く、順番を待つなどの基本的なルール理解
- 困ったときに「助けて」と言える表現力
- トラブルが起きたときに感情をコントロールする力
療育の場では、ソーシャルスキル(SST:Social Skills Training)の一環として、ロールプレイやグループ活動を通じてこれらの力を育てています[6]。
卒業を考える際は、「ひとりで過ごせる」だけでなく「仲間と協調できるか」という視点が欠かせません。

家族や専門家と相談した総合的評価がカギ
最後に大切なのが、複数の視点からの総合的な判断です。
療育の現場には、保育士・言語聴覚士・作業療法士・心理士など多様な専門家が関わっています。
それぞれが子どもの成長を観察し、保護者と意見をすり合わせながら「卒業しても大丈夫かどうか」を検討します。
- 専門家判断の重要性
発達の凸凹は家庭だけでは気づきにくいことがあります。
専門家が客観的にチェックすることで、卒業後に困りごとが再燃するリスクを減らすことができます。 - 家庭・学校との連携
小学校との連携も不可欠です。
特別支援学級や通級指導を利用する予定がある場合、療育の卒業時期をそれに合わせて調整するケースも少なくありません。
学校での様子をフィードバックしながら判断できると、より安心です。
判断を急がず「子どものペース」に合わせる
ここまで見てきたように、卒業の基準は「生活スキル」「ソーシャルスキル」「総合的な評価」の3本柱に基づいて考えるのが一般的です。
しかし、これらはあくまで目安であり、「周りが卒業するから」「年齢だから」といった理由だけで判断するのはおすすめできません。
むしろ大切なのは、子ども本人のペースを尊重すること。
「少し時間はかかっても、確実に自信を積み上げてから卒業する」ほうが、その後の学校生活や社会生活につながりやすいんです。
卒業基準は「できること」+「安心感」
療育の卒業を判断する基準は、単に「何歳になったから」ではなく、
- 自分のことをある程度一人でこなせるか
- 仲間と協力して生活できるか
- 家族や専門家が「大丈夫」と思えるか
この3つが重なったときに「卒業しても安心」といえます。

つまり、卒業とはゴールではなく「次の生活への移行」。
子どもにとって安心できる橋渡しになるよう、焦らず慎重に判断していくことが大切です。
療育の“やめどき” – タイミングの見極め方

療育の卒業は「卒園と同時に」「年長の3月末に」と制度的に決まっている部分もありますが、実際にはそれだけで判断できるものではありません。
子どもの発達や家庭の状況を見ながら、どのタイミングで卒業するのがよいのかを見極める必要があります。
年長の3月がゴール? でも焦らず6月まで様子を見るのも手
多くのご家庭がまず意識するのは、やはり年長の3月末です。
就学を機に卒業するのは自然な流れであり、保育園や幼稚園の卒園と重なることで気持ちの区切りもつけやすいからです。
しかし、必ずしも「3月で終わり」が正解とは限りません[7]。
小学校に入学した直後は、環境の変化や集団生活のルールに適応するまでに時間がかかる子どもも多いもの。
特に発達に特性がある場合は、新しい環境に慣れるまで数か月かかることは珍しくありません。

そのため、あえて小学校入学後の4月〜6月まで療育を継続し、学校生活に慣れてから卒業するという選択肢もあります。
こうすることで、子どもも保護者も安心して「やめどき」を迎えられるんです。

生活や学びに余裕が見えてからの卒業が安心
卒業を考えるうえで大切なのは、「子どもに余裕があるかどうか」です。
たとえば、
- 学校から帰ってきて疲れていても、自分のことをある程度こなせる
- 宿題や学習に取り組む気持ちの切り替えができる
- 友達との関係で大きなトラブルが少なくなってきた
こうした「生活の余裕」が見えてきたら、卒業を考えるサインと言えるでしょう。
逆に、日常生活にまだ課題が多い場合や、学校と家庭の両方でサポートが必要な場合は、卒業を延長したほうが安心です[8]。
卒業後に困らないための“見極め”のコツ
- 一時的な成長に惑わされない
発達の伸びは一気に見える時期もありますが、それが安定して続いているかを確認することが大切です。 - 専門家の意見を複数取り入れる
療育の先生だけでなく、学校の先生や医師、心理士の意見も参考にすると偏りがなくなります。 - 家庭でのサポートのしやすさを考える
「卒業後も家庭で支えられるかどうか」は現実的な判断基準です。
もし家庭だけでは不安なら、もう少し療育を続けて安心材料を増やすのもよい選択です。
卒業は「子どものペース」で決めるのがベスト
周囲の子どもが卒業していくと、「うちもそろそろ……」と焦る気持ちになる親御さんも多いでしょう。
しかし、卒業のやめどきは 「他人のペース」ではなく「子どものペース」 に合わせることが一番大切です。
子どもが自信を持って次のステージに進めるように、焦らずじっくり見守りましょう。
数か月延長したとしても、それが将来の安心につながるなら十分に価値があります。
やめどきは「環境に慣れて余裕が出たとき」
療育の卒業は、年長の3月を一つの目安にしつつも、
- 学校生活に慣れたかどうか
- 日常に余裕が出てきたか
- 保護者が安心して見守れるか
これらを基準に考えるのが安心です。

やめどきを焦らず、子どもに合ったペースで進めることで、卒業が「不安」ではなく「自信」につながる瞬間になります。
療育卒業後、すぐにできる「次の一歩」の準備
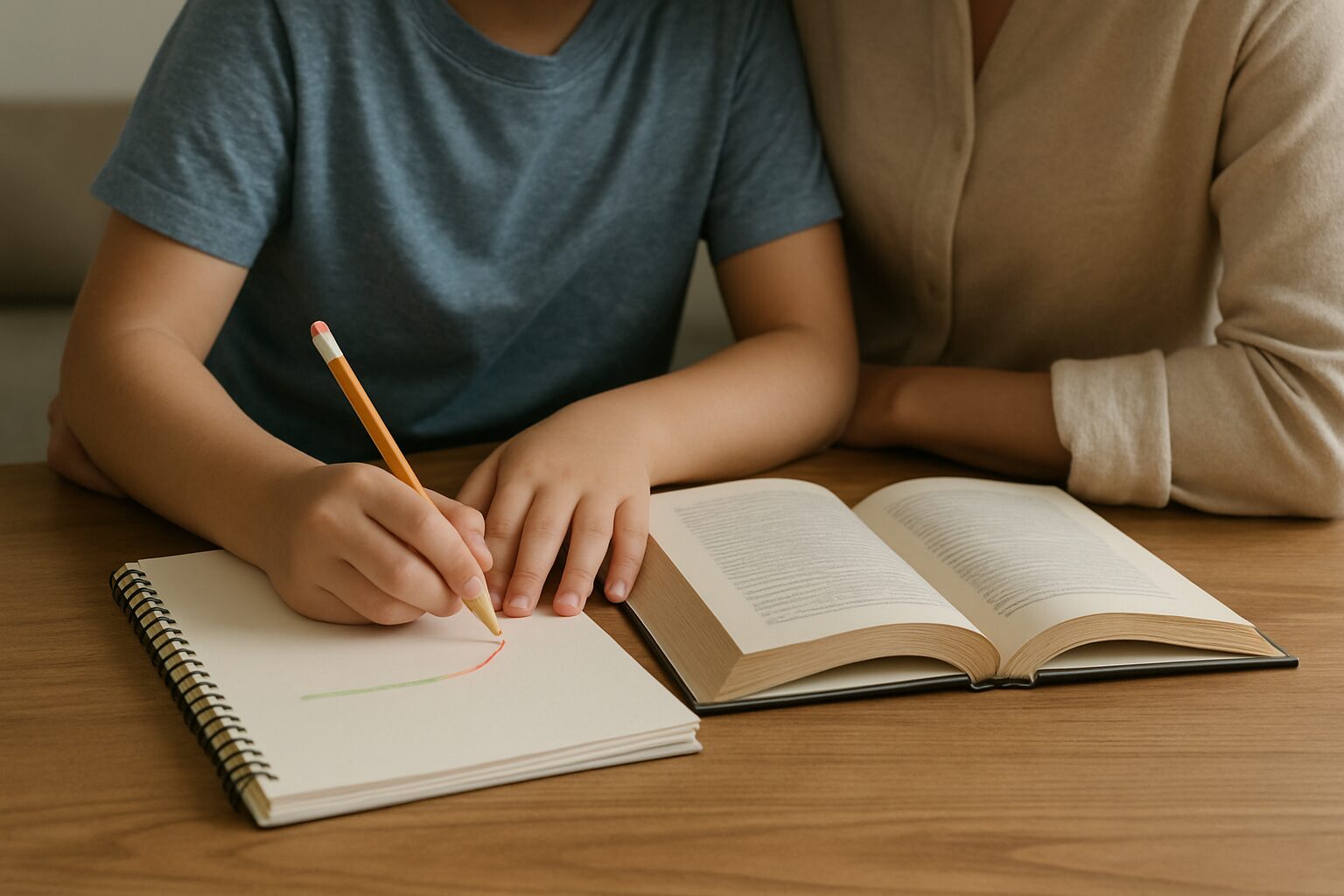
療育を卒業すると、「これからは家庭だけでやっていくのかな?」と不安になる親御さんは少なくありません。
しかし、療育が終わった後にも子どもを支える仕組みは用意されています。
卒業を「終わり」と捉えるのではなく、「次のステージへの移行」と考えることで、子どもも親も安心して歩みを進められるんです。
ここでは、卒業直後に取り入れやすい支援や準備について紹介します。
小学生になって利用できる支援制度
療育(児童発達支援)は未就学児が対象ですが、就学後は利用できる別の制度があります。
代表的なのが放課後等デイサービスと学校での特別支援制度です[9]。
放課後等デイサービス(放デイ)
放デイは小学生から高校生までが利用できるサービスで、放課後や長期休暇中に療育的な支援や学習サポートを受けられます。
集団活動を通じてソーシャルスキルを伸ばしたり、生活習慣の定着を支援してもらえるのが特徴です[10]。
療育からの移行先として利用する家庭は多く、「卒業して終わり」ではなく「形を変えて継続する」感覚で利用できます。
特別支援学級・通級による支援
学校の制度としては、発達に特性のある子ども向けに「特別支援学級」や「通級指導教室」が設けられています。
たとえば、国語や算数は通常学級で学び、週に数時間だけ通級で個別指導を受けるといった柔軟な形が可能です。
学校と家庭、そして療育の経験をつなげることで、スムーズな学習環境を作ることができます[11]。
家庭でできる支援とフォローの仕組み
制度だけに頼らず、家庭でもできる工夫を取り入れておくと、卒業後の安心感がぐっと増します。
安心感と相談できる関係づくり
子どもにとって大切なのは「困ったときに相談できる人がいる」という感覚です。
家庭内で「失敗しても大丈夫」「助けてと言える」雰囲気を作っておくと、卒業後の不安が軽減されます。
また、地域の発達支援センターや相談窓口とつながっておくと、必要なときにすぐ相談できて安心です。
生活の見える化・感情サポート
家庭での支援の一つに「生活の見える化」があります。
予定をカレンダーやカードで示すことで、子どもが先の見通しを持ちやすくなります。
また、気持ちを色カードやイラストで表現する習慣を取り入れると、感情の整理がしやすくなり、トラブルの予防につながります。
卒業後の「移行期間」を上手に活用する
卒業後、すぐにすべてを切り替える必要はありません。
むしろ、数か月間は「移行期間」として、療育で学んだことを生活に定着させる意識が大切です。
- 学校で困ったことを家庭で話し合う
- 療育で使っていた支援ツールを家庭でも継続する
- 必要に応じて相談支援事業所にアドバイスをもらう
こうした「つなぎの工夫」をすることで、卒業後の不安を最小限に抑えられます[13]。
卒業後の準備は「新しい支援につなぐ」こと
療育を卒業したあとも、子どもを支える選択肢はたくさんあります。
- 放課後等デイサービスで継続的にサポートを受ける
- 学校の特別支援制度を活用する
- 家庭でできる支援を取り入れる
- 地域や専門機関と相談できる関係を持っておく

これらを組み合わせることで、卒業が「支援の終わり」ではなく「次のステップの始まり」となります。
子どもにとっても保護者にとっても安心感が増し、自信を持って小学校生活をスタートできるでしょう。

療育卒業経験者の声から学ぶ成功・注意ポイント

療育の卒業は制度的なルールや専門家の判断だけではなく、実際に経験した家庭の声がとても参考になります。
先輩保護者の体験談からは、「スムーズに卒業できた成功例」と「少し早すぎて後悔したケース」の両方を知ることができます。
ここでは、実際の声をもとに、卒業の際に気をつけたいポイントを整理してみましょう。
体験談:無発語の娘の卒業、一番の不安と「次への準備」
実は、我が家の長女も幼稚園の卒園と同時に、児童発達支援を卒業しました。
娘には発語がなく、当時は「言葉で気持ちを伝えられない娘が、小学校という新しい環境で本当にやっていけるだろうか」という不安でいっぱいだったのを、今でも鮮明に覚えています。

周りがスムーズに卒業していく中で、「うちの子は本当に大丈夫?」という焦り。
それは、制度や理屈だけでは割り切れない、親としての正直な気持ちでした。
そこで私たちが卒業前に最も力を入れたのが、「小学校生活が始まっても、安心して学び、過ごせる環境を確保する」ことでした。
具体的には、
- 発達支援の継続:
小学生になっても通える療育(放課後等デイサービス)を探し、娘の成長を止めないための場所を確保。 - 安心できる居場所づくり:
学習支援だけでなく、心から安心して過ごせる「居場所」としての役割を担ってくれる放課後等デイサービスも見学し、契約。
この2つの準備があったからこそ、「卒業=支援の終わり」ではなく、「新しい支援につなげる」という前向きな気持ちで、小学校の入学式を迎えることができました。
卒業時の不安が大きかったからこそ、早めに動き出し、「次の支え」を具体的に用意しておくことの大切さを、身をもって感じています。

「卒園と同時に自然に卒業できた」成功例
知り合いのとある家庭では、幼稚園の卒園と同時に療育を終了しました。
子どもは年長の後半から身辺自立や友達との関わりが安定し、小学校の入学準備も順調だったため、専門家からも「卒業して大丈夫」というお墨付きをもらえたそうです。
この家庭がスムーズに卒業できた理由は、
- 卒業時期を「卒園」とリンクさせて自然な流れを作った
- 専門家・家庭・学校が同じ方向を向いて準備した
- 子ども本人が「小学生になる!」という前向きな気持ちを持てた
という点にあります。
卒業を「終わり」と感じるのではなく「次のステージに進む」という前向きな移行としてとらえることで、子どもも保護者も安心して切り替えができたんです。
「判断が早すぎて困りごとが再燃した」注意すべきケース
一方で、卒業を早めに決断した結果、困りごとが再び表面化したケースもあります。
たとえば「年齢的にもう卒業のはず」と周囲に合わせて卒業した子が、小学校に入学してから学習のつまずきや集団生活でのトラブルに直面したという例があります。
家庭では「療育を続けていればサポートできたのに」と後悔の声も少なくありません。

このようなケースから学べるのは、制度や年齢だけを基準にせず、子どもの発達や環境への適応を冷静に見極める必要があるということです。
特に環境の変化が大きい小学校入学時は、「卒業を急がず数か月様子を見る」という柔軟さが安心につながります。
成功・失敗の分かれ道になるポイント
体験談を見比べると、卒業がスムーズに進むかどうかにはいくつかの共通点があります。
- 専門家と家庭が同じ視点を持てていたか
卒業の判断を事業所任せにせず、保護者が積極的に話し合いに参加することが成功の鍵になります[14]。 - 卒業後の生活設計を描けていたか
放課後等デイサービスや学校の支援体制につなげる準備をしていた家庭は、卒業後の不安が少ない傾向にあります。 - 子ども本人が安心して進めたか
「卒業したい」「小学生になる準備ができた」という本人の気持ちを尊重すると、移行がスムーズになります。
保護者が意識したい心構え
卒業は保護者にとっても大きな節目です。
体験談からは、「もっと準備しておけばよかった」と感じる声と、「早めに情報を集めておいて安心できた」という声が分かれています。
その違いを生んでいるのは、卒業を“突然の終わり”ではなく“段階的な移行”ととらえられたかどうかです。
卒業前から学校や地域のサービスについて情報を集め、つなぎ先を見つけておくと、子どもも保護者も安心して次のステップに進めます。
体験談から見える「準備と柔軟さ」の大切さ
療育卒業経験者の声から学べるのは、
- 卒園とリンクさせることで自然に卒業できる
- 卒業を急ぐと困りごとが再燃するリスクがある
- 成功には「専門家との連携」「卒業後の準備」「子どもの気持ちの尊重」が不可欠
ということです。
卒業の正解は一つではありません。

大切なのは「家庭と子どもにとって安心できるペース」で進めること。
経験者の声を参考に、焦らず柔軟に「やめどき」を見極めていきましょう。
まとめ — 卒業は終わりではなく“次のステージへの移行”
療育の卒業という言葉を聞くと、「もう支援が受けられない」「ここで終わり」というイメージを持つ方も少なくありません。
しかし実際には、卒業は子どもにとっての“ゴール”ではなく、“新しいステージへの移行”を意味しています。
療育卒業はゴールではなく、次へのステップ
療育を通じて身につけた生活スキルやソーシャルスキルは、これからの学校生活や社会生活の土台になります。
卒業はその成果を次の環境で発揮するスタート地点です。
- 小学校入学に合わせて卒業する子どもは、新しい集団生活に挑戦する第一歩を踏み出す瞬間
- 放課後等デイサービスにつなぐ家庭では、継続的な支援を受けながら新しい学びを重ねるタイミング
- 家庭での支援に重点を移す場合も、「子どもを見守る力を親が身につける」という成長のチャンス
つまり、卒業は「支援の終了」ではなく「支援の形を変える」だけなんです。
家庭・学校・支援機関との連携で「安心の卒業」を
卒業を安心して迎えるためには、家庭だけで抱え込まず、学校や地域の支援機関と連携することが欠かせません。
- 学校の先生にこれまでの支援内容を共有する
- 放課後等デイサービスや通級とつなげる
- 必要に応じて相談支援事業所に伴走してもらう
こうした連携を積極的に作っておくと、子どもは「自分を支えてくれる人がいる」という安心感を持てます。
保護者自身も「困ったら相談できる」という余裕があることで、不安を抱え込まずに済みます。
卒業は子どもと家庭の新しいスタート
療育卒業のタイミングに正解はありません。
大切なのは「子どもが自分らしく次のステージに進めるかどうか」です。
- 制度上の目安を参考にしつつ、子どものペースに合わせる
- 専門家・学校・家庭で意見を共有し、総合的に判断する
- 卒業後の支援先やフォロー体制を準備しておく
この3つを意識すれば、卒業は不安ではなく希望に変わります。

療育を通じて積み上げた力を信じて、子どもと一緒に新しい一歩を踏み出しましょう。
卒業は「終わり」ではなく、「未来への架け橋」なんです[15]。

脚注
[1] こども家庭庁「障害児支援」総合ページ(制度全体の入口・継続更新)
[2] 児童発達支援ガイドライン(令和6年7月、公表)「主に未就学」等を明記(PDF)/補足:厚労省「就学前障害児の発達支援の無償化」
[3] 令和6年度 障害福祉サービス等報酬改定Q&A(移行期の短時間等の取扱い)/ 参考:国立障害者リハ「就学前後の移行期における情報連携ガイドライン」
[4] 児童発達支援ガイドライン等の概要(相談支援へ計画交付・担当者会議)/ ガイドライン本文(モニタリング・見直し)は[2]参照
[5] 児童発達支援ガイドライン(評価・連携)[2]参照/こども家庭庁「障害児支援施策」
[6] 系統的レビュー(SST群介入の効果、ASD 6–21歳)PubMed抄録 /総説(Psychiatric Clinics of North America, 2020)抄録
[7] 児童発達支援ガイドライン(就学移行と教育連携)[2]参照/文科省「教育と福祉の連携について」
[8] ガイドライン(相談支援のモニタリング→計画見直し)[2]参照
[9] 放課後等デイサービス ガイドライン(こども家庭庁ポータル)/特別支援教育の現状(制度入口)
[10] 放課後等デイサービスガイドライン(詳細版・PDF)/概要版(PDF)
[11] 通級による指導ガイド(公式ポータル)/障害のある子供の教育支援の手引(令和3年改訂)
[12] 文科省「学校における合理的配慮」対応指針ページ /内閣府「合理的配慮の提供が義務化」リーフレット
[13] こども家庭庁「障害児支援」ページ(切れ目ない支援)/ 文科省「教育・福祉の連携 事例集(2025)」