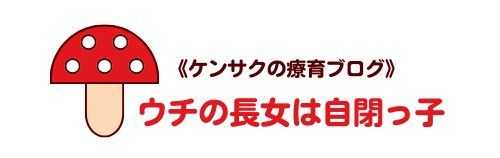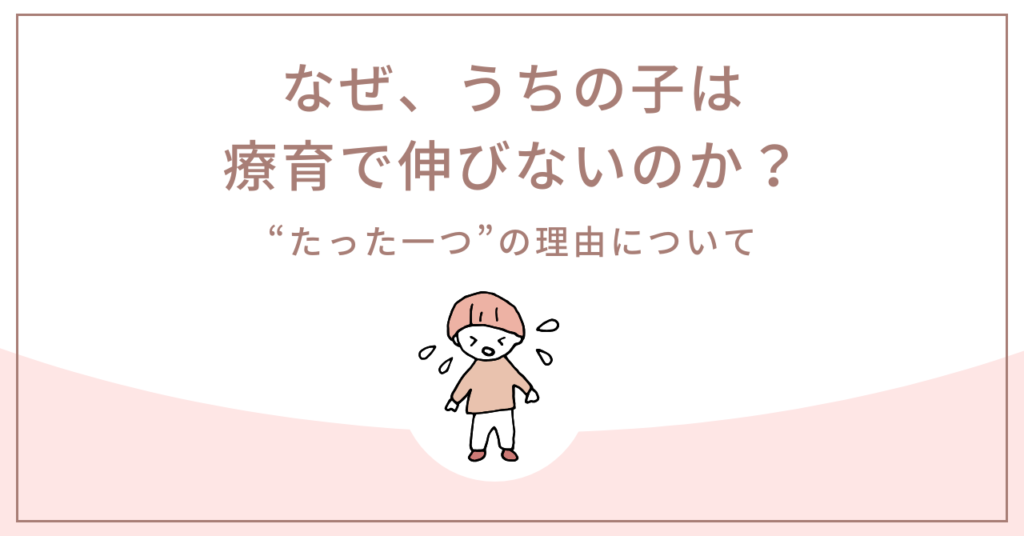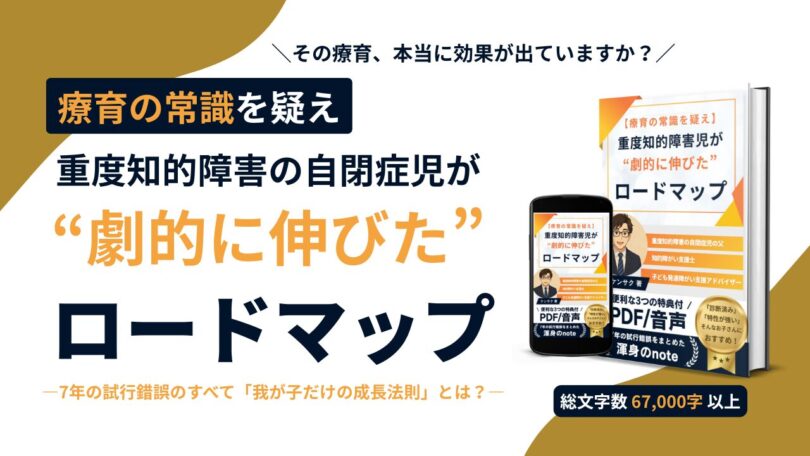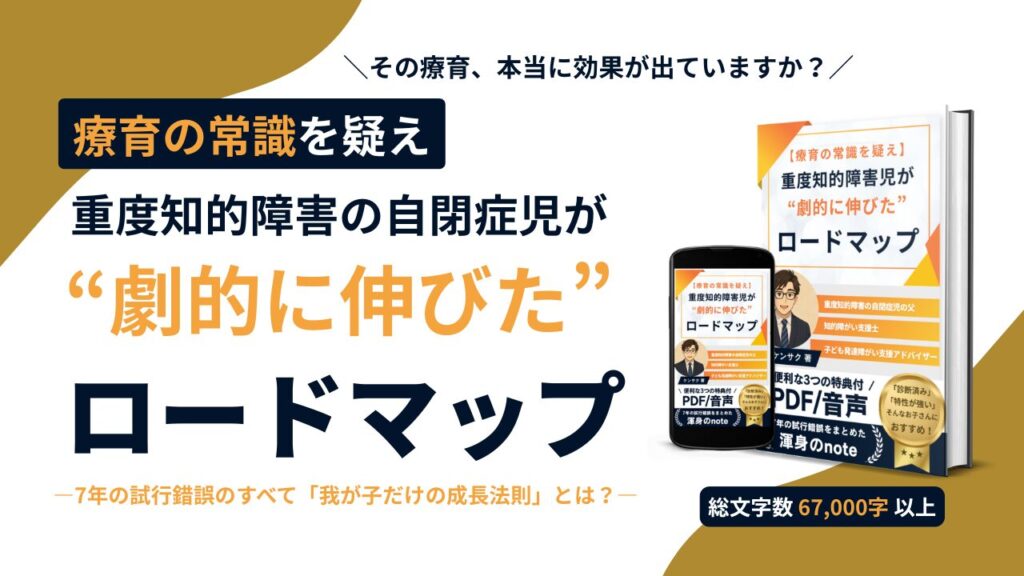「うちの子、このままで大丈夫なんだろうか」
「療育に通っているのに、思ったように成長してくれない」
「他の子と比べてしまって、焦りと不安でいっぱいになる」
これは、決してあなただけの悩みではありません。
むしろ、お子さんの発達に不安を抱えている、多くの親御さんが同じような気持ちを胸に、日々子育てと向き合っています。
我が家にも、重度の知的障害を伴う自閉症の娘がいます。
現在8歳になりますが、彼女の育児を通じて、数え切れないほどの不安や迷いに直面してきました。
支援の専門家ではなく、ひとりの親として言えることがあります。

それは、「努力していない親なんていない」ということです。
早期発見・早期療育の重要性が叫ばれる現代では、多くのご家庭が療育施設に通い、支援を受けることが当たり前になりつつあります。
その中で、週に何回も通っているにもかかわらず、
「思うような変化が見られない」
「むしろ子どもが嫌がってしまう」
という声も少なくありません。
努力しているのに成果が見えにくい──
その状況は、親の心を大きく消耗させ、時には「自分の関わり方が間違っているのでは」と自責の念に駆られることもあるでしょう。
ですが、そのようなときこそ、一度立ち止まって“ある視点”を持ってみてほしいんです。

それが、「子ども自身の“受ける準備”ができているか?」という視点です。
つまり、どんなに優れた療育メソッドであっても、それを受け取る子どもの「土台」が整っていなければ、うまく活用できないということ。
逆に言えば、「土台さえ整えば、どんな療育もその子なりに効果を発揮しやすくなる」とも言えます。
この記事では、その“土台づくり”の重要性と基本原理に絞ってお伝えしていきます。
実際に私が7年間の子育てを通じて体感したこと、そして同じように悩む保護者の方々にお伝えしたいことを、できるだけわかりやすくまとめました。
特別な専門知識は必要ありません。
「療育に通っているけれど結果が出ない」と感じている今だからこそ、知ってほしい本質的な考え方です。
どうか、焦らず、そして比べず。
我が子の可能性を信じて、読み進めてみてください。
目次
なぜ“通うだけの療育”では限界があるのか?
「週に3回、きちんと療育に通っている」
「専門家に任せていれば、きっと成長していくはず」
そんな風に信じて、日々送迎や支援を頑張っている方はとても多いと思います。
ですが、現実には、
「なかなか成果が感じられない」
「むしろ疲れているように見える」
という声も少なくありません。
これは決して療育施設や専門家の力が足りないわけではなく、“構造上の限界”とも言える問題があるからです。
まず、現在の療育支援の大半は「時間的にも物理的にも限られている」という現実があります。
1回の療育はせいぜい1〜2時間。
週に何回通ったとしても、その子の一週間のうちのごくわずかな時間しか支援されないことになります。
その間だけ一時的に姿勢や集中力が整ったとしても、日常生活に戻るとリセットされてしまう──こうした“断片的な支援”では、成長の実感が得られにくくなってしまうんです。
もうひとつの問題は、「療育が家庭とつながっていないこと」です。
多くの親御さんは、「施設に通わせていれば大丈夫」と信じてしまいがちですが、療育の効果が日常にまで浸透するためには、“家庭との連携”が不可欠です。
家庭での声かけや生活の流れ、子どもとの信頼関係など、家の中でこそ整えるべき土台があります。
しかし現実には、療育内容が家庭にうまく伝わっていなかったり、どうフォローすればいいか分からなかったりするケースが多く見られます。
さらに、子ども自身の「受ける準備」が整っていない場合、せっかくの療育も負担になってしまうことがあります。
たとえば、生活リズムが安定していない、過敏さや不安が強すぎて場に入れない、信頼関係が築けていないなど、子ども側の土台が整っていない状態で支援を受けても、うまくいかないのは当然のことです。
これは、私自身が実際に痛感してきたことでもあります。
娘を療育に通わせながら、「この時間は意味があるのだろうか」と感じることもありました。
先生方は一生懸命取り組んでくれているのに、娘がうまく応じられない。
帰ってくるとぐったりしていて、家庭でも癇癪が増える。
それでも「通うことに意味があるはず」と信じ、頑張っていました。
ですが、あるときふと「この子自身、そもそも“支援を受けられる状態”になっているのか?」と考え始めたことが、すべての転機でした。

つまり、「療育の前に必要なことがあるのではないか」という視点に立ったんです。
それが、次にお話しする「療育を受ける体づくり」の大切さにつながっていきます。
本当に子どもの可能性を引き出すためには、“通うだけ”ではなく、“整えること”が必要なんです。
療育の効果が出る子と出ない子の違いとは?
同じように療育に通っていても、「すぐに変化が現れる子」と「なかなか変化が見られない子」がいる。
この違いは一体、どこから生まれてくるんでしょうか。
多くの方が思い浮かべるのは、「特性の強さ」や「知的な遅れの有無」などの発達レベルの違いかもしれません。
もちろん、それらも一定の影響はあります。
しかし、私が7年間娘の育児と療育に向き合ってきた経験からお伝えしたいのは、“それ以前の条件”が、大きな分かれ目になっているということです。
その“それ以前の条件”とは、ずばり──

「療育を受ける側の準備が整っているかどうか」です。
療育は決して魔法ではありません。
子どもが主体的に関わり、少しずつ環境に慣れ、信頼関係を築きながら課題に取り組んでいくプロセスがあってこそ、効果を発揮するものです。
そしてその前提には、「落ち着いて座っていられる」「人の話を受け止められる」「環境に過敏すぎない」など、心身の“受け皿”が整っている必要があります。
この「受け皿」のことを、私は「土台」と考えます。
療育がうまくいく子は、この“土台”がある程度整っているため、支援の中で起きる学びや刺激をしっかり吸収することができるんです。
一方で、この土台がまだ整っていない子にとっては、療育そのものが「負荷」になってしまうことすらあります。
たとえ内容が素晴らしくても、受ける側がキャッチできる状態でなければ、成長につながりにくいんです。
ここで誤解してほしくないのは、「土台がない=親の努力が足りない」という話では決してないということです。
むしろ、多くの親御さんは懸命に努力されているからこそ、「なぜ結果が出ないのか」と悩んでいるんです。
だからこそ必要なのは、“メソッド”よりも先に“土台”という視点を持つこと。
どんなに優れたトレーニング法でも、それを受け取る準備が子どもにない状態では、望む効果は出にくいという現実に、一度しっかり目を向けてみてほしいんです。
この視点を持つようになってから、私自身の関わり方も大きく変わりました。
以前は、
「どうすれば言葉が増えるか」
「どうしたら椅子に座っていられるか」
と、“できること”にばかり目を向けていたんですが、今では「この子が安心して支援を受けられる状態になっているか?」という“状態そのもの”を整えることに意識を向けています。
そして不思議なことに、その意識の変化が娘にも良い影響を与え始めたんです。
では、具体的に「療育を受ける体づくり=土台づくり」とは何なのか。
その中身を詳しく解説していきます。
「療育を受ける体づくり」とは何か?
これまでお伝えしてきた通り、療育の効果を左右する最も重要な要素の一つが「受ける側=子ども自身の準備状態」です。
では、その“準備”とは具体的に何でしょうか?
ここでいう「療育を受ける体づくり」とは、単に「体が健康である」や「椅子に座れる」といった表面的な条件だけではありません。
もっと深いところ──
たとえば「安心感」「自己肯定感」「予測可能な環境」「睡眠や食事などの生活の安定性」など、心と身体の土台が安定している状態のことを指します。
私がこれを意識するようになったきっかけは、ある日の療育での出来事でした。
娘は当時、支援の場に入ってもなかなか指示が通らず、何をするにも落ち着かずにその場をうろうろしてしまっていました。
先生方は丁寧に対応してくださっていたんですが、私の中にはどこか「なぜできないんだろう」「もっと頑張ってもらいたい」という焦りがありました。
ところが、ある支援者の方が何気なく言った一言が、私の考え方を大きく変えました。
「もしかしたら、〇〇ちゃんは“療育を受ける準備”がまだできていないだけかもしれませんね。」
その言葉に、私はハッとしました。
それまでは「どんな支援をするか」「どんな方法が効果的か」ばかりを考えていたんですが、「この子がそもそも支援を“受け取れる状態”になっているか?」という視点が、まったく抜け落ちていたんです。
具体的には、以下のような状態を「土台が整っている」と私は捉えています。
- 安心できる関係性があること
支援者や親との間に信頼関係があることで、指示や働きかけに対して不安や抵抗が少なくなります。 - 日常生活のリズムが安定していること
睡眠・食事・排泄といった基本的な生活が整っていると、心身ともに安定しやすくなります。 - 身体そのものが安定していること
落ち着きがない、すぐに姿勢が崩れるのは、精神的な問題ではなく、体幹や感覚処理といった「身体」の問題である可能性が高いです。
この「身体の安定」こそが、すべての土台となります。 - 感覚の過敏さや不快さがコントロールされていること
光や音、触覚などへの過敏さが強いと、支援に集中できる状態ではなくなってしまいます。 - 予測可能なスケジュールが提示されていること
何が起こるかが事前に分かっていることで、不安が軽減されます。 - 「できた」という経験が積み重なっていること
たとえ小さなことでも、達成感や成功体験を重ねることで、「やってみよう」という意欲が育ちます。
これらは、どれも“家庭の中”で日々意識して積み重ねていくことができるものばかりです。
特別なスキルや資格がなくても、親としての関わり方次第で整えていける「土台」なんです。
そして、この土台が整い始めると、少しずつ子どもの表情や行動にも変化が見えてきます。
それは突然大きく変わるのではなく、ほんのわずかな「前より落ち着いているかも」「嫌がらずに座れた」など、小さな変化として現れます。
ですが、その小さな変化こそが、「受ける体が育ってきている」証なんです。
この視点を持って日々の関わりを見直すだけでも、親の気持ちがずいぶんと楽になります。
「できていないこと」にばかり目を向けるのではなく、「できる準備を整える」ことに目を向ける──
それが、子どもにとっても親にとっても、優しい療育のスタートラインだと私は思っています。
次からは、「この土台があると、なぜどんな療育でも効果が出やすくなるのか?」をさらに掘り下げていきます。
「土台」が整えば、どんな療育法でも伸びる理由
療育というと、「どの手法を選ぶか」が大切だと考えがちです。
ABA(応用行動分析)やTEACCH、感覚統合、言語療法など、さまざまなアプローチが存在し、それぞれに実績と効果があります。
けれども、私が娘の育児と向き合うなかで実感してきたのは、“手法そのものよりも、子ども自身の状態が結果を大きく左右する”という現実でした。
それはたとえるなら、「土が痩せている畑にいくら良い種をまいても、芽が出にくい」というようなものです。
逆に、土壌がふかふかで栄養たっぷりの場所なら、どんな種であっても、それなりに芽を出すことができるんです。
療育もまったく同じ。
その子にとって「療育を受け入れられる心と身体の状態」が整っていれば、どんな手法でも一定の効果が出やすくなります。
逆に、いくら理論的に優れていても、本人の不安や混乱が強い状態では、せっかくの支援も届きません。
この「土台が整っている状態」というのは、子どもが療育の場において、
- 安心してそこにいられること
- 挑戦することに前向きになれること
- 少しずつでも成功体験を積み重ねられること
を意味します。
私の娘も、以前は療育の場に行くだけで疲れ果ててしまい、帰宅後は癇癪がひどくなっていました。
しかし、生活のリズムを整え、無理のない範囲で家庭でもできる支援を取り入れ、支援者と「無理に成果を求めない」方向で関わりを見直してから、少しずつ変化が見られるようになっていきました。
この変化を見て、「ああ、この子は“やっと受け取れる状態になってきたんだ”」と感じたんです。
また、これは私自身の実感だけでなく、支援者の方々からも同様の話を聞きました。
「家庭での安定が整っている子は、支援中の吸収力が全然違う」
「どの手法が合うかよりも、“まず落ち着いて参加できるかどうか”の方が重要」
これはまさに、療育における“相性以前の準備”とも言える視点です。
もちろん、特性や発達段階によって合う手法・合わない手法は存在します。
ですが、その前に「何をやるか」ではなく、「どう受け取れるか」という視点を持つことが、療育の効果を高めるための大きな鍵になります。
そして、ここが保護者の方の力で最も影響を与えられる部分でもあるんです。
決して難しいことをする必要はありません。
お子さんが安心して日々を過ごせるような環境を少しずつ整えていくこと。
それだけでも、療育の場での受け止め方が大きく変わり、支援の効果がじわじわと現れていくはずです。
次からは、実際に私の娘がどのように変化していったか──その過程をありのままにお伝えします。
机上の理論ではない、リアルな体験を通して、“土台づくり”の力を感じていただければと思います。
我が家の娘が示してくれた“変化の兆し”
私の娘は、重度の知的障害を伴う自閉症です。
発語はなく、感覚の過敏さも強く、特に新しい場所や人に対して強い不安を示す傾向がありました。
療育に通い始めたのは3歳ごろでしたが、当初はほとんどの時間を泣いて過ごしていました。
支援者の方々はとても丁寧に関わってくださっていました。
でも私の中には、
「この子には合っていないのではないか」
「そもそも療育自体が早すぎたのかもしれない」
という、不安と迷いもあったんです。
「早期療育が鍵」
「ABAが効果的」
溢れる情報の中で、専門家の言う通りに実践しても、娘の反応は芳しくなく、親子共に疲弊していくばかり……。
そんな日々で芽生えたのは、ある「違和感」でした。
「もしかしたら問題は、娘の障害の重さだけではないのかもしれない」
「専門家や情報に頼りきるあまり、“我が子を一番理解しているはずの親”である私自身が、ある種の思考停止に陥っていたのではないか」
と。
この「違和感」こそが、我が家の大きな転機となりました。
それからは、「有名なメソッドを試す」ことから、「“我が子の専門家”は親である自分自身だ」 という覚悟を持って。
「この子自身の土台を整える」ことに意識を切り替えました。
具体的には、先ほど詳しくお伝えした、あらゆる学びの基盤となる「体」と「心」の安定 です。
特に、専門家から「まず、しっかり歩けるようになりましょう」と何度も言われていた 「歩くこと」 を中心とした運動。
そして「食事」や「睡眠」といった基本的な生活リズムの安定に、徹底的に取り組みました。
すぐに劇的な変化があったわけではありません。
しかし、数ヶ月、一年と続けるうちに。
娘の体幹は明らかにしっかりし、ふらつきが減り、背筋が伸びて、しっかりと地面を踏みしめて歩けるようになったんです 。
すると、どうでしょう。
日常生活での落ち着きが格段に増し、以前は数秒ももたなかった椅子にも、少しずつ座っていられる時間が長くなりました。
指示への反応も明らかによくなり 、理由の分からなかった癇癪も減っていきました 。
この変化のきっかけは、「何かすごい支援方法(メソッド)に出会ったから」ではありません。
あくまでも、「受ける体(土台)を整えること」にフォーカスし直したからこそ、娘自身が変わる準備をしていけたのだと確信しています。
こうした体験から私は、保護者として「支援の効果を高めるために、家庭でできることはたくさんある」と確信するようになりました。
そしてそれは、特別な資格や専門知識がなくても、誰にでも始められることなんです。
焦らず取り組むために知っておいてほしいこと
お子さんに関する心配事、特に発達や行動の遅れに関する不安は、親として非常に大きなストレスになります。
「なぜ他の子はできているのに……」
「今この時期を逃したら、もう取り返せないのでは?」
「もっと早く何かしておけば……」
そんな風に、自分を責めたり、将来を悲観してしまったりする瞬間があるのではないでしょうか。
私自身、娘の育児の中で何度もこうした気持ちに押しつぶされそうになりました。
特にSNSやブログなどで、
「療育で〇ヶ月で発語が!」
「自宅支援で驚くべき変化!」
といった成功例を目にすると。
自分の子どもと比べてしまい、心が大きく揺さぶられることもありました。
ですが、今でははっきりと言えることがあります。
子どもの発達には“その子自身のペース”があり、比較や焦りは何の助けにもならないということです。
もちろん、早期の支援や関わりが大切であることは間違いありません。
でもそれは、「今すぐに結果を出さなければならない」という意味ではありません。
むしろ、「急がないといけない」という焦りが、親子双方にとって負担になり、必要な安定を壊してしまうことすらあるんです。
私が娘の「土台づくり」に意識を向けるようになってから一番良かったことは、“親としての心の安定”が生まれたことです。
「今はできていない。でも、整えていけば、この子は少しずつ伸びていく」
「今日は無理でも、明日またやってみよう」
そう思えるようになったことで、娘にも無理な期待をかけすぎず、穏やかな関係が築けるようになりました。
支援の現場でも、「親の安心」が子どもに与える影響は大きいと言われています。
それは、子どもは常に“親の表情”を見ているからです。
親が焦りや不安でいっぱいだと、子どももそれを敏感に感じ取り、「自分はダメなんだ」「何かおかしいのかな」と受け止めてしまうことがあります。
だからこそ、親自身が「焦らなくていい」と思える視点を持つことが、実は療育の第一歩でもあるんです。
土台づくりも、決して一朝一夕で完了するものではありません。
3日で変わるわけでも、1ヶ月で劇的に成長するわけでもありません。
ですが、日々の積み重ねの中で「変化の兆し」が少しずつ現れてくるものです。
そしてそれは、「親が子どものペースを信じて待つ」ことによって可能になる変化だと、私は感じています。
これまでお伝えしてきた内容は、どれも「すぐに成果が見えること」ではありません。
ですが、「ゆっくりでも確実に前に進んでいける道」を示すものです。
一緒に暮らし、一緒に悩み、一緒に育っていくなかで、「この子はちゃんと伸びていける」と信じる気持ちを、何より大切にしてほしいと思います。
次からは、「では実際に何から始めればいいのか?」について、具体的な一歩をご紹介します。
土台づくりに取り組みたいけれど、何からやればいいのか分からない──そんな方に向けた内容です。
じゃあ実際に何から始めればいいの?
ここまで「療育を受ける体づくり=土台の重要性」についてお話ししてきました。
でも、いざ実際に取り組もうとすると、「結局何をすればいいの?」と戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。
大丈夫です。
特別な準備や難しいステップは必要ありません。
まずは、「今日からできること」に目を向けてみましょう。
私が「土台づくり」として一番はじめに意識し、そして7年間で最も効果を実感したのは、「1日の流れを整えること」。
特に、
- 質の高い「睡眠・食事」のリズム
- 日中の「運動(特に“歩行”)」の確保
この2つでした。
療育の成果が出にくいと感じていた当時。
娘は体幹が弱く、多動傾向が強く、椅子に数秒と座っていられませんでした。
当然、机上課題なんてまともにできる状態ではありません。
当時の私は「なぜ集中できないんだ」と娘の「心」の問題として捉えそうになりましたが、それはまったくの見当違いでした。
問題の根源は、まず「体」にあったんです。
そこでまず、「この子の1日が“見通しのあるもの”になるように」と、食事や睡眠の時間をできるだけ安定させました。
そして何より、ほぼ毎日のように、時間を見つけては娘と手をつなぎ、歩き続けました。
「歩くこと」と療育に何の関係があるのか?
最初は半信半疑でした。
しかし、この「土台づくり」を続けた結果、娘の体は安定し、落ち着きが増し、椅子にも座れるようになったんです。
「落ち着きがない」
「指示が聞けない」
「勉強が進まない」
その根本原因は、実は「心の持ちよう」ではなく、「体の不安定さ」や「生活リズムの乱れ」にあるのかもしれません。
もし、あなたが療育の効果をなかなか感じられないと悩んでいるなら。
まず、この「土台」を見直すことが、思わぬ突破口になる可能性は非常に高いんです。
大切なのは、“特別なこと”をするのではなく、“日常の中でできること”を丁寧に積み重ねていくことです。
これこそが、療育を受けるための「土台」を育てる最短ルートだと私は実感しています。
ただし、
「歩くのを嫌がる子には、どうすればいいの?」
「そもそも、家から出たがらないんだけど……」
「生活リズムの具体的な整え方は?」
と感じることもあるかもしれません。
そうした方に向けて、以下のnoteで、家庭で取り組める土台づくりの実践方法を、より詳細に紹介しています。
おわりに:あなたと子どもに、確かな希望を届けたい
ここまで、長文を最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。
この記事を通じてお伝えしたかったこと──
それは、「療育の成果が出ない」のは、決してあなたの努力が足りないからではないということ。
そして、「何かができるようになる前に、まず整えるべきものがある」という視点です。
子どもが成長するためには、安心して関われる環境が必要です。
その環境をつくるために、支援者の力ももちろん大切です。
しかし、家庭という“子どもが最も長く過ごす場所”での関わり方こそが、成長の土台を支える最大の鍵になります。
「でも、家庭でできることって限られているし……」
「自分には専門知識もないし、何をしていいか分からない……」
そう感じる方も多いと思います。
でも、私は声を大にしてお伝えしたいんです。
“できること”は必ずあります。
しかも、それは今すぐ、今日からでも始められることばかりです。
たとえば、子どもと向き合うときに「焦らないでいいよ」と心の中で自分に言い聞かせること。
たとえば、今日あった“ちょっとしたできごと”を「できたね」と言葉にしてあげること。
たとえば、1日の流れを少し整えて、安心できる時間を1分でも増やしてあげること。
こうした積み重ねは、目には見えにくいけれど、確実に子どもの中に根を張っていきます。
そしてその根が、やがて大きな成長を支える幹となっていきます。
私自身、療育に通いながらも成果が見えず、何度も迷い、立ち止まり、落ち込んできました。
でも「土台を整える」という視点を持ってからは、少しずつ娘の変化を感じられるようになり、何より私自身が子育てに対して前向きになれました。
この記事が、かつての私のように悩んでいる誰かにとって、小さな希望の種になってくれたら。
そして、あなたとあなたのお子さんにとって、これからの毎日が少しでも穏やかで、希望に満ちたものになっていくことを、心から願っています。
なお、ここでお伝えできたのは、あくまでも「考え方」と「最初の一歩」にすぎません。
この「土台」を具体的にどう構築していくのか?
その「実践方法(How)」のすべてを、私の7年間の試行錯誤の記録として、67,000字のnoteに詰め込みました。
もしあなたが、
「うちの子に合った『土台』の作り方を具体的に知りたい」
「一般書には載っていない、重い子や特性の強い子の『癇癪・こだわり』への現実的な予防策が知りたい」
「『我が子の専門家』になるための実践的な方法を学びたい」
そう思われるなら、ぜひ下記のリンクから『療育の常識を疑え』をご覧ください。
今回の記事と合わせて読むだけでも、あなたの療育観は大きく変わるはずです。