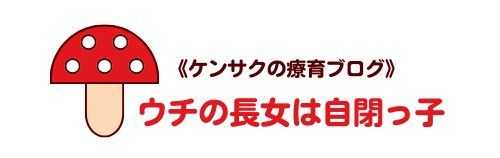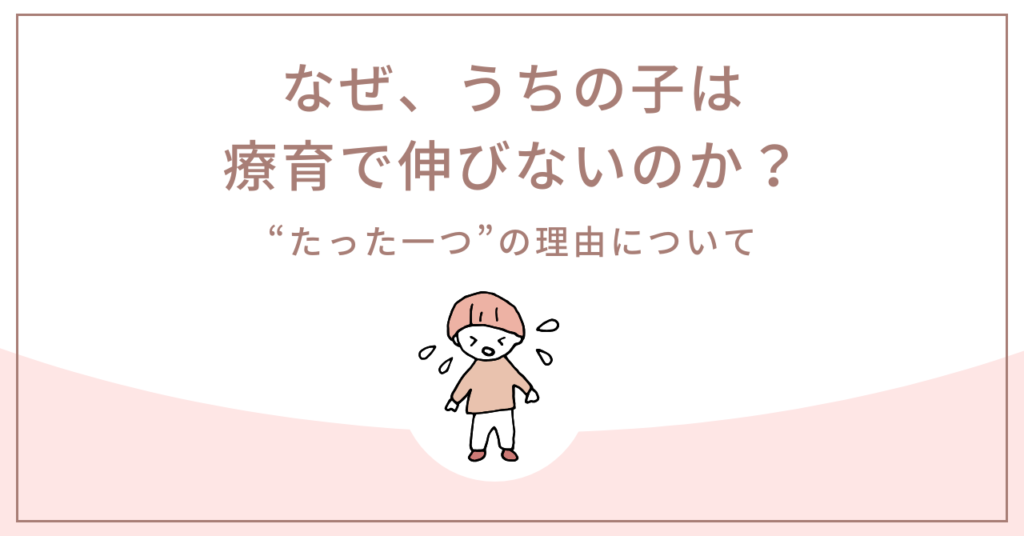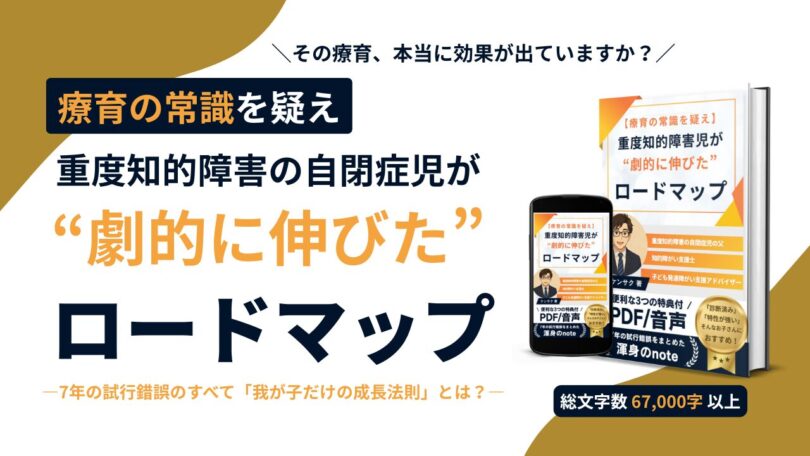「やめてって言ってるでしょ!」
「どうして、何度言ってもやめてくれないの……」
「やめて」という、たった一言が伝わらない。
その繰り返しに、「育て方が悪いのかな……」と自分を責めてしまう。
そのお気持ち、痛いほどわかります。
何を隠そう、私の娘も発達障害で、以前はやめてと言ってもやめない行動の連続でした。
でも、声かけなどを工夫することで、少しずつですが確かに効果が見えてきたんです。
もしあなたが今、かつての私のように疲れ果て、自分を責めているのなら、どうか聞いてください。
これだけは、絶対に覚えておいてほしいんです。
その子の行動は、あなたのせいでは、決してありません。
発達障害の子の「やめてと言ってもやめない」行動は、わがままや反抗ではなく、生まれ持った脳の特性が関係している可能性が高いです。
このブログ記事では、私たち夫婦の実体験をもとに、なぜ「やめて」が伝わらないのか、その根本的な理由を脳の仕組みから解き明かします。
そして、具体的な対策を余すことなくお伝えします。
これは単なるテクニック集ではありません。
「今この瞬間」を乗り切る対策から、未来への希望、そしてあなた自身と家族を守るための、具体的な戦略です。

- 「やめてと言ってもやめない」本当の理由
- 「やめてと言ってもやめない」ときの具体策
- うまくいかないときの次の打ち手
※本記事にはプロモーションが含まれます。
目次
「やめてと言ってもやめない」本当の理由→発達障害の特性が関係?
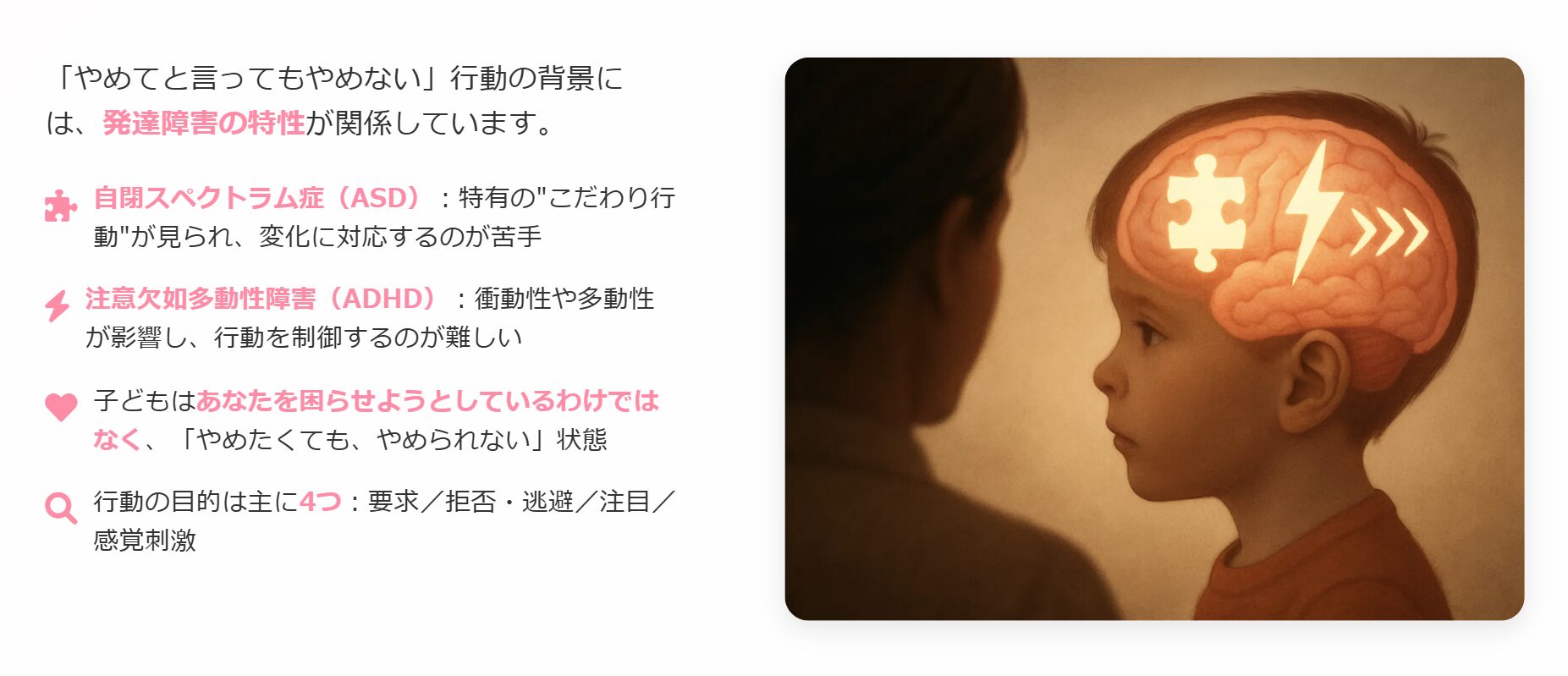
結論から言うと。
「やめてと言ってもやめない」
その背景には、発達障害の特性が関係している場合があります。
たとえば、自閉スペクトラム症(ASD)では特有の“こだわり行動”が見られ、注意欠如多動性障害(ADHD)では“衝動性や多動性”が影響していることがあります。[1][2]
適切な対応としては、相手に分かりやすく説明したり、具体的な指示を示したり、環境を工夫すること。
さらに、必要に応じて専門機関へ相談することが大切です。[3]
問題行動を起こす理由
子どもが問題行動を起こすとき、その裏には必ず目的があります。
行動分析学の枠組みでは大きく4つ(要求/拒否・逃避/注目/感覚刺激)に分類されることが一般的です。[5][8]
- 要求(〇〇が欲しい、〇〇したい)
- 拒否・逃避(〇〇はやりたくない)
- 注目(親や周りの人にかまってほしい)
- 感覚刺激(その行動自体が心地よい)
特に発達障害の子は、これらの気持ちを言葉でうまく表現するのが苦手なため、行動で示そうとします。
それが、親から見ると「やめてと言ってもやめない」状況につながってしまうんです。[9]
それは「意志」ではなく「脳の特性」の問題です
一番大切なことからお話しします。
子どもは、あなたを困らせようとして「やめない」わけではないんです。
むしろ、「やめたくても、やめられない」。
子ども自身も、自分の衝動に困っていることがほとんどです。[4]
① 不安を減らし、安心したい脳(自閉スペクトラム症・ASD傾向)
このタイプの子にとって、世界は変化だらけで予測不能な場所。
だからこそ「いつもと同じ」に強くこだわります。
特定の行動を繰り返すのは、それが心を落ち着かせる儀式だからです。[1]
「やめて」の一言は、その安心を突然奪うパニックボタン。
だから、かえって行動に固執してしまうんです。[9]
② 強い刺激と注目が欲しい脳(注意欠如・多動症・ADHD傾向)
こちらのタイプの子の脳は、常に新しい刺激や強い反応を求めています。
そして、ここが重要なのですが、叱られることさえも、彼らにとっては強力な「注目」というご褒美になります。
無視されるくらいなら、怒られた方がマシ。
だから、叱れば叱るほど、注目を求めて行動がエスカレートしてしまうんです。[8]
子どもの「内なる世界」を覗いてみませんか?
私たちはつい、自分の物差しで子どもの行動を判断してしまいます。
でも、もし彼らが体験している世界が、私たちとまったく違ったらどうでしょう?
たとえば、スーパーの照明が絶えずチカチカするストロボライトに見え、冷蔵ケースのモーター音が頭に響くサイレンのように聞こえていたら?
周りの人のざわめきが、何百ものラジオを同時に聞かされているように感じていたら?
そのカオスの中で、唯一安心できるのは、自分でコントロールできる行動(同じ場所をぐるぐる回る、特定のおもちゃを触り続けるなど)だけかもしれません。[9]

その子にとって「やめられない」行動は、嵐の中で必死にしがみついている浮き輪のようなものなんです。
そして、子ども自身も、そんな自分の感覚や衝動に振り回され、「どうして僕はうまくできないんだろう」と混乱し、傷ついているかもしれないんです。

大切なのは「診断名」より「行動の目的」を見抜くこと
この「内なる世界」を少し想像するだけで、子どもの行動が違って見えてきませんか?
大切なのは、「うちの子はどっちだろう?」と診断名に悩むことよりも、「今、この行動で何を伝えようとしているんだろう?」と、その目的を探る視点を持つことです。[5]
【お守りツール①】わが子の「やめない理由」分析チェックシート
お子さんの行動に当てはまる項目にチェックを入れて、一番多いものが、今の行動の主な目的かもしれません。
要求が目的?
- [ ]何かを手に入れようとしているとき(お菓子、おもちゃ等)にその行動は起きるか?
- [ ]「〇〇したらあげる」という交換条件を出すと、行動は収まるか?
拒否・逃避が目的?
- [ ]嫌なこと(片付け、着替え、宿題等)をさせようとすると、その行動は始まるか?
- [ ]その行動をすることで、嫌なことを先延ばしにできているか?
注目が目的?
- [ ]親が他のことに集中しているとき(スマホ、家事、兄弟の世話等)に、その行動は起きやすいか?
- [ ]行動を叱ったり反応したりすると、ニヤッとしたり、さらにエスカレートしたりするか?
- [ ]逆に、完全に無視すると、しばらくして諦めることがあるか?
感覚刺激が目的?
- [ ]人や状況に関係なく、一人でいる時でもその行動は起きるか?
- [ ]行動しているとき、うっとりしていたり、楽しそうに見えるか?
- [ ]特定の音、光、感触などを、自ら求めているように見えるか?
どうする? わが家で効果絶大だった4つの具体策

原因の仮説が立ったら、次は具体的なアクションです。
わが家の長女にも効果があった、子どもの脳に届く関わり方の設計図を、実体験と共にご紹介します。
対策1:肯定的な言葉に変換する【NG例:注意や命令ばかりする】
私たちはつい、「〇〇しないで!」「ダメ!」という否定的な言葉を使いがちです。
でも、それでは子どもは「また怒られた……」と心を閉ざすか、反発するだけ。
「~しないで」を「~しようね」に言い換えることを意識してみてください。[3]
わが家の娘の場合、以前は口に物を入れたり、虫刺されをひたすら搔きむしる癖がありました。
そのとき、「食べない!」「掻かない!」と叫ぶ代わりに、「お口から出そうね」「おてては、おひざにしようね」と声をかけ続けました。[7]

正直、最初は私たち親が慣れるのに時間がかかりました。
でも、今では自然とこの声かけができるようになり、娘もある程度すんなりと指示に従ってくれるようになったんです。
対策2:指示は「簡潔」かつ「具体的に」【NG例:漠然とした指示をする】
「ちゃんと片づけて!」のような漠然とした指示は、特に発達障害の子には伝わりません。
「何を」「どこに」「どうするのか」が分からず、混乱して癇癪につながることもあります。[6]
片づけが苦手だった娘に、わが家ではこう伝えました。
まず、娘と目線を合わせ、「遊ぶのはおしまい。お片づけの時間だよ」と伝えます。
そして、「このおもちゃは、この赤い箱に入れようね」「このぬいぐるみは、ソファの上に戻そうか」というように、一つひとつ具体的に指示を出すんです。
タイマーや視覚スケジュールなどの視覚的な補助を併用すると、切り替えがさらにスムーズになります。[3]

対策3:親が主導権を握る【NG例:子どもの言いなりになる】
癇癪を起こされると、つい言いなりになった方が楽だと感じてしまいますよね。
でも、それを繰り返すと「抵抗すれば思い通りになる」と子どもが学習してしまいます。
大切なのは、笑顔で共感しつつも、伝えるべきことは伝えるという姿勢です。[10]
「テレビ見たいよねー、わかるよ。でも、まずはお片づけをしようか」
そう言って、少し手伝いながらでも最後までやらせる。
最初はすごく抵抗されましたが、これを繰り返すうちに、娘との間に「お約束は守る」という信頼関係ができてきました。

根気は必要ですが、後々が本当に楽になります。
対策4:状況によっては「スルー」も必要
もし、ここまでの対応をしてもふざけて聞かない場合。それは「注目」が目的かもしれません。
その場合は、あえてスルーするのが効果的です。[8]
反応せずに放っておくと、子どもは「この行動では注目されないんだ」と気づき、自然とやめることがあります。
もちろん、危険な行動や他人に迷惑をかける場合は別です。[13]
どのケースが注目目的なのか、日頃からお子さんを観察して見極める必要がありますが、これも強力なカードの一つです。

【お守りツール②】状況別・声かけ言い換えフレーズ集
| こんなとき | つい言いがちなNG声かけ | 脳に届く声かけ(言い換え例) |
|---|---|---|
| お店で走り回る | 「走らないで!」 | 「カートを押すお手伝いしてくれる?」 「ママと手をつないで歩こう」 |
| 物を投げる | 「投げちゃダメ!」 | 「ボールは投げていいよ。これはそーっと置こうね」 |
| 兄弟を叩く | 「叩かないの!」 | 「叩きたくなるくらい嫌だったんだね。でも、叩くのはダメ。言葉で『やめて』って言おう」 |
| ご飯で遊ぶ | 「遊ばないで食べなさい!」 | 「お野菜さん、お口に入れてくれるのを待ってるよ。パクってできるかな?」 |
| 切り替えられない | 「もうおしまいって言ったでしょ!」 | 「あと3回やったらおしまいにしようか」 「タイマーが鳴ったら、バイバイね」 |
【緊急マニュアル】カオスな瞬間のための3ステップ応急処置
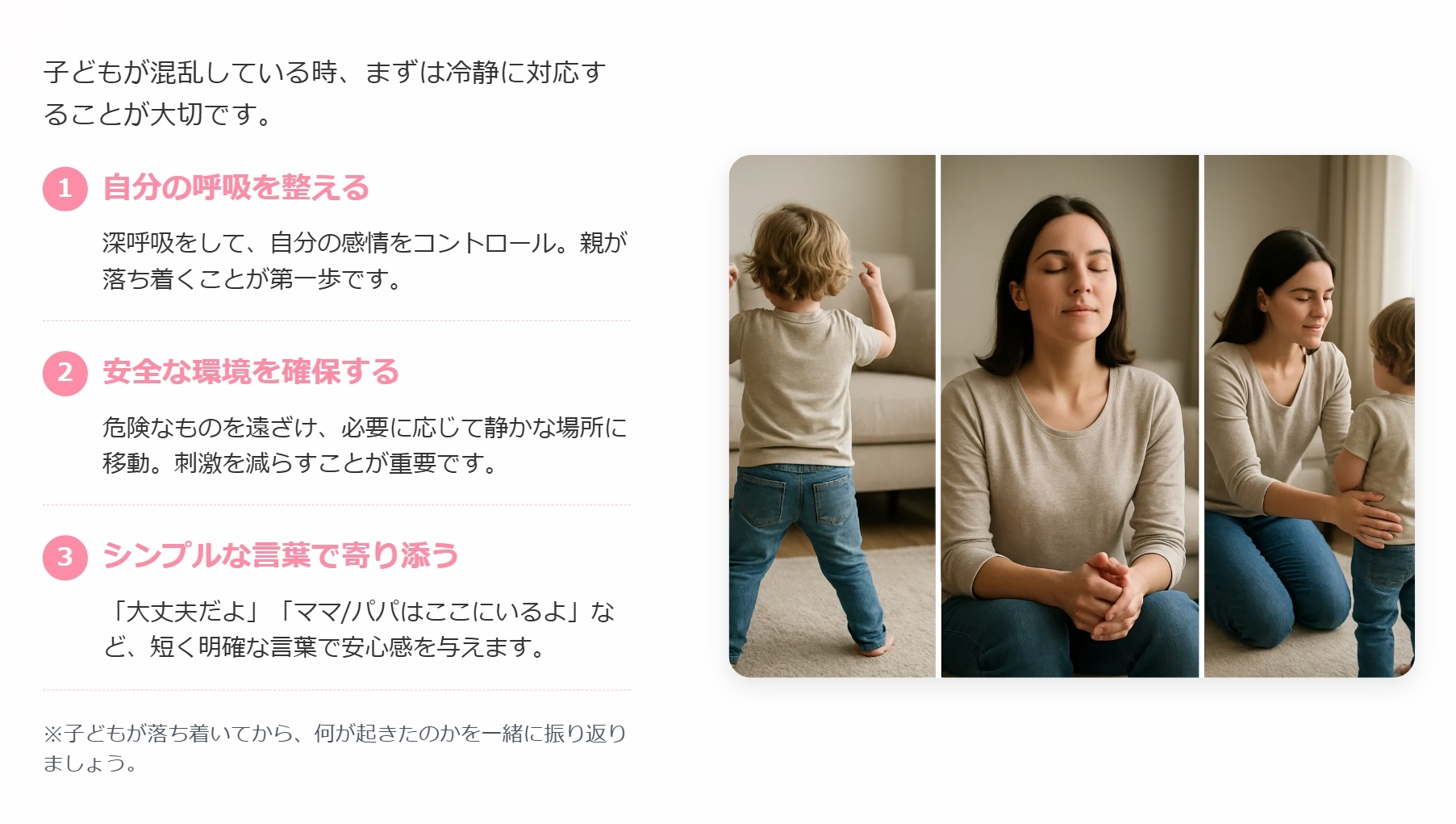
理論はわかっていても、現実は待ってくれません。
スーパーの床で子どもがひっくり返ったとき、私たちは冷静な専門家ではいられません。
以下は、そんな戦場の真っただ中で使える、応急処置マニュアルです。

前提として、まずはあなた自身とお子さんの安全を確保するようにしましょう。
ステップ1:『一時停止』して、物理的に距離をとる(約10秒)
感情的に怒鳴りそうになったら、それは脳が「脅威」を感じているサインです。
この状態では、何を言っても火に油を注ぐだけ。
- 息を吐く:まず、怒りを吐き出すように、長く息を吐きます。
- 物理的に離れる:子どもから2、3歩離れ、しゃがんでください(子どもを見下ろすのをやめる)。
- 実況中継する:心の中で「ああ、今すごくイライラしてるな」「心臓がバクバクしてる」と自分の状態を実況中継します。これだけで、感情を客観視でき、理性が少し戻ってきます。

このステップの目的は、あなたの脳を「戦闘モード」から「対話モード」に切り替えることです。
ステップ2:『共感』の言葉で、子どもの脳に接続する
子どもの脳がパニック(興奮)状態の時、正論や指示は届きません。
まず、相手の感情の波長に合わせ、安心させる必要があります。
- 見たままを言葉にする:「床にごろんしたかったんだね」「大きな声が出てるね」
- 気持ちを代弁する:「お菓子が買ってもらえなくて、すごく悲しかったんだね」「帰りたくなくて、嫌な気持ちなんだね」

ここでは一切、しつけも指示もしません。
「あなたの気持ち、ちゃんとわかってるよ」というメッセージを送ることに徹してください。
子どもは、理解されたと感じることで、初めて聞く耳を持つことができます。[10]
ステップ3:『2つの選択肢』を与え、行動を導く
子どもの気持ちが少し落ち着いたら、最後に具体的な行動を導きます。
ここでのコツは、「やめなさい」という命令ではなく、「どちらかを選ばせる」形にすることです。[10]
- 具体的で、簡単な選択肢を提示する:
- 「カートに乗って行く? それとも、ママと手をつないで歩いて行く?」
- 「このお菓子と、あっちのお菓子、どっちか一つだけ選ぼうか?」
- 「あと1分だけ遊ぶ? それとも、お家に帰ってからビデオを見る?」

自分で選ぶという小さな主導権を与えることで、子どもはコントロールされているという感覚ではなく、自分で決めたという納得感を持つことができます。[7]
試してもうまくいかないとき|次の打ち手と専門家への相談タイミング
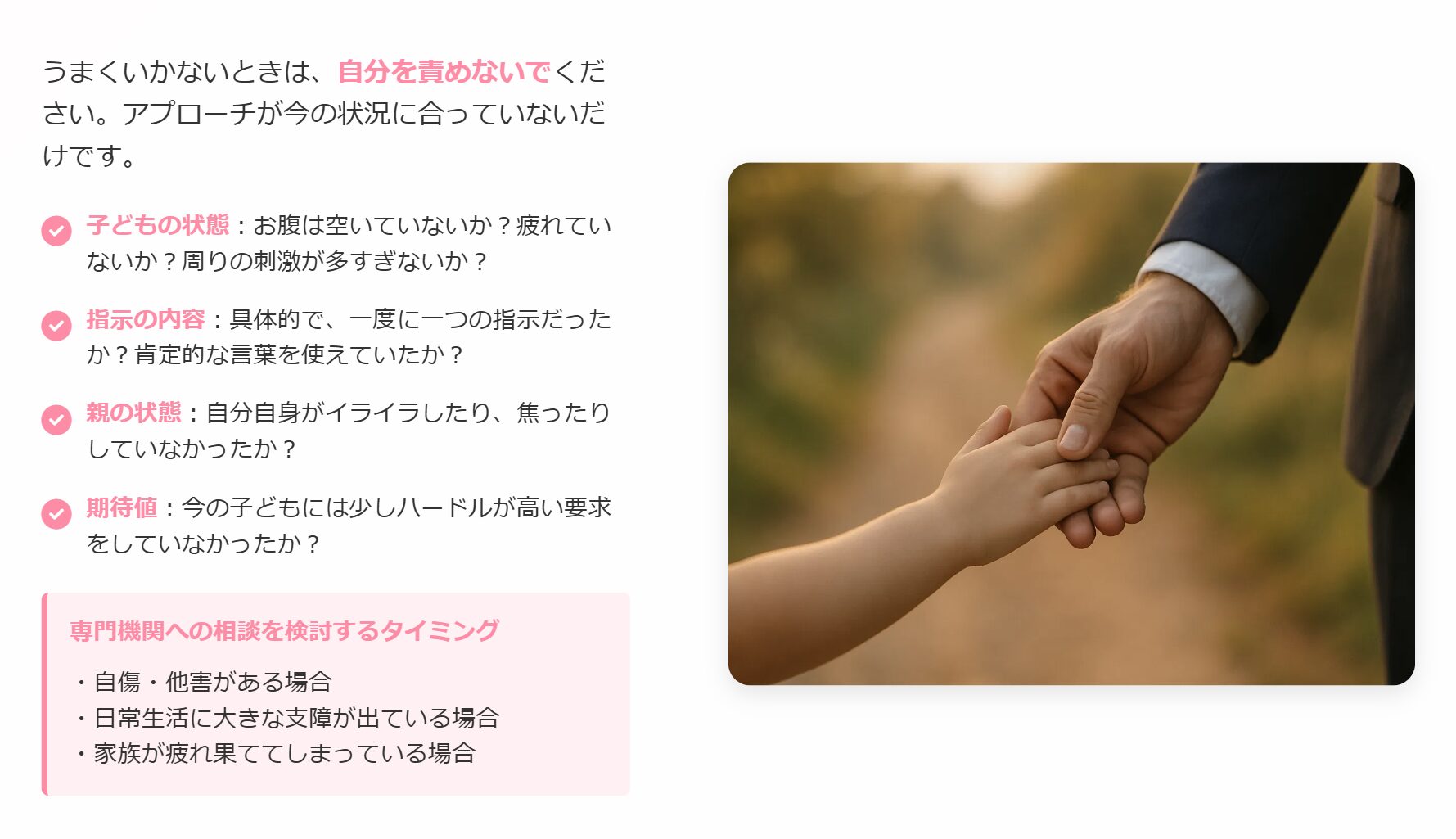
この記事に書かれていることを試しても、うまくいかないことは必ずあります。
その時、決して「やっぱり私のやり方が悪いんだ」と自分を責めないでください。
子どもの特性やその日のコンディションは千差万別。
うまくいかないのは、あなたではなく、アプローチが今の状況に合っていないだけです。
方向性の見直し
もし行き詰まったら、一度立ち止まって以下の点を確認してみてください。
- 子どもの状態は?:お腹は空いていないか? 疲れていないか? 周りの刺激が多すぎないか?(そもそも指示を受け入れられる状態か)[9]
- 指示の内容は?:本当に具体的で、一度に一つの指示だったか? 肯定的な言葉を使えていたか?[6]
- 親の状態は?:自分自身がイライラしたり、焦ったりしていなかったか?(親の不安は子どもに伝染します)
- 期待値は?:もしかして、今のこの子には少しハードルが高い要求をしていなかったか?

うまくいかないときは、多くの場合、これらのどこかに原因が隠れています。
アプローチを少し変えるだけで、うまくいくことも少なくありません。
専門機関への相談を検討するタイミング
以下の状況が数週間以上続く場合は、一人で抱え込まず、専門家を頼ることをおすすめします。
それは、あなたとご家族を守るための、前向きで賢明な判断です。[13]
- 自傷・他害がある場合:頭を壁に打ち付ける、他の子を頻繁に叩いてしまうなど、本人や周りの安全が脅かされるとき。
- 日常生活に大きな支障が出ている場合:園や学校に行けない、食事や睡眠がとれないなど、生活の基盤が崩れているとき。
- 家族が疲れ果ててしまっている場合:親が精神的に追い詰められていたり、きょうだいへの影響が大きかったりして、家庭が機能不全に陥りそうなとき。
相談先
あなたと家族を守るための、周りとの協力体制づくり
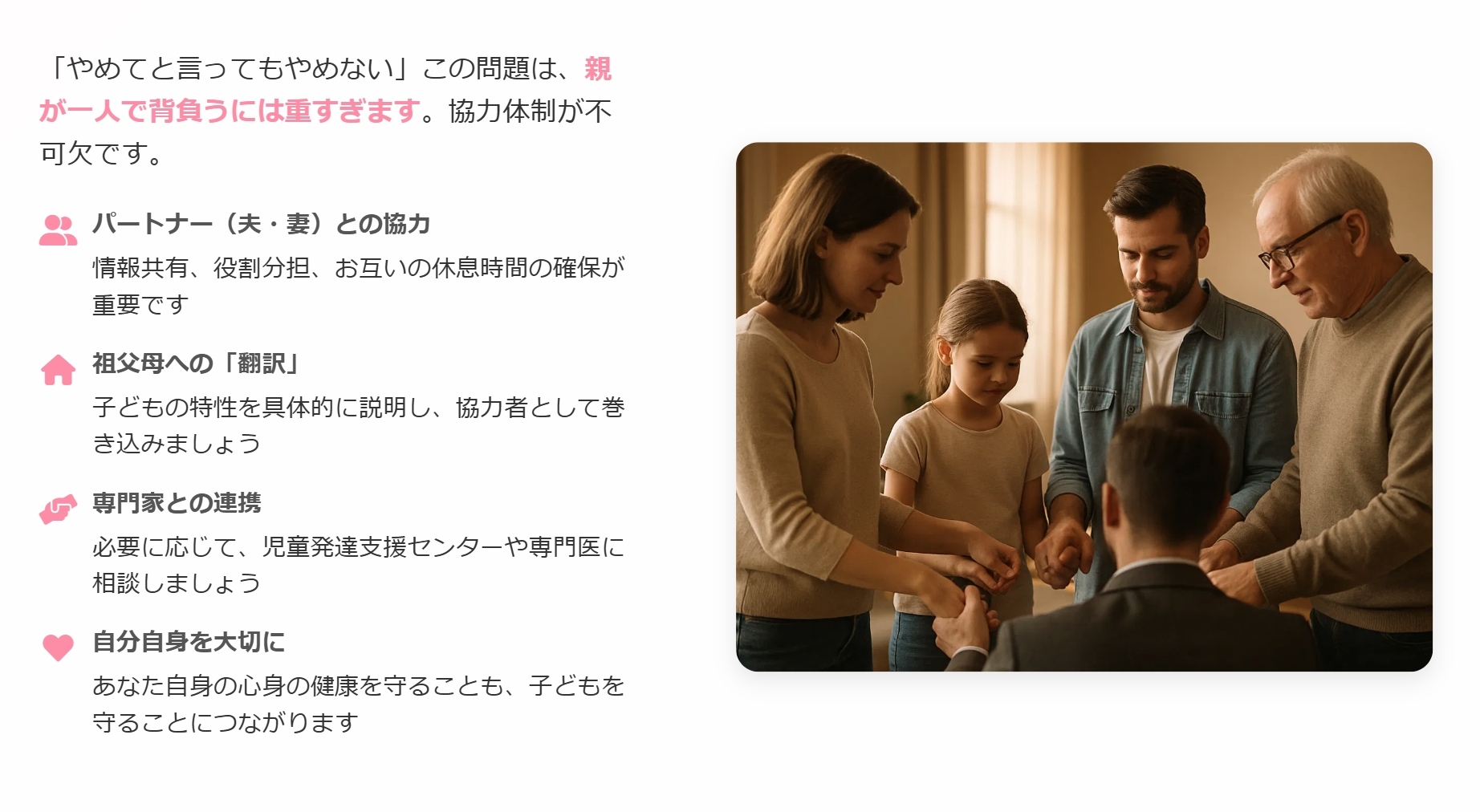
「やめてと言ってもやめない」この問題は、親が一人で背負うにはあまりにも重すぎます。
あなたを中心とした、家族や周りの人との協力体制をつくることが、状況を改善する上で不可欠です。
パートナー(夫・妻)へ:大切な協力者になるために
多くの家庭で、育児の負担はどちらかに偏りがちです。
パートナーは、もう一人の親であると同時に、一番の理解者であり、大切な協力者です。
- 情報を共有する:この記事の内容や、子どもの特性について冷静に話し合う時間を作りましょう。
- 役割を分担する:母親が子どもと向き合う役なら、父親は祖父母との調整役や、支援制度を調べる情報収集役になるなど、それぞれの得意分野で役割を分担しましょう。[12]
- 休息時間を確保する:「今日は僕がみるから、少し休んで」とお互いに声をかけ、意識的に一人になれる時間を作ることが、長い目で見て家族全員のためになります。
祖父母へ:「翻訳」で世代間の壁を越える
「私たちの頃は……」「甘やかしすぎよ」
善意からくる言葉が、深く胸に突き刺さることは少なくありません。
ここで大切なのは、彼らを責めるのではなく、子どもの特性を「翻訳」してあげることです。
「わがままを言ってるんじゃなくて、脳の仕組みで、急に気持ちを切り替えるのがすごく苦手なんです。だから、出かける5分前に『そろそろだよ』って一度だけ声をかけてもらえると、すごく助かります」[3]
このように、具体的な事実とお願いしたい具体的な行動をセットで伝えてみてください。
感情的な対立ではなく、孫を助けるための協力者として巻き込むんです。
その関わりが未来を創る:今日の「大変」が「生きる力」に変わるまで

最後に、未来の話をさせてください。
「やめてと言ってもやめない」
子どもとの毎日は、先が見えず、ただただ消耗するだけのように感じるかもしれません。
しかし、あなたが今、悩みながらも実践しようとしている関わりは、子どもの未来を創る、何より大切な土台作りなんです。[10]
- あなたが子どもの気持ちを代弁し続けることで、子どもは自分の感情を理解し、言葉で伝えるスキルを学びます。
- あなたが具体的な選択肢を与え続けることで、子どもはパニックにならずに自分で考えて決める力を身につけます。[7]
- あなたが肯定的な言葉で関わることで、子どもは「自分はダメじゃないんだ」という自己肯定感を育みます。[3]

今日の「大変」は、5年後、10年後に子どもが社会で生きていくための「生きる力」に、間違いなくつながっています。
あなたはただ問題行動を減らしているのではなく、子どもの未来そのものを育んでいるんです。

まとめ:できたことを、たくさん褒めてあげよう
「やめてと言ってもやめない」子育ては、本当に大変です。
でも、「どのタイミングで、どう指示をするか」というポイントを押さえるだけで、景色はまったく違うものになります。[6]
そして、忘れてはならない一番大切なこと。
それは、指示を聞けたときに、たくさん褒めてあげることです。[10]
できたことを褒める。
できなくても、やろうとしたその過程を褒める。
その積み重ねが、お子さんとの信頼関係を何よりも強くし、指示が通りやすい土台を作ってくれます。
わが家も、まだまだ試行錯誤の毎日です。
でも、確かな手応えを感じています。
この記事が、暗いトンネルを照らす、小さな光になれたなら、これほど嬉しいことはありません。
▼この記事で参考にした書籍です

ABA(応用行動分析)に基づいた、より具体的な声かけのテクニックがイラスト付きで分かりやすく解説されています。
今日の話からさらに一歩進みたい方は、ぜひ手に取ってみてください。
脚注・参考文献
[1] 国立精神・神経医療研究センター病院(年不記載)自閉スペクトラム症(ASD)— 疾患解説ページ。https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease06.html
[2] 文部科学省(年不記載)参考3 定義と判断基準(試案)等—ADHDの定義。https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/attach/1361233.htm
[3] 厚生労働省(年不記載)発達障害の特性(代表例)—配慮(肯定的・具体的・視覚的な伝え方等)。https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/e-learning/hattatsu/characteristic.html
[4] 国立精神・神経医療研究センター病院(2022)“ADHDタイプ”の方の対処策①—ADHDは脳機能の発達の偏り。https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/rinshoshinri/rinshoshinri_blog20220228-1.html
[5] 平澤紀子ほか(2024)「機能的アセスメントに基づく行動支援計画…」行動分析学研究 38(2):120-130—4つの機能(要求/逃避/注目/感覚)。https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjba/38/2/38_120/_pdf/-char/ja
[6] 国立特別支援教育総合研究所 CPEDD(年不記載)学習障害(LD)のある子どもの指導・支援—具体的・簡潔な指示と視覚的補助。https://cpedd.nise.go.jp/shido_shien/ld
[7] CDC(2024)Parent Training in Behavior Management for ADHD—保護者訓練(行動療法)とスキル習得。https://www.cdc.gov/adhd/treatment/behavior-therapy.html
[8] Cooper, Heron, & Heward(2020/2021版情報)Applied Behavior Analysis, 3rd ed.—消去(計画的無視)等の基礎。https://www.pearson.com/en-ca/subject-catalog/p/applied-behavior-analysis/P200000000905/9780137477210
[9] 厚生労働省(2021)発達障害児者の感覚の問題に対する評価と支援の有用性の調査—感覚過敏等が行動に影響。https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000797323.pdf
[10] NICE(2018, 最終レビュー2025)NG87: Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management—構造化された支援・親支援。https://www.nice.org.uk/guidance/ng87
[11] こども家庭庁(年不記載)こども家庭センター—市区町村の相談・支援の包括窓口。https://www.cfa.go.jp/policies/kokasen
[12] 厚生労働省(年不記載)福祉・介護 障害児支援施策—児童発達支援センター等。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html
[13] AAP(2020)Identification, Evaluation, and Management of Children With ASD—重篤な問題行動への対応・併存症評価。https://publications.aap.org/pediatrics/article/145/1/e20193447/36917/Identification-Evaluation-and-Management-of
[14] こども家庭庁(年不記載)相談窓口—全国の相談先一覧。https://www.cfa.go.jp/children-inquiries
[15] 国立成育医療研究センター(年不記載)こころの診療科—ASD/ADHD等の診療。https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/naika/kokoro.html