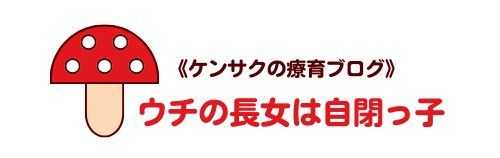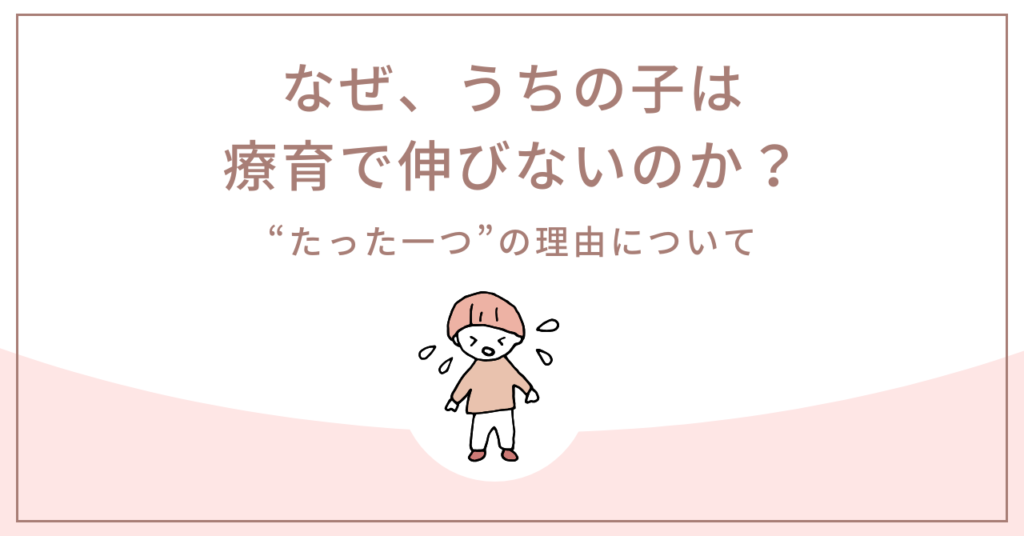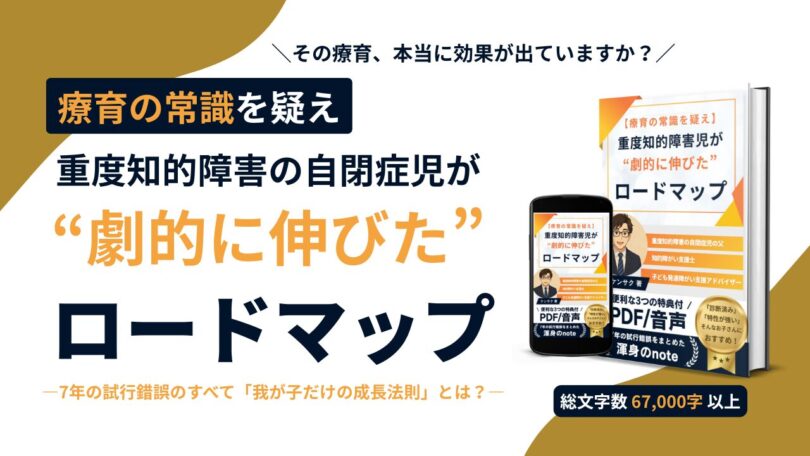「もう無理……育てられない」
障害児である我が子を育てていて、そう思ったことはありますか?
毎日の育児がしんどい、気持ちが追いつかない。
そんなふうに感じるのは、あなただけじゃありません。
誰にも言えない不安や罪悪感。
でも、それを一人で抱え込む必要はありません。
頼れる支援や選択肢はあります。
あなたが少しでも楽になる方法を、一緒に考えませんか?
- 親としての罪悪感や心理的負担を軽くする方法
- 「育てられない」と感じたときに頼れる支援制度や相談先
- 実際に「育てられない」と感じる親の体験談
このブログ記事では、同じ悩みを持つ人の本音も紹介します。
そして、あなたの気持ちが軽くなるヒントをお伝えします。

「もっと楽に子育てできないかな?」そう感じている方は、具体的な解決策や乗り越えるためのコツを紹介した以下の記事もおすすめです。
※本記事はプロモーションを含みます。
目次
「障害児を育てられない」と感じたあなたに伝えたいこと

「もう無理」
「どうしたらいいのかわからない」
そう思ったことはありませんか?
障害児の育児は、本当に本当に大変です。
それは、重度知的障害を伴う自閉症の娘を育てる、私たち夫婦にはよくわかります。
頑張っているのに辛いと感じるのは、あなたが弱いからではありません。
あなたには、様々な支援を受ける権利があります。
相談できる場所、頼れる制度を知るだけで、心が軽くなることもあります。

この先、一人で抱え込まないでください。
あなたが楽になることが、子どもの幸せにもつながります。
一人で抱え込まない具体的な方法について、見ていきましょう。

「障害児を育てられない」と感じるのは普通のこと?

「育てられない」と思うのは、あなただけではありません。
実際、多くの親がそう感じています。
障害児の育児は、心にも体にも大きな負担がかかります。
「寝る時間がない」
「自由がない」
「社会から孤立している」
そんな思いを抱えながら、毎日を必死に生きている人は多いんです。
母親は「24時間子どもにつきっきり。誰とも話せず苦しい」と訴える。
父親は「職場に理解がなく、仕事との両立ができない」と悩む。
育児のストレスで、心身を壊す人も少なくありません。
だから、「育てられない」と感じても、決して異常ではないんです。
むしろ、それだけ頑張っている証拠なんです。

親だって人間、限界があります
「育てられない」と思うのは、決して珍しいことではありません。
「毎日が辛い」
「逃げたい」
「子どもを施設に預けるべきか迷っている」
そう感じたことがある人は、決して一人ではないはずです。
無論、私たち夫婦もそう思うことは今でもあります。
社会は「親なら育てて当然」と思いがち。
でも、親だって限界が人間です、限界があります。

その気持ちを認めることが、まずは大切な一歩になります。
罪悪感を感じるのは、本気で子育てしている証拠です
「育てられない」と感じると、多くの親が罪悪感を持ちます。
「私がもっと頑張るべきだった……」
「他の人は普通に育てているのに……」
でも、罪悪感を抱くこと自体が、子どもを大切に思っている証拠です。
「親としての責任を果たせていない」なんてことはありません。
むしろ、親が無理しすぎるほうが、子どもにとってもよくないんです。
罪悪感を感じたら、一度立ち止まって考えてみましょう。
「私は無理していないかな?」と。

ネガティブな感情を否定せず、受け入れる方法
「辛い」
「もう無理」
「逃げたい」
そんなネガティブな感情が出てくるのは、自然なことです。
でも、その感情を押し殺してしまうと、心が壊れてしまう。
だからこそ、まずは自分の気持ちを受け入れることが大切です。

ネガティブな感情と向き合うための、具体的な方法を5つ紹介します。
① 自分の気持ちを言葉にする
心の中にため込まず、ノートに書き出してみる。
「今日はこんなことで辛かった」と整理するだけでも、気持ちが楽になります。
② 誰かに話す
家族や友人、療育の先生など、信頼できる人に話す。
「共感してもらえた」と感じるだけで、心は軽くなるものです。
③ 自分を責める言葉をやめる
「私はダメな親だ」「もっと頑張らないと」
そう思ったら、「私は頑張ってる」と言い換えてみてください。
④ 休む時間を作る
疲れたら休むのは当たり前。
短時間でもいいので、自分の時間を作りましょう。
⑤ 専門家に相談する
心のケアが必要だと感じたら、カウンセリングを受けるのも一つです。
専門家に話すことで、新しい視点が見えてくることもあります。
オンラインで、精神科医や臨床心理士などの専門家とマンツーマンで相談できるサービスがおすすめ。
中でも「インターマインド・パーソナルケア」は、初回カウンセリングを今なら無料で行っています。
詳しくは、以下の公式サイトをご覧ください。
\公式HPはこちら/
今なら初回カウンセリング無料!

どんな感情も、無理に消す必要はありません。
むしろ、向き合うことで、少しずつ心が軽くなるはずです。
「もう限界」と感じたときに、試してほしいこと

障害児の育児は、心も体もすり減るほど大変。
何もかも投げ出したくなる瞬間があるのは、当然のことです。
でも、そんなときに大切なのは、一人で抱え込まないこと。
限界を感じたときは、次に紹介するストレス軽減法や相談窓口の活用などを試してみてください。
しんどいときに実践できるストレス軽減法
先ほどご紹介した、ネガティブな感情と向き合うための方法と少し重複しますが、具体的には次の4つです。
①心と体を大切にする
まずは何よりも、あなたの心身の健康を第一に考えてください。
あなたが倒れてしまっては、お子さんを支えることも難しくなってしまいます。
- 休息と睡眠を確保する【可能な限り昼寝や休憩を】
少しでも時間を見つけて横になりましょう。
10分程度の短い休憩でも、効果はあります。 - 五感を満たす
美味しいものを食べる、よい好きな香りを楽しむ、心が安らぐ音楽を聴く。
穏やかな時間を過ごして、少しでもリラックスしましょう。
②周りの人に頼る・助けを求める
一人で抱え込まず、積極的に周りの人に頼りましょう。
あなたは一人ではありません。
- 家族やパートナーと協力する
家事や育児を分担し、お互いをサポートし合いましょう。辛い気持ちや悩みを打ち明け、共感してもらうだけでも心が軽くなることがあります。 - 友人や知人に相談する
信頼できる友人や知人に、話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることがあります。
一緒に食事に行ったり、趣味を楽しんだりする時間を作ることで、気分転換になります。 - 支援サービスを活用する
障害児対応のシッターなど、一時的に子どもを預かってもらえるサービスを利用しましょう。
児童発達支援(療育)や放課後等デイサービスなども、積極的に活用しましょう。 - オンラインコミュニティに参加する
SNSやインターネット上には、障害児育児に関するオンラインコミュニティが多数存在します。
同じ悩みを持つ親御さんと交流することで、孤独感を解消し、情報交換や励まし合いができます。
③考え方や行動を工夫する
ストレスを感じやすい考え方の癖に気づき、より楽な考え方や行動を意識してみましょう。
- 完璧主義を手放す
すべてを完璧にこなそうとせず、多少のことは「まあ、いっか」と許せるようにしましょう。
常に全力疾走する必要もありません。時には力を抜いて、休憩することも大切です。 - よい面に目を向ける
子供の小さな成長や変化に目を向け、喜びを共有しましょう。
意識してポジティブな言葉を使うようにするのも大事です。 - 境界線を引く
自分の時間と子どものための時間を明確に区別し、自分の時間を大切にしましょう。
良い意味で子どもへの期待値を下げて、期待外れで落ち込むことも減らしましょう。
④専門家のサポートを求める
どうしても辛いときは、一人で抱え込まず、専門家のサポートを求めてください。
- カウンセリング
カウンセラーに話を聞いてもらうことで気持ちが整理され、新たな視点が見つかることもあります。
上述した「インターマインド・パーソナルケア」のように、精神科医や臨床心理士などの専門家に相談できるサービスがおすすめです。 - 医師の診察
当たり前のことですが、心身の不調を感じたら、早めに医師の診察を受けましょう。

ストレスはゼロにできないけれど、軽くすることはできます。
少しずつでも、自分を大切にする時間を持ちましょう。
「育てられない」と感じたときに頼れる相談窓口
育児の悩みは、一人で抱えるものではありません。
困ったときは、頼れる窓口に相談しましょう。
児童相談所(児相)
育てられないと感じたら、まず相談すべき場所です。
子どもの福祉について、専門の相談員が話を聞いてくれます。
発達障害者支援センター
発達に不安がある子どものサポートをしてくれます。
育て方のアドバイスはもちろん、支援制度の案内も受けられます。
地域の子育て支援センター
親同士の交流や、育児の相談ができる場所です。
「同じ悩みを持つ人がいる」と感じられるだけで安心できます。
精神保健福祉センター
心の負担が大きくなりすぎたときに頼れる場所です。
カウンセリングや医療機関の紹介も行っています。

どの窓口も、「相談するだけ」でも大丈夫です。
悩みを言葉にするだけで、気持ちは少し軽くなります。
サポートの種類を知っておきましょう
障害児の育児には、行政や地域のサポートがあります。
でも、「どんな支援があるのかわからない」という人もいるかもしれません。
以下、知っておきたい支援制度をまとめました。
レスパイトケア
介護疲れの保護者の方々が一時的に休息できるよう、お子さんを預かるサービスです。
短時間から宿泊まで、様々な形態があります。
訪問支援サービス
専門家が自宅を訪問し、お子さんのケアや発達に関するアドバイスを行うサービスです。
日常生活のサポートや、専門的な療育を受けることができます。
発達障害者支援センターの相談支援
発達障害に関する専門的な知識を持つ相談員が、育児の悩みや発達に関する相談に応じます。
お子さんの発達評価や、適切な支援機関の紹介なども行っています。

各種支援制度については、お住まいの自治体の障害福祉課や児童福祉課などで相談できます。
支援制度は、自分で探さないと見つからないことが多いものです。
「助けが必要」と感じたら、遠慮なく相談しましょう。
使える制度を知ることで、育児の負担は確実に軽くなります。
「無理」と思ったときは、少し立ち止まることも大切です。
あなたが笑顔でいることが、子どもにとっても一番の幸せになるんです。

「手放す」という選択肢【罪悪感とどう向き合う?】

「もう無理……」そう思ったとき、「手放す」という選択肢もあります。
障害児の育児は、想像以上に負担が大きい。
24時間気を抜けず、心も体も限界を迎えることがあります。
それでも、「親なのだから」と無理をする人が多いんです。
でも、育児を続けることで親自身が壊れてしまっては意味がありません。
時には、施設に頼ることも必要です。
実際に、障害児を施設に預けた親の多くが「最初は罪悪感でいっぱいだった」と語ります。
でも、「自分の時間ができて、子どもと向き合えるようになった」という声も多いんです。

手放すことは「見捨てる」ことではありません。
親の心身の健康が守られてこそ、子どもも幸せになれるんです。
施設に預けることは悪いことなのか?
「子どもを施設に預けるのは親失格?」
そんなふうに思うかもしれません。
でも、施設を利用することは決して悪いことではありません。
むしろ、子どもにとってより良い環境を提供できる場合もあります。
実際に、障害児施設では専門の支援が受けられます。
個別の発達支援プログラムや、医療ケアが整っているところもあります。
親だけで抱え込むのは限界があります。
子どもにとって最善の環境を選ぶことも、大切な愛情のかたちです。

「手放す」という選択をした人の体験談
ここでは、子どもを施設に入所させた親御さんの体験談を紹介します。
揺れ動く心、押し寄せる葛藤:意思決定の過程
施設への入所という決断は、親御さんにとってどれほど重く、苦しいものだったでしょうか。
罪悪感、お子さんが新しい環境に馴染めるかという不安。
そして何よりも「この選択が本当に最善なのか」という問いかけが、幾度となく心をよぎったことでしょう。
あるブログには、お子さんの施設見学の様子が克明に綴られています。
ご家族全員で何度も話し合い、それぞれの想いを共有しながら、真剣に検討する様子が伝わってきます。
また、20代の重度知的障害を持つ息子さんを施設に入所させたお母様は、
「半年経った今でも、あの決断が正しかったのかと自問自答してしまう」と語っています。
この言葉からは、親御さんの心の奥底にある、拭いきれない葛藤が痛いほど伝わってきます。
施設入所を検討するまでの間、どれほどの苦悩があったのか、想像することしかできません。
だからこそ、親御さんの気持ちに寄り添い、その決断を尊重することが大切なんです。
*参考:
障害児入所施設へ見学
重度障害者の施設入所。
あなたを手放すそのひまで ~障害児入所の流れについて~
我が子のために、最善の環境を求めて:適切な施設の探索と選定
「子どものために、少しでもよい環境を見つけたい」
すべての親御さんに共通する願いです。
障害の種類や程度、子どもの個性やニーズに合わせて、親は様々な情報を集め、施設を探し始めます。
施設の専門性(特定の障害への対応)、所在地、スタッフの専門知識、施設の雰囲気や理念……
考慮すべき点は多岐にわたります。
施設見学は、親にとって非常に重要な機会です。
ある親御さんは、
「子どもだけでなく、家族全体のことも理解し、サポートしてくれるかどうかを確認することが大切」
と語ります。
また、幼児から高校生まで年齢別に完全に区切られた施設を見学した親御さんは、
「安全対策がしっかりと施されていることを確認し、ようやく安心できた」
と言います。
親は子どもの個々のニーズに合致し、安心して過ごせる環境を提供してくれる施設を、懸命に探しているんです。
*参考:
障害児入所施設へ見学
あなたを手放すそのひまで ~障害児入所の流れについて~
新しい生活への第一歩:移行期間と最初の適応
施設への入所が決まっても、すべてがうまくいくとは限りません。
新しい環境に戸惑い、不安を感じるのは、子どもだけでなく親も同じ。
この大切な期間を円滑に進めるためには、施設スタッフの温かいサポートが不可欠です。
あるブログで書かれている、グループホームへの入居が決まった息子さん。
引っ越し当日、強く抵抗する様子が綴られています。
親御さんの胸も締め付けられる思いだったでしょう。
別のブログでも、グループホームへの入居を嫌がっていた息子さんがいました。
でも、同じような経験をした親御さんのブログを読むことで、「自分だけではないんだ」と気持ちが楽に。
そして、決断に自信を持てたという体験談が語られています。
入所当初は、環境の変化からお子さんに不安や行動上の課題が見られることもあります。
しかしそれは新しい生活に慣れるための過程であり、周囲の理解とサポートが重要です。
*参考:
グループホーム入居を決意したらするべきこと
【実践報告】資料編児童施設入
我が子の成長という希望:子どもの発達と幸福への影響
施設に入所するという決断は、親御さんにとって断腸の思いだったかもしれません。
しかし、時が経つにつれて、お子さんの成長という形で、その決断が肯定的に捉えられるようになることも。
あるお母様は、施設に入所してから息子さんの落ち着きが増し、表情も明るくなったと感じています。
また、グループホームでの一人暮らしを通して責任感が芽生え、生活にメリハリがついたという利用者の声も。
施設では、入所しているお子さん一人ひとりの最大限の発達を保障することが目標。
専門的なケアや療育を受けることで、お子さんの社会性、自立心。
そして、全体的な幸福度が向上するケースも少なくありません。
親御さんは、日々成長していくお子さんの姿を見ることで、
「あのときの決断は間違いではなかった」
と、改めて感じているのではないでしょうか。
*参考:
グループホームの体験談!部屋の様子、支援員へのインタビューも!
障害児入所施設の機能強化をめざして
重度障害者の施設入所。
育児放棄とは違う?正しい知識を知る
「手放す」という選択をすると、「育児放棄だ」と言われることがあります。
でも、支援を利用することは育児放棄ではありません。
育児放棄とは、子どもの安全を無視して放置すること。
食事を与えない、必要な医療を受けさせない、暴力をふるう。
これらは「ネグレクト」と呼ばれ、虐待にあたります。
一方、施設や支援サービスを利用することは、子どもにとって最適な環境を整えることです。
「育てる責任を果たすために必要な判断」なんです。
「親が無理をして精神的に追い詰められるより、適切な支援を利用する方が、子どもにとってもよい」
そのことを忘れないようにしましょう。
「手放す=見捨てる」ではありません。
正しい知識を持ち、必要なサポートを活用することが大切です。
「育てられない」から「育てていく」へ【心を軽くする考え方】

「もう育てられない」
そう思うのは、決して珍しいことではありません。
育児は、体力も気力も必要な大変な仕事です。
特に、障害児の育児は24時間気が抜けません。
「自分には無理だ」と感じるのは、ごく自然なことです。
しかし、少し視点を変えてみると気持ちが軽くなることがあります。
育児を「すべて自分がやるべき」と思うと、負担が大きくなります。
でも、「育てる=一人で頑張ること」ではありません。

支援を受けることは、親としての責任を果たすことでもあります。
時には、周りに頼ることで、家族みんなが笑顔になれることもあるんです。
「全部自分で抱えなくていい」頼れる環境をつくる
「親だから、すべて自分でやらなきゃ」
そう思うと、どんどん辛くなります。
でも、育児は一人でするものではありません。
頼れる環境をつくることで、心がぐっと軽くなります。
たとえば、地域の子育て支援センターでは、障害児の親が集まり、悩みを共有しています。
福祉サービスを利用すれば、時間と心の余裕が生まれることもあります。
ショートステイや訪問支援を活用すれば、親も休むことができます。
一人で抱え込まず、周りに頼ることが大切です。
育児は、みんなで支え合っていいものなんです。

夫婦や家族との関係を良好に保つためにできること
障害児の育児は、夫婦や家族の関係にも影響を与えます。
ストレスがたまり、すれ違うことも少なくありません。
でも、関係を良好に保つために、できることはあります。
- 夫婦で役割を分担する
すべて母親がやるのではなく、協力し合うことが大切です。 - 感謝の言葉を忘れない
「ありがとう」を伝えるだけで、お互いの気持ちは変わります。 - 気持ちを話し合う時間を作る
育児の不満や悩みは、ため込まずに共有しましょう。 - 一緒に支援を受ける
相談窓口やカウンセリングを夫婦で利用するのも効果的です。
家族で支え合うことができれば、育児の負担も軽くなります。

お互いを思いやることが、何よりも大切です。
障害児を育てながら、親も自分の人生を大切にするには?
育児に追われると、自分のことを後回しにしがち。
でも、親自身の人生も大切にすることが重要です。
たとえば、「1日30分だけでも自分の時間を作る」と決めるだけで違います。
読書をする、散歩をする、好きな音楽を聴く。
そういった小さな楽しみが、気持ちをリフレッシュさせてくれます。
また、仕事や趣味を持つことも、心の支えになります。
実際に、「仕事があることで、気持ちのバランスが取れる」と話す親も多いです。
親が幸せでいることは、子どもにとってもよい影響を与えます。
「自分を大切にすることは、子どものためにもなる」
そう考えて、少しでも自分の時間を持つようにしてみてください。

まとめ:「障害児を育てられない」と感じるあなたへ
障害児の育児は、想像以上に大きな負担がかかります。
「もう無理」「逃げたい」と思うのは、決して珍しいことではありません。
しかし、育児は一人で抱え込むものではありません。
支援を活用し、頼れる環境を作ることで、心が軽くなることもあります。
- 「育てられない」と感じるのは普通のこと
- 頼れる支援や相談窓口がある
- 施設を利用する選択肢もある
- 夫婦や家族との関係を良好に保つことが大切
- 親自身の人生も大切にすべき
あなたが楽になることは、子どもの幸せにつながります。
完璧な親でいる必要はありません。
支援を受けながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
今回の記事が、少しでもお役に立てば幸いです。