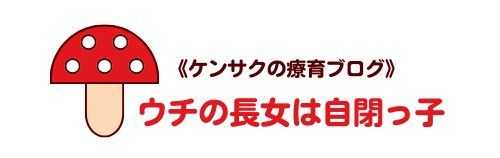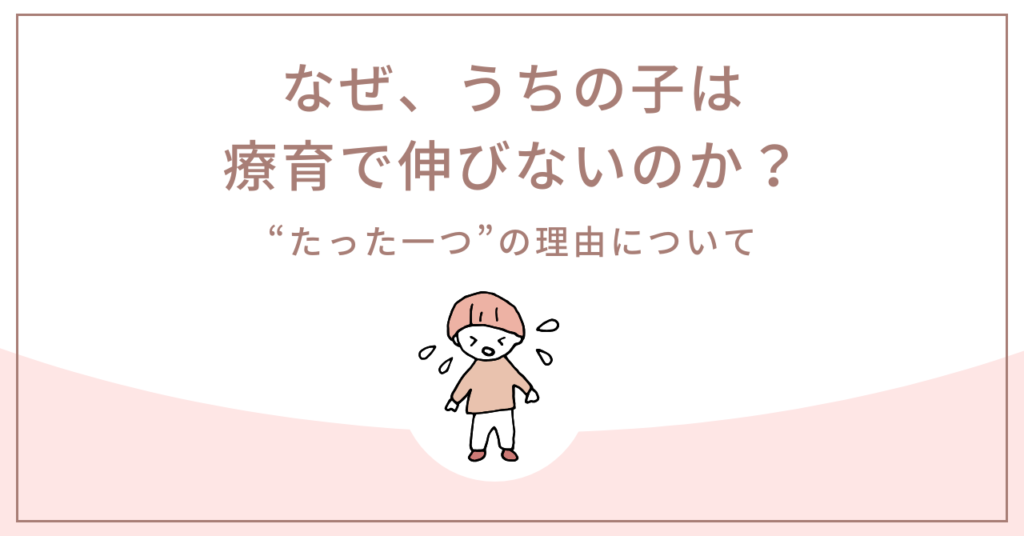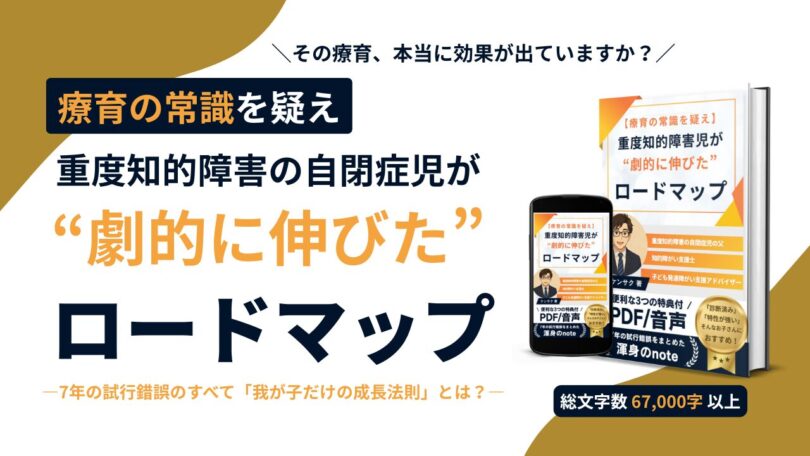「感覚統合を発達させる遊びやトレーニング方法、支援の具体例などについて詳しく知りたい」といった方へ。
私たち夫婦は発達障害の娘に感覚統合遊びを取り入れてきましたが、心と体の成長に大きく貢献してくれたと考えています。今回はその実体験をもとに、感覚統合遊びやトレーニング、支援の具体例について紹介します。
- 感覚統合遊びの効果
- 感覚統合を発達させる遊びやトレーニング方法、支援の具体例
- 感覚統合におすすめの療育
この記事を読めば感覚統合遊びについての理解が深まり、子どもへどのように取り入れたらよいのかがわかります。
私の娘の実体験をもとに紹介していますので、ぜひ参考にしてください!

※感覚統合については『子ども理解からはじめる感覚統合遊び 保育者と作業療法士のコラボレーション』という本を参考にしています。説明もわかりやすく、感覚統合の遊びや支援の具体例についても写真付きで解説されていて読みやすいので、興味のある方はご覧になってください。
目次
感覚統合遊びやトレーニングの具体例、おすすめ13選!

まず最初に、おすすめの感覚統合遊びやトレーニング、支援の具体例についてご紹介します。
感覚の調整に関するトラブル(感覚過敏、感覚鈍麻など)
- シーツブランコ
- 泥んこ遊び(砂遊び)
- 水遊び
- こちょこちょ遊び
- トランポリン
- ブランコ
感覚の識別・フィルターに関するトラブル(違いに気づかない)
- 自分のエリアをわかりやすくする
- 片づける位置をわかりやすくする
- 音当てゲーム
感覚に起因する姿勢・運動のトラブル(動きが不器用、目で追えないなど)
- 正座・立位
- ボールプール
- ビーズ通し(ひも通し)
- 風船バレー
これらは自宅や公園など、ご家庭でも行いやすい例ですが、感覚統合に強みを持つ療育(へやすぽアシスト)などを活用するのもおすすめです。
- へやすぽアシスト:
累計2万人以上のサポート実績を誇る、オンライン個別運動療育。子ども一人ひとりの特性に合わせた運動療育プログラムを実践。テレビや新聞、SNS等でも多数紹介されています。私の娘も体験してみました。
>>運動療育「へやすぽアシスト」をおすすめする理由【無料体験あり】

上記の具体例や療育については後ほど詳しくご紹介しますが、まずは感覚統合について簡単に説明していきます。
感覚統合とは?【感覚統合遊びの効果】

感覚統合とは、様々な感覚器官から入ってくる情報を脳が正しく分類・整理し、適切に反応する能力のことです。五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)のほかに、固有受容覚や前庭覚が重要な役割を果たします。

たとえば、目で見たものに対して手を伸ばしたり、バランスを保ちながら歩いたりするのは、感覚統合がうまく機能しているからこそ可能です。
発達に遅れがある子どもや発達障害児はこれらの能力が低下している状態で、特に触覚・固有受容覚・前庭覚にアンバランスが生じると言われています。
よって、こういった子どもたちに対して、遊びを通じて感覚統合機能を向上させるのは有効と考えられています。ちなみに、あまり聞きなじみのない固有受容覚と前庭覚とは、次のような意味です。
- 固有受容覚:
筋肉や関節にある受容器から得られる感覚で、自分の身体の位置や動きを知ることができます。 - 前庭覚:
内耳にある前庭器官から得られる感覚で、自分の身体がどの方向に動いているかを把握したり、重力に対して姿勢を保つことができます。
感覚統合遊びの効果
感覚統合遊びの効果は、主に以下の4つです。
1. 運動能力の発達
- 身体の動きの協調性:
感覚統合がスムーズに機能することで視覚情報と体の動きを連携させ、ボールをキャッチする、縄跳びをする、ハサミを使うといった動作をスムーズに行えるようになります。 - バランス感覚:
前庭感覚と固有受容覚の発達により、転ばずに歩く、片足で立つなどのバランスを必要とする動作を習得します。 - 姿勢の保持:
適切な感覚統合は、座っているときに姿勢を保つ、長時間集中して作業するといった行動をサポートします。
2. 学習能力の発達
- 集中力・注意力:
感覚統合がうまく機能しないと、周囲の刺激に過剰に反応したり、逆に無反応になったりすることがあります。感覚統合を促すことで適切な情報処理能力が育まれ、集中力や注意力の向上につながります。 - 読解力・書字力:
視覚と手の動きの連携がスムーズに行えるようになることで、 文字を書く、文章を読むといった学習活動が円滑になります。 - 空間認識能力:
空間認識能力は、周囲の環境や物体の位置関係を正確に把握する能力です。空間認識能力を高めることは、図形問題を解いたり、地図を読んだりする際に役立ちます。
3. 社会性・情緒の発達
- コミュニケーション能力:
感覚統合が適切に機能することで、相手の表情や声のトーン、仕草などから相手の気持ちを理解することができるようになります。 - 情緒の安定:
感覚刺激に適切に対応できるようになることで不安やストレスを軽減し、落ち着いて行動できるようになります。 - 適応力:
様々な感覚刺激を経験して状況に合わせて適切に対応することで、新しい環境や変化への適応力を身につけていきます。
4. 日常生活動作の発達
- 着替え、食事、トイレ
感覚統合は、ボタンをかける、箸を上手に使う、トイレで排泄するといった日常生活で必要な動作を習得する上でも重要な役割を果たします。
感覚統合がうまくいかないと、日常生活で様々な困りごとに直面します。 感覚統合遊びを通して楽しみながら五感を刺激し、体を動かす経験を通して感覚統合を促していけば、子どもの発達をサポートしていくことができます。

感覚統合遊びがなぜ重要なのか?
感覚統合遊びが重要な理由は、子どもの日常生活における基本的なスキルを養うためです。
感覚統合が適切に行われないと、子どもは周囲の環境に適応するのが難しくなり、学校生活や社会活動でのストレスが増大します。感覚統合遊びを通じて、視覚、聴覚、触覚、前庭感覚、固有受容覚の各要素をバランスよく刺激し、脳がこれらの情報を適切に処理する能力を高めることができます。
また、これらの遊びを継続して行うことで、子どもはより自信を持って行動できるようになります。

感覚統合遊びは、子どもの発達に必要不可欠な要素を強化するだけでなく、親子で楽しく取り組める点も大きな魅力です。
次からは、感覚統合を発達させる重要な「基礎感覚」について紹介していきます。
感覚統合を発達させる3つの感覚とその特徴

触覚・固有受容覚・前庭覚の3つの感覚は「基礎感覚」と呼ばれることもあり、日常生活における様々な活動において重要な役割を担っています。これらにトラブルが起きていると、それぞれ次のような反応が見られます。
触覚のトラブル
触覚には「防衛する役割」と「識別する役割」があります。
前者は、熱い熱湯に触ったときにパッと手を離したりするはたらき。後者は、筆箱とノートが入っているカバンの中からノートだけを手探りで探すといったようなはたらきです。
これらにトラブルが起きると、必要以上に「防衛する役割」を使ってしまうので、たとえば歯磨きや散髪を嫌がったり、泥やのりなどに触ることに抵抗を示すといった反応が見られます。
さらに、本来は触覚(親との触れ合いやスキンシップなど)を通じて情緒を安定させるところを「不快」と処理してしまい、すぐに癇癪を起こしたり泣いたりしてしまうことにもつながってしまいます。

固有受容覚のトラブル
固有受容覚にトラブルが起きると、手足を動かす感覚がわかりにくく、身体各部の位置・動きをとらえることも難しいため、力加減のコントロールが難しく動きも不正確になります。
よって、おもちゃなどを乱雑に扱ったり、友達の髪の毛を引っ張ったりしてしまうような困りごとが出てしまいます。さらに、体操が苦手、ボタンをとめられない、フォークや箸などの食器をうまく使えない、といったケースも多くなります。
前庭覚のトラブル
前庭覚にトラブルが起きると、姿勢保持・覚醒・眼球運動・自律神経などに影響を及ぼします。
- 姿勢保持:
重力にあらがえずに、たとえば椅子に座っていてもすぐにグニャっとうなだれてしまいます。 - 覚醒:
ゴロゴロしたり、話を聞いてもぼんやりすることが多くなります。 - 眼球運動:
物や人の動きを見続けられないので、ボール遊びなどが苦手です。 - 自律神経:
頭の位置の変化に過剰に反応したり、激しい揺れでもまったく酔わなかったりします。

これら3つの基礎感覚を発達させるためには、子どもが楽しく自発的に参加できるような遊びやトレーニング、支援を提供することが大切です。具体例については、次から詳しく見ていきましょう。
感覚統合を発達させる遊びやトレーニングの具体例(タイプごとに紹介)

感覚統合を発達させるには、前述の触覚・固有受容覚・前庭覚を刺激したり、身体を動かすのがおすすめです。
たとえば、外遊びでは砂場やブランコ、すべり台などの遊具を使って重力や動きに対応する感覚を鍛えることができます。室内遊びでは、粘土やスライムなどの手触りのあるものや、音楽や絵本などの聴覚や視覚に訴えるものを使って、触覚や聴覚を刺激することができます。
とはいえ、子どもによって困っていることは十人十色です。子どもがどのような特性を持っているかによって、感覚統合を発達させる方法は変わってきます。

冒頭で紹介した『子ども理解からはじめる感覚統合遊び 保育者と作業療法士のコラボレーション』では、子どもに起こっているトラブルを次の3つのタイプに分類しています。
- 感覚の調整に関するトラブル(感覚過敏、感覚鈍麻など)
- 感覚の識別・フィルターに関するトラブル(違いに気づかない)
- 感覚に起因する姿勢・運動のトラブル(動きが不器用、目で追えないなど)
タイプごとにどのような遊びや支援が必要か、具体例もまじえながら詳しく見ていきましょう。

今回は自宅や公園など、ご家庭でも行いやすいものに絞って紹介します。
①感覚の調整に関するトラブル(感覚過敏、感覚鈍麻など)
感覚に対する反応は人それぞれです。
たとえば、大きな音に対して過剰に反応する子ども(感覚過敏)もいれば、まったく気にしない子ども(感覚過敏)もいますので、対応の仕方は当然かわってきます。
感覚過敏の子ども

このタイプの子どもは、とにかく「安心・安全を保障する」ことが大切です。
たとえば、室内では室内遊び用のテントを用意したり、屋外では帽子や耳栓などを使用して感覚刺激を防衛する、といったことが求められます。子どもが安心感を得られたら、次のような遊びに取り組んでみましょう。
【シーツブランコ】
シーツやタオルなどを使って子どもを包んで揺らしたり、ひっぱったりする遊びです。体の感覚やバランス感覚を刺激することで、自分の体の位置や動きに気づかせることや、シーツに包まれることで安心感や心地よさを感じることができます。
遊ぶときは、シーツを揺らす強さや速さなどを調整しながら、声かけや歌などでコミュニケーションをとるのがよいでしょう。ちなみに娘もわりと好きです。

【泥んこ遊び(砂遊び)】
公園の砂場などで行います(素手で行うのがおすすめです)。手で砂を掘ったり、砂を型はめに詰めたり、スコップで穴を掘ったりするとよいでしょう。その際はお手拭きなどを準備しておき、汚れるのを嫌がったらすぐに対応できるようにしておきます。

遊びを通じて触覚や固有受容覚の刺激につながります。これは次に紹介する「感覚鈍麻」の子どもにもおすすめです。
【水遊び】
水の感触は多くの子どもにとって心地よいものです。水鉄砲、水風船、ジョウロなど、遊びの幅も広がります。 水遊びに抵抗がある場合は、洗面器に水を張って遊んだり、お風呂で泡遊びを楽しむのもよいでしょう。
感覚鈍麻の子ども

このタイプの子どもは、覚醒が低く集中力が低い傾向があります。ボーっとしていて活動に参加できないことが多いので、適切に感覚刺激や、興味・関心をくすぐることが必要になります。
次のような遊びがおすすめです。
【こちょこちょ遊び】
歌に合わせて子どもの手や足をくすぐったり、なぞったりする遊びです。身体感覚を刺激したり、表情や声の変化に気づくことが期待できます。
遊ぶときは子どもの反応や気分に合わせて、適度にくすぐるようにしましょう。私はくすぐり過ぎてしまいましたので……(笑)

【トランポリン】
トランポリンで跳ねることで体幹やバランス感覚が鍛えられ、脳幹に刺激が与えられます。また、飛んでいるときに色々な物を見ることで、目のトレーニングや集中力向上にもなります。

一人で跳ぶのが難しい場合は親が手を添えて一緒に跳ねたり、一人で跳べる場合でも「ジャンプ!ジャンプ!」などと声をかけてあげることで、楽しく活動できるとよいでしょう。
【ブランコ】
前後に大きく揺られることで、前庭覚を刺激します。安全面に配慮しながらも、体を思い切り動かすように促すとよいでしょう。
②感覚の識別・フィルターに関するトラブル(違いに気づかない)

このタイプの子どもは、「似ている形の違いがわからない」「どの音に注意を向けたらよいかわからない」「味の違いがわからない」など、感覚の違いを識別して情報の取捨選択を行うことが苦手な傾向があります。

よって、注目するべき情報とそうでない情報の違いをわかりやすくしてあげる必要があります。具体的には次のような支援や遊びがおすすめです。
【自分のエリアをわかりやすくする】
たとえば、食事のときは自分の食べ物だけをランチョンマットの上に置く(他人の食べ物に手を出さない)など、境界線をわかりやすくして自分と他人のエリアを明確化してあげるとよいでしょう。
【片づける位置をわかりやすくする】
たとえば、玄関で靴を脱ぐときは👣マーク(足跡マーク)を置いておいて正しく脱がせる(玄関では靴を脱ぐ、その際は靴をそろえて脱ぐ)など、視覚的に位置を明確化するとよいでしょう。
【音当てゲーム】
色々な音を聞かせて何の音かを当てさせるゲームです。音の違いに耳を傾けることで、聴覚を刺激し、音の識別能力を高めることができます。動物の鳴き声、乗り物の音、楽器の音など、身近な音を素材にするのがおすすめです。
音は録音しておくか、親が真似して発声してもよいでしょう。
③感覚に起因する姿勢・運動のトラブル(動きが不器用、目で追えないなど)

このタイプの子どもは、前庭覚や固有受容覚の情報が脳に届きにくくいので、姿勢が崩れやすく、座位や立位などの姿勢を保ちにくいといった特徴があります。また、手先が不器用だったり、眼球運動が苦手な傾向も。
こういった子どもたちには、次のような方法がおすすめです。
【正座・立位】
いきなり長い時間正座や立位を行うのは難しいと思いますので、まずは10秒でも20秒でもやってみることが大切です。
その際、正座であれば座布団の上だったり、立位であれば少しだけ高さのある台の上でやってみると効果的です。娘も同じ方法で、ある程度の時間できるようになりました。

【ボールプール】
ボールプールに入ってボールが動くことで、触覚や固有受容覚が変化します。
ボールプールに入っている自分の身体がどのようになっているのかを把握することで、ボディイメージの発達につながります。
【ビーズ通し(ひも通し)】
数十個のビーズと何本かのひもを用意し、ビーズをひもに通して遊びます。
当然、指先を器用に使う必要がありますし、目線を常にひもに集中しなければなりません。目と手の協調動作の発達につながります。
【風船バレー】
ゆっくりと動く風船を追いかけることで、視覚を刺激します。風船の動きを予測することで、目の追従性を高める練習になります。

以上、3つのタイプについてご紹介しましたが、『子ども理解からはじめる感覚統合遊び 保育者と作業療法士のコラボレーション』の中ではさらに多くの遊びが紹介されています。細かいタイプ分けもされていますので、「もっと詳しく知りたい」という方は書籍をご覧になってください。
なお、こちらで紹介したトランポリンやひも通しなどのおもちゃについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。
>>【実体験】自閉症児におすすめのおもちゃ12選!|夢中になるものを紹介
感覚統合遊び・トレーニングのポイントと注意点
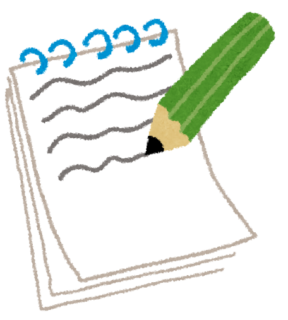
感覚統合遊びの効果については前半で述べた通りですが、もう少し具体的に言うと、以下のような成長が期待できます。
- 自己認識や社会性が育まれて「他者とのコミュニケーションが円滑になる」
- 身体のバランスや協調性が向上して「字を書くような細かい動作がスムーズになる」
- 空間認識や注意力が高まることで「落ち着いて物事に取り組むことができる」
とはいえ、もちろん一朝一夕にいくものではなく、失敗も繰り返しながら取り組んでいくこととなります。もちろん、娘も同じです。。

感覚統合遊びの効果が出るまでの期間はもちろん個人差があります。ある程度長期的な視点で取り組むことが重要です。
以下、感覚統合を発達させる遊びやトレーニング、支援のポイントと注意点をまとめました。
子どもの反応をよく観察する
感覚統合遊びの効果は、子どもの反応を見ながら判断する必要があります。
楽しんでいる様子が見られる場合はその活動を継続すべきですし、嫌がる様子が見られる場合は無理強いせずに遊び方を変えたり、別の遊びに切り替えたりするなど、柔軟に対応することが大切です。
遊びの難易度や刺激の強さを調整する
感覚統合遊びは、子どもの発達段階に合わせて難易度や刺激の強さを調整することが重要です。
たとえばブランコが苦手な場合は、低い位置でゆっくりと揺らすことから始めたり、トランポリンでは最初は座ったままジャンプさせてみたりするなど、段階的に刺激に慣れていく工夫をしてみましょう。
療育を活用する
ご家庭で感覚統合遊びの効果が出にくいと感じたり、子どもに合った遊び方が分からなかったりする場合は、感覚統合に強みを持つ療育を活用してみましょう。
おすすめの療育については、次で紹介します。

一番大事なのは、子どもに興味・関心をもって取り組んでもらうことですので、無理のないペースで取り組むのがよいでしょう。
感覚統合の発達におすすめの療育
感覚統合を発達させるために、ここまでは家庭でもできる方法を中心にご紹介してきましたが、療育を活用するのも効果的です。
おすすめは、娘が体験したへやすぽアシスト。累計2万人以上のサポート実績があり、各種メディアやSNS等で話題のオンライン療育です。
へやすぽアシスト

一人ひとりの特性に合わせた運動療育プログラムを実践しているオンライン運動療育です。オンラインでも、エンタメ要素を取り入れた独自の仕掛けを施しているので、子どもが飽きる心配はいりません。Zoomを使用して自宅で受講できるので、通室時間を気にする必要もなく、送迎の手間も省けます。
コースは1回50分。発達特性や運動面での課題に合わせて、感覚統合をはじめとした、縄跳び・鉄棒・協調運動・ボディイメージの養成など、個別プログラムを作成します。テレビや新聞など、各種メディアでも取り上げられている、注目の療育です。
今なら期間限定で、30分の無料体験授業を実施中です。通常だと3,300円の授業が無料となっているので、この機会にぜひ検討してみてください。
\期間限定で無料体験実施中!/
以下の記事で、娘が体験した様子やへやすぽアシストの詳細をご覧いただけます。
まとめ【タイプに合わせて最適な感覚統合遊びを】
以上、感覚統合を発達させる遊びやトレーニング、支援の具体例についてまとめました。
まずはお子さんがどういったトラブルを抱えているか(どのタイプに該当するか)を判断したうえで、適切な感覚統合の遊びや支援に取り組んでみてください。

正直、娘もこれらすべての取り組みを毎日行っているわけではありませんが、やればやるほど少しずつできるようになってきたのは事実です。感覚統合を発達させて、少しでもお子さんの成長をサポートしてもらえると嬉しいです。
今回は家庭での取り組み方を中心にご紹介しましたが、へやすぽアシストのように感覚統合にも力を入れている療育を活用するのも有効です。ぜひ、この機会に検討してみてください。
今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
- へやすぽアシスト:
累計2万人以上のサポート実績を誇る、オンライン個別運動療育。子ども一人ひとりの特性に合わせた運動療育プログラムを実践。テレビや新聞、SNS等でも多数紹介されています。
>>運動療育「へやすぽアシスト」をおすすめする理由【無料体験あり】