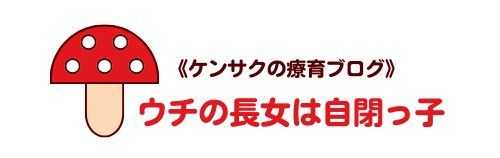「高齢出産なんて、しなきゃよかったのかもしれない……」または「高齢出産、やめたほうがいいのかな……」と思われている方へ。
このページにたどり着いたあなたは、そんな不安の中にいるのではないでしょうか。
私は重度知的障害を伴う自閉症の長女を育てる父親です。
その長女は、妻が高齢出産に近い年齢で出産し、結果的には障害児でした。
もし、もっと若いときに授かっていたら……
そんな「後悔」という二文字が頭をよぎったことは、これまでたくさんありました。
このブログ記事は、そんな絶望の中でも前を向くことを決めた私たち夫婦の話です。
きれいごと一切なしの現実と、「高齢出産になるから悩んでいる」という不安を希望に変えるための具体的な方法を、私たち夫婦の経験と、信頼できる情報に基づいてお伝えします。

- 「高齢出産しなきゃよかった」という実際の声
- 高齢出産のデメリット・メリット
- 高齢出産で後悔しないために、今できること
※本記事にはプロモーションが含まれています。
目次
「高齢出産しなきゃよかった」——ネットに溢れる“後悔”の声
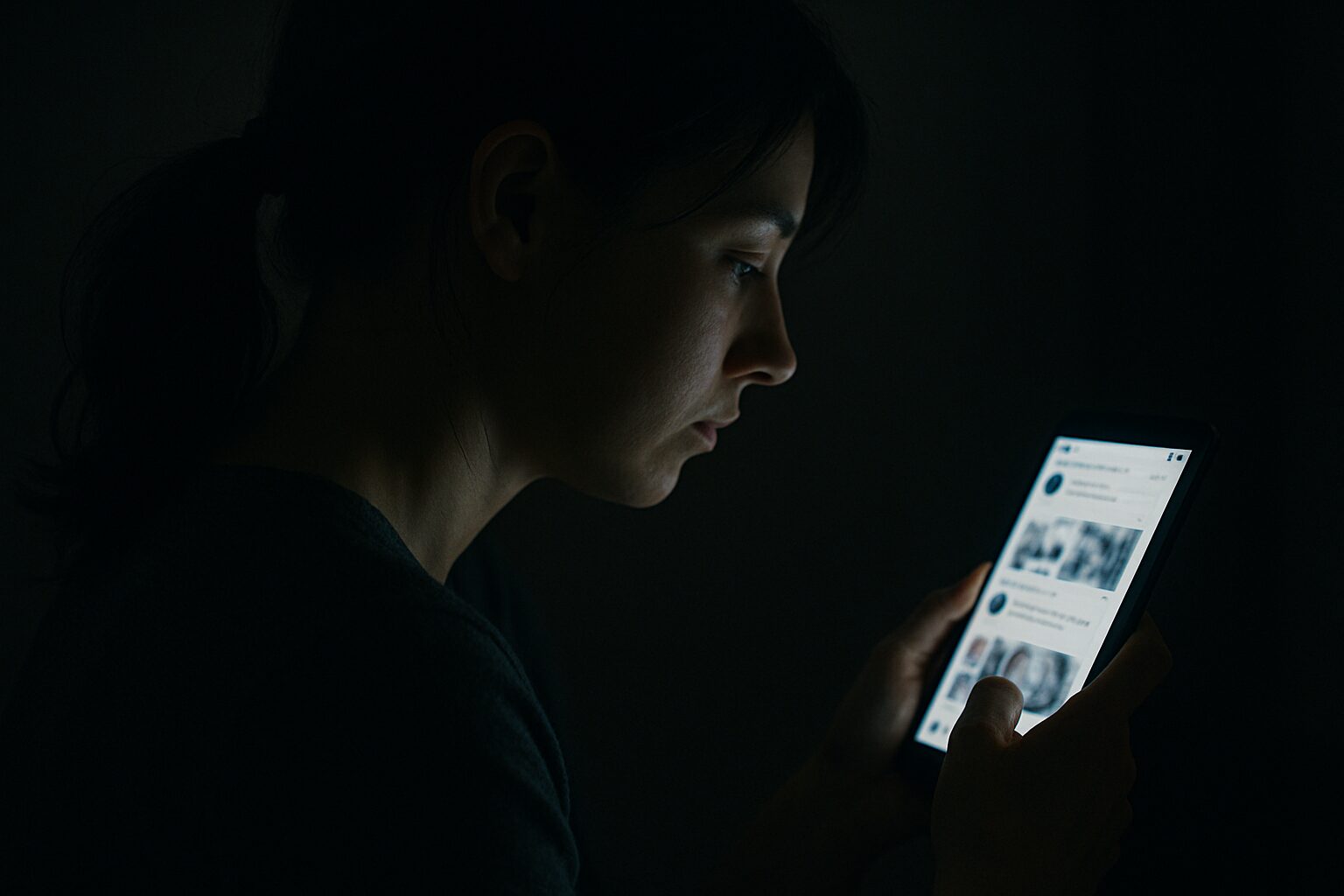
「こんなこと思うなんて、母親失格だ……」
「周りはみんな幸せそうなのに、どうして私だけ……」
そうやって自分を責めていませんか?
でも、それは決してあなた一人だけではありません。
SNSや個人のブログには、同じように悩む人たちの痛切な叫びがあふれています。

少しだけ、耳を傾けてみてください。
これは、あなたと同じ痛みを知る“仲間”の声です。
体力的な悩み
「産婦人科で泣く子を見て、高齢出産の寝不足育児は産後うつ必至。相手がいないと無理。」
「高齢自然分娩は事故級の地獄。産後3年死んでた。金かけた方が予後良い。」
子どもとの時間への不安
「40&43歳出産で、子供との時間が短いのが本当のしんどさ。」
「高齢出産で子供と過ごす時間が短く、老いて寂しい思いさせるかも。」
障害リスクへの不安
「高齢出産で障害リスク大。一生面倒見て死後心配。余裕ない。」
子どもの視点からの声
「高齢出産の子供側で最悪。恥ずかしく、介護早い。産まれてきたくなかった。」
これらの声は、決して他人事ではありません。
インターネット上の多くの体験談の中で、後悔の理由として特に多く語られていたのが、
「若いうちに産めばよかった」という体力や、子どもと過ごせる時間の短さに関するものでした。
わかる……夜泣きでフラフラなのに、公園では走り回る子を追いかけないといけない。
本当に「若い頃の体力、返して!」って何度も思いました。。

そして、もう一つが、
障害を持つ子どもが生まれたときの「知っていれば……」という、情報に対する後悔です。
特に、出生前診断を受けなかったことへの後悔は、多くの体験談で繰り返し語られています。
あなたのその苦しみや不安は、決して間違っていません。
むしろ、それだけ真剣に子どもと向き合っている証拠なんです。
なぜ私たちは不安になるのか? 高齢出産が抱える4つの「壁」

では、なぜ多くの人が「高齢出産しなきゃよかった」という気持ちに悩まされてしまうんでしょうか。
それは、個人の気持ちの問題だけではなく、乗り越えなければならない、大きく分けて4つの「壁」が存在するからです。
①医学的な壁:避けられない身体のリスク
これは、多くの人が最初に直面する壁です。
年齢を重ねることで、私たちの身体にはどうしても変化が訪れます。
- 母体へのリスク:
35歳を過ぎると、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの合併症が増え、帝王切開になる割合も高まることが指摘されています。
*出典:国立成育医療研究センター「高齢出産は高リスク?」/厚生労働省資料「年齢と妊娠・出産に伴う合併症のリスク」 - 胎児へのリスク:
最も不安に感じるのが、赤ちゃんへの影響でしょう。
卵子の加齢により、染色体数的異常のリスクは年齢とともに上昇します。
たとえばダウン症候群(21トリソミー)の出生時リスクは、40歳で約1/100(約1/98)です。
また、流産のリスクも年齢とともに上昇し、40歳ではおよそ4割程度とされています。
*出典:Prenatal Screening Ontario「年齢別の確率」/Cleveland Clinic「Advanced Maternal Age」/BMJ 2019(ノルウェー全国登録研究) - 産後の負担:
無事に出産を終えても、戦いは続きます。
産後の身体的・精神的な回復支援が重要で、産後うつのハイリスク群(EPDS9点以上)は産後1か月で約9.7%という行政データがあります。
*出典:こども家庭庁 資料(EPDS9点以上=9.7%)/厚労省「産婦健康診査におけるEPDS活用」
これらの数字は、時に私たちを打ちのめします。
しかし、これは目を背けてはいけない、出発点となる現実なんです。
②経済的な壁:忍び寄る「ダブルケア」と「老後破産」
私自身、これが一番リアルな恐怖でした。
子どもの将来と、自分たちの老後。
その両方が、重くのしかかってくるんです。
- ダブルケアの現実:
高齢出産の場合、子育てに手がかかる時期と、自身の親の介護が必要になる時期が重なる「ダブルケア」の可能性が非常に高くなります。
サポートを受ける側であるはずの祖父母が、介護の対象になってしまうんです。
*出典:内閣府 男女共同参画局「ダブルケア実態調査報告書」 - 教育費・老後資金の負担:
40歳で子どもを持った場合、その子が大学を卒業するのは親が60代前半。
そこから老後資金を準備する時間はほとんど残されていません。
教育費と老後資金を同時に準備する「二重の負担」は、高齢出産の家庭が直面する構造的な問題です。
③精神的な壁:ママ友との孤立と「みっともない」という自己嫌悪
身体やお金の問題と同じくらい、心をむしばむのが社会的なプレッシャーです。
- 周囲の視線:
「おばあちゃんに間違われたらどうしよう……」という不安や、他の若いお母さんたちとの年齢差からくる孤立感。 - 内面化された羞恥心:
「出産は若いうちに」という社会の価値観に縛られ、「高齢出産はみっともない」と自分自身を責めてしまう苦しみ。 - 「かわいそうな子ども」という呪い:
「お母さんが年寄りだから、この子はかわいそう」
そんな心無い言葉や視線が、母親の罪悪感を増幅させます。
しかし、覚えておいてください。
第一子出産の約30%が35歳以上の女性というデータもあるように、高齢出産は、もはや「例外」ではなく、現代社会の「当たり前」になりつつあるんです。
*出典:厚生労働省「人口動態統計(確定数)2023」
④情報量の壁:「知らなかった」では済まされない現実
そして、これらすべての壁の根底にあるのが「情報」の壁です。
特に、出生前診断については、「知っていれば、心の準備ができたかもしれない」「知っていれば、違う選択ができたかもしれない」という声が後を絶ちません。
情報を知っているか、いないか。
その差が、未来を大きく左右してしまう可能性があります。
【高齢出産時の対策】私たちが“本気で”取り組んだ「5つのこと」

長女の障害がわかったとき、私たち夫婦はどん底にいました。
しかし、いつまでも泣いてはいられない。
もし、もう一度子どもを授かる機会があるなら、絶対に後悔だけはしたくない。
その一心で、私たちは二女・三女を妊娠する前は、本気で準備を始めました。
以下は、具体的な行動の話です。
①【大前提】夫婦で現実と向き合う。
一番最初にやったことは、少しかっこ悪いですが、お互いの不安や恐怖をすべて吐き出すことでした。
「障害のある子がまた生まれたらどうしよう」
「育てていける自信がない」
どちらかが一方を責めるのではなく、二人で一緒に現実と向き合う。
それがすべての始まりでした。
②【栄養】妻だけでなく私も飲んだ。「葉酸サプリ」というお守り
「できることは、全部やろう」
そう決めて、まず始めたのが葉酸サプリでした。
葉酸は、妊娠の1か月以上前から妊娠3か月まで、通常の食事に加えて1日400μgの摂取が神経管閉鎖障害のリスク低減に有効とされています。
*出典:厚生労働省 e-ヘルスネット「葉酸とサプリメント」
- 妻が飲んでいたもの:【BELTA】厚生労働省推奨の葉酸サプリ
- 私(夫)が飲んでいたもの:【makana(マカナ)】

長女のときは、私自身は何もしていませんでした。
その反省から、二女と三女のときは、夫である私も当事者としてサプリを飲むことに決めたんです。
結果的には、二女も三女も健常児として生まれてきてくれました。
もちろん、それが直接的な効果があったかは科学的には分かりません。
でも、「夫婦で一緒に取り組んでいる」という事実が、何よりの心の支えになりました。
③【検査】長女のとき、知らなかったことを悔やまないために。私たちがNIPTを選んだ理由
これは、私たちにとって最も大きな決断でした。
そして、今、「高齢出産になるので悩んでいる」というあなたに、一番伝えたいことです。
長女のとき、私たちは新型出生前診断(NIPT)という検査の存在をよく知りませんでした。
もし知っていたら……という気持ちが、ずっと胸の内にありました。
NIPTは、母親の血液を採るだけで、お腹の赤ちゃんがダウン症などの染色体数的異常を持つ可能性を、妊娠10週前後から高精度で推定できるスクリーニング検査です。
*出典:国立成育医療研究センター 解説/こども家庭庁 報告書

もちろん、命の選別につながるという倫理的な議論があることも理解しています。
私たちも、何度も何度も話し合いました。
ただ、現実問題として、育てるのは想像を絶する苦労があります。。

私たち夫婦がNIPTを受けることになった経緯や理由、NIPTの詳細については、以下の記事をご覧ください。
>>出生前診断を受けなかったら後悔する?【NIPT体験談と後悔しない選択】
④【備え】万が一の先の、万が一に備える。「臍帯血保管」という未来への投資。
もう一つ、私たちが行った「未来への備え」が、臍帯血の保管です。
臍帯血とは、出産時にしか取れない、へその緒や胎盤に含まれる血液のこと。
この中には、体の様々な細胞の元になる「幹細胞」が豊富に含まれています。
*出典:東京都保健医療局「さい帯血移植について」/日本赤十字社:Q&A
現在、自閉症や脳性麻痺など、治療が難しいとされてきた病気に対して、この臍帯血を使った再生医療の研究が世界中で進んでいます。
長女が自閉症である私たちにとって、これは一筋の光でした。
すぐに治療法が見つかるわけではないかもしれない。
でも、将来、娘を救う可能性が少しでもあるのなら、それに賭けたい。
そう思い、二女・三女の出産時に臍帯血を保管することを決めました。

高齢出産によるリスクを考えると、妊娠中であれば臍帯血の保管を一度は検討すべきです。
臍帯血保管に関する私たち夫婦の実体験は、以下の記事で詳しく紹介しています。
>>【実体験】臍帯血を保管せず、本当に後悔しない? 自閉症児を持つ親が語る「保管すべき理由」
⑤【相談】一人で抱えない。自治体、病院、そして同じ境遇の仲間を頼る。
最後に、もう一つ大切なことです。
どうか、一人で抱え込まないでください。
妊娠・出産は、孤独な戦いになりがちです。
でも、あなたの周りには、手を差し伸べてくれる人が必ずいます。
- かかりつけの産婦人科医
- 自治体の保健師さん
- 家族や信頼できる友人
- 同じ痛みを知る当事者
専門家を頼り、公的なサポートを最大限活用してください。
それが、あなたの心と体を守る一番の方法です。
【高齢出産だからこその光】我が子に「出会えてよかった」

ここまで、高齢出産の厳しい現実と、私たちが行った対策についてお話ししてきました。
では、私は今、「高齢出産をしなければよかった」と思っているのか。
答えは、断じて「NO」です。
もちろん、子育ては大変です。
特に障害のある長女との毎日は、体力も精神力も削られます。
でも、高齢出産だったからこそ、得られたものも確かにありました。
多くの体験談でも語られているように、高齢出産にはメリットも存在するんです。
経済的な安定
若い頃よりも収入が安定していたから、長女の療育や治療に、選択肢を持って臨むことができました。
精神的な成熟
社会の荒波に揉まれてきた経験があったから、予期せぬ出来事にも、少しは冷静に対処できたのかもしれません。
確立された人間関係
周囲には子育てを終えた先輩がたくさんいて、彼らのリアルなアドバイスは、何よりも心強いものでした。
何より、私がもし若い頃に結婚していたら、今の妻と出会い、この子たちの父親になることもなかったでしょう。
大変なことは山ほどある。
でも、娘たちの寝顔を見るたびに、私は心の底から思うんです。
「あなたたちに出会えて、本当によかった」と。
まとめ:「高齢出産しなきゃよかった」という不安に悩まされた、あの日の私へ
「高齢出産しなきゃよかった」
そう思ってしまう自分を、どうか責めないでください。
その感情は、あなたが母親として、一人の人間として、真剣に命と向き合っている証です。
そして、今妊娠中で、「高齢出産、やめたほうがいいのかな……」と悩まれている方へ。
不安は、決してなくならないでしょう。
でも、それを乗り越えるための「武器」を持つことはできます。
それが、正しい情報であり、事前の備えです。
- 健康的な生活を送る
- 葉酸サプリを活用する
>>おすすめ「【BELTA】厚生労働省推奨の葉酸サプリ」「【makana(マカナ)】」 - NIPT(新型出生前診断)で「知る」選択をする
>>「出生前診断を受けなかったら後悔する?【NIPT体験談と後悔しない選択】」で詳しく紹介中 - 臍帯血保管で未来の可能性に備える
>>「【実体験】臍帯血を保管せず、本当に後悔しない? 自閉症児を持つ親が語る「保管すべき理由」」で詳しく紹介中 - 一人で抱えず、専門家や仲間を頼る
高齢出産は、決して簡単な道のりではありません。
しかし、しっかりとした準備と、周囲のサポートがあれば、その先には、かけがえのない喜びが待っています。
あなたの選択を、後悔で終わらせないでほしい。
この記事が、あなたの暗闇を照らす、小さな光となることを心から願っています。