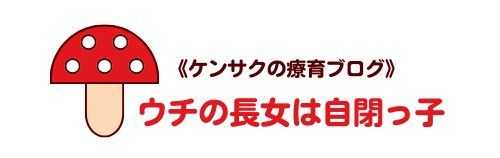「周りの子と、うちの子、何かが違う気がする……」
「もしかして、自閉症なのかな……?」
1歳のお子さんを育てながら、言葉にならない「違和感」を抱え、不安な気持ちでこのページにたどり着いた親御さんへ。
その胸のざわめき、痛いほどよくわかります。
はじめまして、ケンサクと申します。
重度知的障害を伴う自閉症の長女を育てる父親です。
今でこそ娘の特性を理解し、日々楽しく格闘(?)していますが、長女が1歳だった頃の私たち夫婦は本当に不安でした。
「まさか発達障害や自閉症ではないよな……」と打ち消したい気持ちと、「でも、やっぱりどこか違う」という拭えない不安。
毎日その狭間で揺れ動いていました。
喃語はなく、名前を呼んでも振り向かない。
指さしもせず、お座りさえ苦手で癇しゃくばかり……そんな日々の中で感じていた途方もない不安と孤独感を、今でも鮮明に覚えています。
この記事では、そんな出口の見えない不安を抱える親御さんのために、私たち夫婦が経験してきたこと、そして学んだ知識を総動員して、以下のことをお伝えします。
- 1歳児に見られる自閉症の具体的なサイン(チェックリスト付)
- その「違和感」の正体と、親としてどう向き合えばいいか
- 一人で抱え込まないための具体的な相談先とアクション
- 診断を待つ間に家庭でできる、親子の絆を深める関わり方
あなたのその「違和感」は、決して気のせいではありません。
それは、お子さんを深く見つめているからこその、大切なサインです。
このブログ記事が、あなたの不安を整理し、希望を持って次の一歩を踏み出すためのお守りになれば、これほど嬉しいことはありません。

目次
1歳児への「違和感」は自閉症のサイン?|まず知ってほしいこと

「何かが違う」と感じるけれど、それが具体的に何なのか言葉にできない。
1歳の頃の「違和感」とは、そういう漠然としたものですよね。
でも実は、その直感の背景には、いくつかの共通したパターンが隠れていることが多いんです。
多くの専門機関や育児情報サイトで指摘されている1歳頃の自閉症(ASD)のサインを、3つのカテゴリに分けてまとめました。
あなたの感じている「違和感」がどれに当てはまるか、一緒に見ていきましょう。
社会的コミュニケーションのサイン:目が合いにくい、反応が薄い
これは、ASDの中心的な特性の一つで、人との関わり方に現れます。
- 目が合いにくい、またはそらす:
抱っこしても、授乳中でも、なんだか目が合わない。
合ってもすぐにそらしてしまうことがあります。 - 名前を呼んでも振り向かない:
聞こえているはずなのに、何度呼んでも知らんぷり。
まるで自分の名前を認識していないように見えることがあります。 - 指さしをしない:
興味があるもの(犬や飛行機など)を指さして「見て!」と伝えようとしません。
また、大人が「ワンワンだよ」と指さした方を見ようとしないこともあります。 - バイバイなどの真似をしない:
周りの大人がやっている「バイバイ」や「パチパチ」といった簡単な身振りを真似しようとしません。 - あやしても笑い返さない:
「いないいないばあ」をしても反応が薄かったり、笑顔が少なかったりします。
行動や興味のかたより:同じことを繰り返す、独特な遊び方
遊び方や興味の対象が、少しユニークに見えることもあります。
- おもちゃの一部分に執着する:
ミニカー全体で遊ぶのではなく、タイヤだけを指でずーっとクルクル回している、といった行動です。 - 物を一列に並べる:
積み木を積んだり、車を走らせたりするのではなく、ただひたすらキレイに並べることに熱中します。 - 同じ行動を繰り返す(常同行動):
部屋の同じ場所を行ったり来たりする。
手を目の前でヒラヒラさせるなどの動きが見られることもあります。 - 一人遊びが多く、他人に興味が薄い:
他の子がいる場でも輪に入ろうとせず、一人で黙々と遊び続けます。
親がいなくなっても平気なことがあります。
感覚のかたより:とても敏感、またはとても鈍感
五感の感じ方が、定型の子たちと少し違うことがあります。
これが「育てにくさ」につながることも多いです。
- 特定の音を極端に嫌がる(聴覚過敏):
掃除機やドライヤー、赤ちゃんの泣き声などを聞くと、耳をふさいでパニックになります。 - 抱っこや触られるのを嫌がる(触覚過敏):
抱っこしようとすると体を反らせて嫌がることがあります。
特定の素材の服や靴下を断固として拒否することもあります。 - 極端な偏食(味覚・嗅覚過敏):
離乳食がなかなか進まない。
特定の食感や見た目のものしか受け付けない、といった様子です。 - 寝つきが悪い、夜泣きが激しい:
ささいな物音や光で起きてしまったり、一度泣き出すと30分以上泣き止まなかったりします。
【我が家の場合】長女に見られた1歳の頃のサイン
一般的なサインを読んで、「うちの子はどうだろう?」と思われたかもしれません。
参考までに、当時1歳だった私の長女に「違和感」として感じていた具体的な様子をお話しします。
喃語がない(発語もない)
周りの子が「まんま」「わんわん」と言い始める中、意味のある言葉どころか、「あーうー」といった赤ちゃんらしいおしゃべりもほとんどありませんでした。
家の中があまりに静かで、「この子は何を考えているんだろう」と不安で胸が張り裂けそうでした。
指差しをしない
公園で犬を見ても、空に飛行機が飛んでいても、それを指さして私たちに教えようとすることが全くありませんでした。
感動を共有できない、という見えない壁を感じていました。
名前を呼んでも振り向かない
これは最も初期に感じた違和感です。「もしかして耳が聞こえないのでは?」と本気で心配になり、耳鼻科で聴力検査も受けました。
結果は異常なし。聞こえているのに、振り向かない。
その事実に、言いようのない不安を感じたのを覚えています。
お座りが苦手
体幹が弱かったのか、ベビーチェアに座らせてもすぐにぐにゃっと傾いてしまい、一人で安定して座っていることができませんでした。
離乳食をあげるのも一苦労でした。
癇癪が多い
一度スイッチが入ると、火がついたように泣き叫び、それが1時間以上続くこともありました。
何をしても泣き止まず、理由もわからず、夫婦で途方に暮れる毎日でした。
多動傾向がある
とにかく落ち着きがなく、常に動き回っていました。
家の中でも外でも、一瞬目を離した隙にどこかへ行ってしまい、道路に飛び出しそうになって肝を冷やした経験は一度や二度ではありませんでした。
1歳児の気になるサイン・チェックリスト
これは診断ツールではありませんが、専門家に相談する際の参考になります。
3〜5個以上、継続的に見られる場合は、一度相談を検討してみてもいいかもしれません。
| カテゴリ | チェック項目 |
|---|---|
| 社会的 コミュニケーション | □ 目が合いにくい、またはそらす □ 名前を呼んでも、ほとんど振り向かない □ 興味のあるものを指さして伝えようとしない □ 「バイバイ」など簡単な身振りを真似しない □ あやしても、あまり笑い返さない □ 他の子どもにほとんど興味を示さない |
| 行動・興味 | □ おもちゃを機能的に遊ぶより、一列に並べることを好む □ 車のタイヤを回し続けるなど、おもちゃの一部分に固執する □ 同じ場所を行ったり来たりするような、同じ動きを繰り返す □ 大人の手を取り、道具のように使って欲しいものを取ろうとする(クレーン現象) |
| 感覚・その他 | □ 抱っこされるのを嫌がったり、のけぞったりする □ 掃除機など特定の音を極端に嫌がる □ 特定の服や靴下を履くのをひどく嫌がる □ 食べ物の好き嫌いが極端で、特定の物しか食べない □ 寝つきが悪かったり、夜中に何度も起きたりする |
「うちの子、当てはまる…」と思ったら。まず知ってほしい2つのこと

チェックリストを見て、「やっぱりうちの子、当てはまる……」と、ドキッとしたかもしれません。
でも、ここでパニックになる必要はありません。
今、あなたに知っておいてほしい、大切なことが2つあります。
これは「個性」なの? 「自閉症のサイン」との違いは「一貫性」
でも、1歳なんて発達に個人差が大きいって言うし、ただの個性なのかなって思ったりもして……。


1歳児の発達は、本当に個人差が大きいです。
では、どこで見分けるか。ポイントは、その行動が「 一時的か、一貫しているか」「特定の状況だけか、様々な場面で見られるか」です。
たとえば、たまたま疲れていて名前を呼んでも振り向かない子もいます。
でも、どんなに機嫌が良くても、静かな場所でも、 一貫して振り向かない場合は、サインの可能性が高まります。
一人遊びが好きな子もたくさんいますが、親が関わろうとしても全く興味を示さず、持続的に孤立した遊び方をする場合は、少し注意が必要かもしれません。
大切なのは、一つの行動だけで判断するのではなく、複数のサインが、様々な場面で、継続的に見られるかという視点です。
【一番伝えたい】自閉症は、親の育て方や愛情不足が原因ではありません
もし、心のどこかで「私の育て方が悪かったのかな」「愛情が足りなかったのかな」と自分を責めているなら、今すぐその気持ちを手放してください。
自閉症は、生まれつきの脳機能の障害であり、育て方や愛情不足が原因ではありません。
これは、科学的に証明されている事実です。
あなたは何も悪くない。
愛情が足りないなんてことは、決してありません。
むしろ、誰よりもお子さんのことを想い、心配しているからこそ、今こうして情報を集めているはずです。
どうか、ご自身を責めることだけはしないでください。
不安を「次の一歩」に変えるための具体的なアクションプラン

「原因が育て方じゃないことはわかった。でも、じゃあこれからどうすればいいの?」
そう思った方へ。
漠然とした不安を、具体的な「次の一歩」に変えていきましょう。
Step1:まずは「記録」から始めよう
専門家に相談に行くとき、一番役に立つのが「客観的な記録」です。

「何が気になりますか?」と聞かれても、いざとなるとなかなか上手く説明できないんですよね。私たちもそうでした。
だから、 簡単なメモや育児日記でいいので、「いつ、どこで、どんな行動が気になったか」を書き留めておくことを強くおすすめします。
さらに効果的なのが スマホでの動画撮影。
言葉で説明しにくい独特な動きや癇癪の様子など、ありのままを撮っておくと、診察の場で非常に役立ちます。
Step2:一人で抱え込まず「相談」しよう
記録が少し集まったら、勇気を出して専門家に相談してみましょう。
1歳半健診は重要なチャンス
多くの自治体で行われる1歳半健診は、発達の専門家に相談できる最初の公的な機会です。
ここでは「M-CHAT」という質問紙を使って、発達の様子を確認することがあります。
もし何か指摘されても、それは診断ではなく、あくまで「早期支援につなげるためのきっかけ」です。
臆せず、日頃の心配事を話してみてください。
どこに相談すればいい? 主な相談先とその役割
健診を待たずに相談したい場合、以下のような窓口があります。
| 機関名 | 主な役割 | こんなときに |
|---|---|---|
| 市区町村の 保健センター | 育児に関する全般的な相談窓口。保健師さんが話を聞いてくれる。 | 「何から相談していいかわからない」という最初の段階に。 |
| かかりつけの 小児科医 | 発達に関する初期評価と、必要なら専門機関への紹介状を書いてくれる。 | まずは身近な先生に聞いてみたいときに。 |
| 児童発達支援 センター | 発達に支援が必要な子どもへの「療育」の提供や相談。 | 療育に興味がある、具体的な支援を受けたいと考え始めたときに。 |
| 発達障害者支援センター | 発達障害に関する専門的な相談や情報提供。 | 診断がなくても、発達障害について幅広く知りたいときに。 |
相談に行くのは勇気がいるけど、一人で悩んでいるよりはいいかもしれないですね。


私たちも市の福祉窓口に相談したことで、臨床心理士さんとの面談につながり、そこから自治体の療育へと道が開けました。あのとき、勇気を出して電話して本当に良かったと思っています。
Step3:「診断」までの道のりを知っておこう(焦らないで)
1歳という年齢では、すぐに「自閉症です」と診断が下りることは稀です。
多くの場合、確定診断は3歳前後になることが多いと言われています。
相談に行っても、「もう少し様子を見ましょう(経過観察)」と言われることも少なくありません。
すぐに白黒つかない状況はもどかしいですが、「我が子の特性を理解し、関わり方を学ぶための準備期間」と捉えて、焦らずに進んでいきましょう。
よくある質問(Q&A)

ここでは、多くの親御さんが抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q
1歳で自閉症の診断はできますか?
A
1歳で確定診断が下りることは非常にまれです。
早ければ1歳半頃から診断されることもありますが、多くは3歳前後です。
1歳半健診などで指摘されるのは、あくまで早期の支援につなげるための「スクリーニング(ふるい分け)」であり、確定診断ではありません。
Q
言葉の遅れだけが気になります。これも自閉症のサインですか?
A
言葉の発達は個人差が非常に大きいものです。
言葉の遅れだけで自閉症と判断することはできません。
大切なのは、言葉の遅れに加えて、これまでお伝えしてきたような「目が合いにくい」「指さしをしない」といった社会的コミュニケーションのサインが見られるかどうかです。
言葉の理解が進んでいるかどうかも合わせて見ていく必要があります。
Q
夫(パートナー)に相談しても「考えすぎだ」と言われます。どうすればいいですか?
A
これは「あるある」で、多くのご家庭で起こることです。
温度差があると、ママ一人が抱え込んでしまい辛いですよね。
そんなときは、感情的に「何かがおかしい」と訴えるだけでなく、客観的な事実を見せるのが効果的です。
Step1で紹介した「気になる行動の記録や動画」をパートナーと共有してみてください。
また、「専門家も大事だと言っているから」と伝えて、1歳半健診に一緒に行ってもらうのも良い方法です。
第三者の意見を聞くことで、パートナーの理解が得られやすくなることがあります。
診断を待つ間に。お家でできる「親子の絆を深める」関わり方のヒント

「様子見」と言われても、親としては何かしてあげたいですよね。
診断を待つ間も、お家でできることはたくさんあります。
それは「訓練」ではなく、「親子の絆を深める」ための工夫です。
- 子どもの「好き」な世界に寄り添ってみる:
もしお子さんがタイヤを回すのが好きなら、「クルクルだねー」と一緒に言いながら隣で回してみてください。
大好きなことに共感してもらえるのは、子どもにとって何より嬉しいことです。
そこからコミュニケーションが芽生えることもあります。 - 言葉だけでなく「見てわかる」工夫を:
言葉の理解がゆっくりな子も多いです。
「お風呂だよ」と声かけするだけでなく、お風呂のアヒルのおもちゃを見せるなど、言葉と実物をセットで伝えると理解しやすくなります。
これは「視覚支援」といい、療育でも使われる基本的な手法です。
なるほど……関わり方にもコツがあるんですね。
どんなおもちゃや絵本がいいんだろう?


うちの長女が夢中になったおもちゃや、言葉を促すのに役立った絵本については、別の記事で詳しく紹介しています。
ぜひ参考にしてみてください。
早期療育は、親子にとっての「心強い味方」です

もし専門機関に相談してすすめられたら、ぜひ「早期療育」を検討してみてください。
療育って何? 子どもにとってどんな効果があるの?
療育とは、発達に特性のあるお子さん一人ひとりに合わせた専門的な支援のことです。
遊びを通して、コミュニケーションの力や社会性を伸ばしていくお手伝いをしてくれます。
早期に療育を始めることで、子どもの脳が柔軟なうちに発達の土台を築き、将来の困難を減らすことができると言われています。
療育が「親の心」を救ってくれる理由
でも、療育の本当の価値は、それだけではありません。

私が一番伝えたいのは、療育は「親を救ってくれる場所」でもあるということです。
専門家から我が子への具体的な関わり方を教えてもらえることで、「どうしていいかわからない」という無力感が和らぎます。
そして何より、同じ悩みを持つ仲間(ママ友・パパ友)に出会えます。
「うちだけじゃなかったんだ」と分かり合える仲間がいるだけで、心がどれだけ軽くなるか。
孤独な子育てから、チームで子育てに挑む感覚に変わるんです。
うちの長女も、療育に通い始めてから少しずつ落ち着きが出てきて、できることも増えました。
でもそれ以上に、私たち夫婦が「この子のままでいいんだ」と受け入れ、前向きになれたのは、療育のおかげです。
療育、すごく大事なんですね。
でも、健常児だったら逆効果なのかあとか、どこに行けばいいのかなあとか、色々考えちゃいます……。


その気持ちもよくわかります。以下の記事では、そんな疑問にお答えしています。
たとえ健常児だったとしても、療育の経験は子どもの成長にとってプラスになることばかりです。ぜひ読んでみてください。
【まとめ】「違和感」は、我が子を誰よりも深く理解するためのスタートライン
ここまで、長い文章を読んでくださって、本当にありがとうございました。
1歳の子どもに自閉症の可能性を感じる……その不安は、経験した人にしかわからない、本当に辛いものだと思います。
でも、どうか忘れないでください。
あなたが感じているその「違和感」は、子育ての失敗のしるしなどではありません。それは、
お子さんの個性を誰よりも深く理解し、その子に合ったサポートを見つけるための、正しく、そして愛情に満ちたスタートラインなんです。
道は、あなたが想像していたものとは少し違うかもしれません。
でも、あなたは決して一人ではありません。
ご紹介したようなサインが多く見られる場合は、勇気を出して相談してみてください。
そして、お家ではお子さんの「好き」に寄り添ってみてください。
焦らず、でも着実に、今できることから一歩ずつ。
その一歩が、お子さんにとって、そしてあなた自身にとって、希望に満ちた未来へとつながっていくはずです。
今できることを、冷静に考えて、行動に移してみてください。
この記事が、あなたの心の重荷を少しでも軽くし、前へ進むための小さな灯りとなれたなら幸いです。