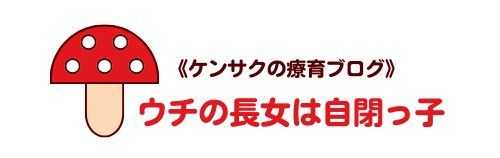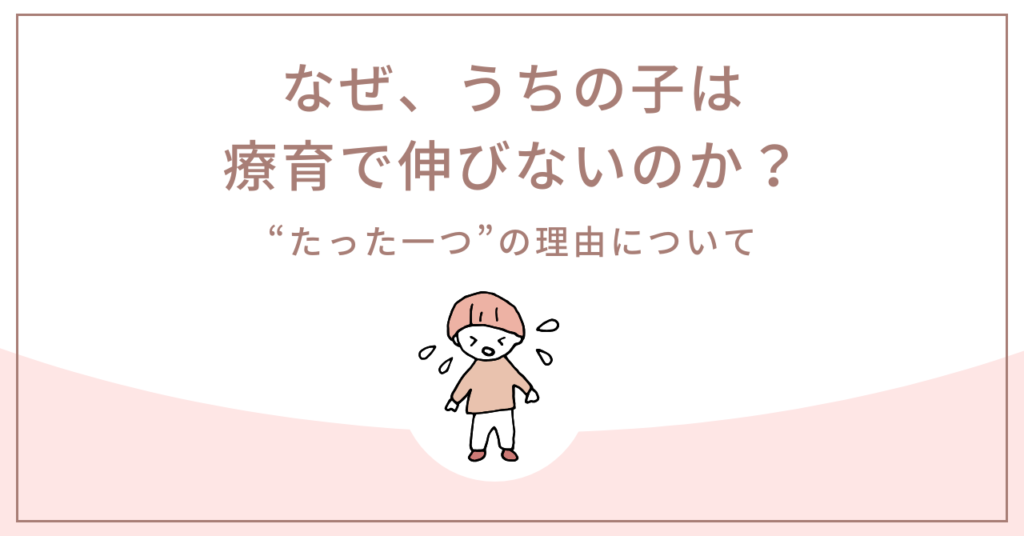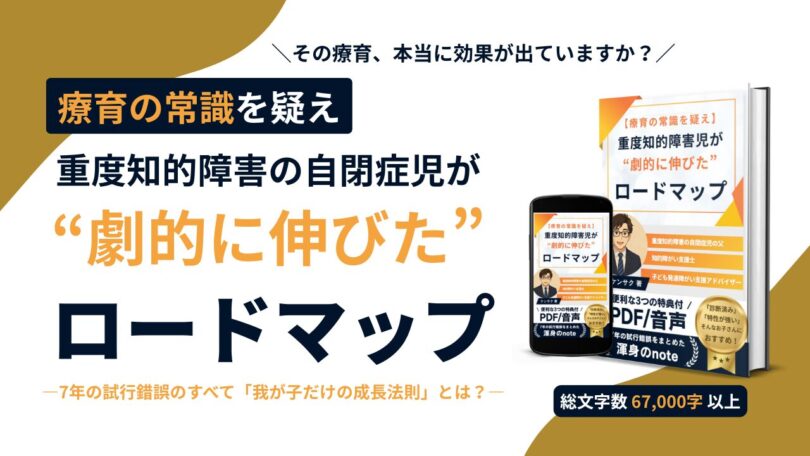「うちの子、バイバイするときに手のひらが自分に向いてる……これって大丈夫?」
「逆さバイバイは自閉症のサインって本当?」
1歳から2歳頃のお子さんによく見られる「逆さバイバイ」。
発達に関する情報に触れる中で、ふと不安に駆られる瞬間があるかもしれません。
でも、まずは焦らないでください。
逆さバイバイは健常児にもよくある動作です。
私の娘も、かつては逆さバイバイをしていました。
この記事では、そんな実体験を交えながら、逆さバイバイの疑問や不安を解消していきます。
- 逆さバイバイしていても問題ないのか?
- なぜ逆さバイバイをするのか?
- 発達障害を心配すべきケースの見分け方
- 我が家で効果があった、逆さバイバイのなおし方
このブログ記事を最後まで読めば、「逆さバイバイ」に対するモヤモヤが晴れ、今日からお子さんとどう向き合えばよいかが明確になるはずです!

目次
逆さバイバイは問題ない? 健常児でもやる?

まず一番にお伝えしたいのは、逆さバイバイは多くの健常児に見られるごく自然な発達の一過程だということです。
特に1〜2歳の子どもにはよく見られます。
「逆さバイバイ=発達障害」と結びつけるのは早計です。
ほとんどの場合、成長とともに自然に正しいバイバイができるようになります。

逆さバイバイは、多くの健常児にも見られる行動です。
なぜ健常児でも逆さバイバイをするのか?
子どもが逆さバイバイをする主な理由は、発達段階特有の「不器用さ」にあります。
大人の動きを「見たまま」真似しているから
子どもは、大人が自分に向けてくれる手のひらを一生懸命に真似しようとします。
しかし、相手の視点に立って「手のひらを外側に向ける」という変換がまだうまくできません。
そのため、自分から見えるのと同じように、手のひらを自分側に向けてしまうのです。
これを、専門的には鏡像反応と呼びます。
手や指のコントロールがまだ発達途中だから
大人にとっては簡単な「手を振る」という動作も、子どもにとっては複雑な運動です。
指や手首、腕を協調させて動かす練習の過程で、自然とやりやすい形が逆さバイバイになることがあります。
多くの子は、心と体が成長するにつれて、2歳を過ぎる頃から自然と正しいバイバイができるようになります。
逆さバイバイをしていても、多くの場合、問題はありません。

【要注意】逆さバイバイに「他のサイン」が重なるとき

「ほとんどが大丈夫」と聞いても、やはり気になってしまいますよね。
逆さバイバイ自体は問題ありませんが、他の発達のサインと合わせて見ることが重要です。
もし、逆さバイバイに加えて以下の様子が複数見られる場合は、少し注意深く見守り、必要であれば専門家への相談を検討しましょう。
心配なサインのチェックリスト
✅ コミュニケーションのサイン
- 名前を呼んでも、振り向かないことが多い
- 「ワンワン、いたね」などと指をさしても、そちらを見ない
- 自分の興味があるものを指さして伝えようとしない
- 視線が合いにくい、または目が合ってもすぐに逸らしてしまう
- 「ちょうだい」と言っても、なかなか物を渡してくれない
✅ 言葉の発達のサイン
- 2歳になっても意味のある単語(ママ、ブーブーなど)がほとんど出てこない
- 言葉が出ても、オウム返し(エコラリア)が多い
- 言葉でのやりとりが一方通行になりがち
✅ 社会性・遊びのサイン
- 他の子どもにあまり関心を示さず、一人遊びを好む
- ごっこ遊びのような、想像力を働かせる遊びをしない
- おもちゃを本来の遊び方とは違う、独特な方法(並べるだけ、回すだけなど)で遊び続ける
✅ 行動のサイン
- 3歳を過ぎても逆さバイバイが続く
- バイバイ以外の動作(手づかみ食べなど)も、どこか不自然でぎこちない
- 特定の物や手順に強いこだわりがあり、変化を極端に嫌がる
【実体験】問題があったケースとなかったケース
私の妻のママ友の話です。
1歳半健診で逆さバイバイの指摘があり、 他の発達には問題がなかったため、経過観察に。
でも2歳頃になると、自然に手のひらを相手に向けたバイバイができるようになり、結果的に問題はなかったそうです。
一方、我が娘の場合。
逆さバイバイが長く続きました。
そして、上記のチェックリストにあるような他のサイン(視線が合いにくい、言葉の遅れなど)も複数当てはまっていました。
結果として、娘は知的障害を伴う自閉症と診断されたのです。

この経験から言えるのは、逆さバイバイという一つの事象だけで判断するのではなく、お子さんの発達全体を温かく見守ることが何よりも大切だということです。
なぜ逆さバイバイをするのか?【詳しく解説】

そもそも逆さバイバイとは、子どもが手のひらを自分に向けて振る仕草のこと。
逆手バイバイと呼ばれることもあります。
なぜ逆さバイバイをするのか。
理由をもう少し詳しく解説していきます。
逆さバイバイが出る理由を、もう少し具体的に
逆さバイバイは、主に以下の2つの原因で生じます。
鏡像反応
子どもは自分が相手から見られている姿を想像できないため、相手の動作をまねするときに鏡像的に反応します。
たとえば、相手が右手で手を振ると、子どもは左手で手を振ります。
同様に、相手が手のひらを外側に向けて手を振ると、子どもは手のひらを内側に向けて手を振ってしまうのです。

逆さバイバイをする子どもは、
自分に向いている手のひらが、相手にも見えていると思っているんです。
視覚的注意
子どもは、自分が見ているものに強く注意を向けます。
たとえば、他人が手を振るときに手のひらが見えると、子どもは手のひらに注目します。
そのため、自分が手を振るときにも手のひらを見ようとしてしまいます。

これらの原因は、
子どもがまだ自分と相手の視点を切り替えたり、
自分と相手が同じものを見ているのを認識する能力が発達していない、
といったことと関係があると考えられています。
逆さバイバイの発達段階と年齢
逆さバイバイは、子どもの発達段階に応じて変化します。
以下は、一般的な逆さバイバイの発達段階と年齢です。
生後9ヶ月~1歳
子どもは他人の手を振る動作に反応して、自分も手を振り始めます。
しかし、まだ手のひらの向きには気づかず、健常児でも逆さバイバイをすることがあります。
1歳~2歳
子どもは他人の手のひらに注目して、自分も手のひらを見ようとします。
しかし、手のひらを見ると逆さになってしまうことには気づかず、
健常児でも逆さバイバイを続けてしまうことがあります。
2歳~3歳
子どもは自分と相手の視点を区別できるようになります。
そのため、正しいバイバイをすることができます。
逆さバイバイは、子どもの発達に合わせて自然に改善されることが多いです。
そういう点では、幼児期に逆さバイバイをしていても問題ないケースが多いと言えるでしょう。

しかし、3歳を過ぎても逆さバイバイをしている場合は注意が必要です。
ちなみに、私の娘もしばらく逆さバイバイをしていましたが、次に紹介する方法で改善することができました。
【実体験】逆さバイバイをなおす方法|健常児にも有効

「いつか直るかな」と待つのも一つの手ですが、「できることなら教えてあげたい」と思うのが親心ですよね。
我が家では、知的障害のある娘にも効果があった、とても簡単な3つのステップを根気強く続けました。
特別な道具は何もいりません。
今日からすぐに試せます。
ステップ1:正しいお手本を「楽しく」見せる
一番シンプルで、基本となる方法です。
子どもが逆さバイバイをしたとき、またはバイバイをする場面で。
焦らず、笑顔で、正しいお手本を見せてあげましょう。
- 「〇〇(ママ・パパ)はこうやるよ〜」
と声をかけながら、手のひらをしっかり相手(外側)に向けて振ってみせます。
「バイバーイ!」と明るく声をかけると、まねしやすくなります。 - 子どもと同じ方向を向いてお手本を見せるのがコツです。
対面だと、子どもにとっては左右が逆に見えてしまい、混乱することも。
一緒に鏡を見ながらやるのもよいでしょう。 - 間違いを指摘するより、「こうするともっとカッコいいね!」など、
ポジティブな言葉で促すのがおすすめです。
「あれ?おてて逆さまかな?」と優しく問いかけるのもよいですが、
言い過ぎないようにしましょう。
ステップ2:できた瞬間を「逃さず」褒める
ほんの少しでも、偶然でも、正しいバイバイができた瞬間を見逃さずに、
「おお!今のバイバイ、上手だったね!」
「すごい!できたね!」
と、少し大げさなくらいに褒めてあげましょう。
- 具体的に「手のひらがバイバイできたね!」など、
何がよかったのかを伝えましょう。
子どもは「これが正しいんだ!」と理解しやすくなります。 - 褒められることで、「またやってみよう!」という意欲につながります。
これは逆さバイバイに限らず、子どもの成長を促す基本ですね。
ステップ3:優しく「動きをガイド」する
子どもがバイバイをするとき、そっと手首や腕(肘のあたり)に手を添えて、
正しい手のひらの向きになるように優しく誘導してあげる方法です。
- あくまで優しく、お子さんの抵抗がない範囲で行いましょう。
無理強いは逆効果です。 - 言葉だけでなく、体の感覚を通して正しい動きをインプットさせます。
「自分でできた!」という感覚をサポートしてあげましょう。

我が娘の場合、自閉症という特性もあり、この方法で完全になおるまで1年以上かかりました。
おそらく何百回、何千回と繰り返したと思います。
でも、根気強く続けた結果、ちゃんとできるようになったのです。
お子さんのペースに合わせて、気長に取り組んでみてください。

また、以下の動画では上記の方法以外も解説されています。
参考にしてみてください。
逆さバイバイは自閉症のサイン?【関連性と見守るポイント】

「もしかして、うちの子の逆さバイバイは自閉症のサインなの?」
インターネットなどで情報を目にし、このように不安に思われる親御さんもいるかもしれません。
逆さバイバイが自閉症の特性の一つとして挙げられることがあるのは事実です。
でも、まず一番にお伝えしたい大切なことがあります。
それは、逆さバイバイだけで、「この子は自閉症だ」と判断することは絶対にできないということです。

すでにお話ししたように、逆さバイバイは健常児にもごく普通に見られるものです。
また、自閉症と診断されているお子さんでも、逆さバイバイをしないケースもたくさんあります。
では、なぜ逆さバイバイと自閉症が関連付けて語られることがあるのでしょうか?
そして、どのような点に注目して見守ればよいのでしょうか。
逆さバイバイと自閉症が関連付けられる理由
自閉症の特性の一つに、「他者の視点に立って考えることの難しさ」が挙げられることがあります。
バイバイをするとき、相手からどう見えているかを想像するのではなく、
自分が見えている手の甲を相手に向けて振ってしまう(=逆さバイバイ)ことが、
この特性と関連しているのではないか、
と考えられているためです。
また、自閉症の子どもは、動きをまねすること(模倣)に特有のパターンがある場合もあり、
それが逆さバイバイの形で現れる可能性も指摘されています。

ただし、これらはあくまで可能性の話であり、医学的に確立された原因というわけではありません。
健常児と自閉症児で見られる「違い」の傾向とは?
逆さバイバイが「心配ないか」「少し注意して見守る方がよいか」を考える上で、
一つの目安となるのが「年齢」と「他の発達面の様子」です。
健常児の場合
多くの場合、逆さバイバイは一時的なものです。
個人差はありますが、周りの人のまねをしたり、コミュニケーションが発達したりするにつれて、
2歳〜3歳頃までには自然と正しい手の振り方に変わっていくことが多いと言われています。
自閉症児の場合(傾向として)
自閉症の特性がある子どもの中には、3歳を過ぎても逆さバイバイが長く続くケースが見られることがあります。
重要なのは、逆さバイバイに加えて、以下のような特徴が年齢相応の発達と比べてゆっくりだったり、
難しい様子が見られたりする場合です。
- 視線が合いにくい、名前を呼んでも振り向かないことが多い
- 指さしをしない(興味のあるものを指さして伝えたり、大人の指さした方を見たりしない)
- 言葉の発達がゆっくり、言葉が出ても一方的、オウム返し(エコラリア)が多い
- 他の子に関心を示さない、一人遊びを好む
- 特定の物事への強いこだわりがある、遊び方が独特
- 感覚の過敏さ、または鈍感さがある(特定の音を極端に嫌がる、逆に痛みを感じにくいなど)
ウチの長女の場合も、 逆さバイバイが長く続いたことに加え、
視線が合いにくい、言葉でのコミュニケーションが難しいといった、
他の特徴も併せて見られました。

なお、以下の記事で、長女の自閉症に気づいたきっかけについてまとめています。
大切なのは「全体像」を見ること
繰り返しになりますが、逆さバイバイはあくまで「たくさんのサインの中の一つ」に過ぎません。
上に挙げた特徴も、一つ二つ当てはまるからといって、すぐに自閉症と結びつくわけではありません。
子どもの成長には個人差があります。
大切なのは、逆さバイバイという一つの行動だけに注目するのではなく、
日々の生活の中でのコミュニケーションの様子、遊び方、興味の示し方など、
子どもの発達全体を温かく見守ることです。
もし、逆さバイバイが長く続くことに加え、上記のような他の特徴も複数見られ、
「ちょっと気になるな」「育てにくさを感じるな」と親御さんが感じ続ける場合は、
一人で抱え込まないでください。

その際は、かかりつけの小児科医や子育て支援センター、発達専門の医療機関などに相談してみることをおすすめします。
不安な場合は、とにかく早めの相談・行動が大切です。
なお、まだ療育に取り組まれていない場合は、早めの検討をおすすめします。
療育は早いに越したことはありませんし、もし健常児であっても成長を促すことにつながります。
早期療育のメリットや、おすすめの療育や・療育の選び方などについては、以下2つの記事で詳しく紹介しています。

逆さバイバイについて、よくある疑問

逆さバイバイについて、多くの親御さんが気になる点や不安に感じる点をまとめます。
Q
逆さバイバイは、いつまで続いたら心配すべき?
A
一つの目安は3歳です。
多くの子は2〜3歳頃までに自然に直りますが、3歳を過ぎても逆さバイバイが主なやり方である場合は、言葉の遅れなど他の発達面もあわせて注意深く観察し、かかりつけの小児科や地域の子育て支援センターなどに相談してみることをおすすめします。
Q
逆さバイバイと自閉症の関連性は、医学的に証明されているの?
A
いいえ、「逆さバイバイをするから自閉症だ」という直接的な医学的根拠はありません。
ただし、自閉症の特性の一つである「他者の視点を理解する難しさ」や「動きの模倣の特異性」が、逆さバイバイという形で現れる可能性があると考えられています。
あくまで全体像を見るための一つのサインと捉えましょう。
Q
逆さバイバイを無理に直そうとすると、悪影響はありますか?
A
はい、あります。
叱りつけたり、強制的に手の向きを変えたりすると、子どもはバイバイ自体が嫌いになったり、親とのコミュニケーションに不安を感じたりする可能性があります。
あくまで本記事で紹介したような「楽しく、優しく、根気強く」というアプローチを心がけてください。
まとめ:逆さバイバイは健常児でもやる、でも注意はしよう
逆さバイバイをしていても問題はないのか、健常児でもやるのか。
そして、その逆さバイバイのなおし方について詳しく解説しました。
この記事で解説してきた要点をまとめます。
- 逆さバイバイは、健常児にもよく見られる自然な発達過程です。
- それ単体で自閉症と判断することは絶対にできません。
- 判断する際は、言葉やコミュニケーションなど「発達の全体像」を見ることが重要です。
- 3歳を過ぎても続くなど、他のサインと合わせて気になる場合は、専門機関に相談しましょう。
お子さんの逆さバイバイに気づいたとき、それは同時にお子さんの成長を注意深く見守る素晴らしい機会でもあります。
不安な気持ちは、それだけあなたがお子さんを愛している証拠です。
もし「育てにくさを感じるな」「ちょっと気になるな」という気持ちが続くなら、どうか一人で抱え込まないでください。
かかりつけの小児科医、地域の子育て支援センター、保健師さんなど、相談できる場所はたくさんあります。
早めに相談し、必要であれば早期療育のようなサポートにつながることは、お子さんの健やかな成長を促す上で非常に価値のあることです。
この記事が、あなたの不安を和らげ、次の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。