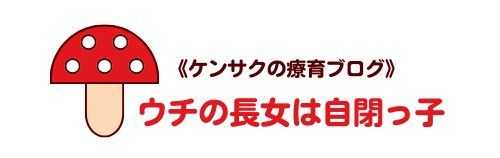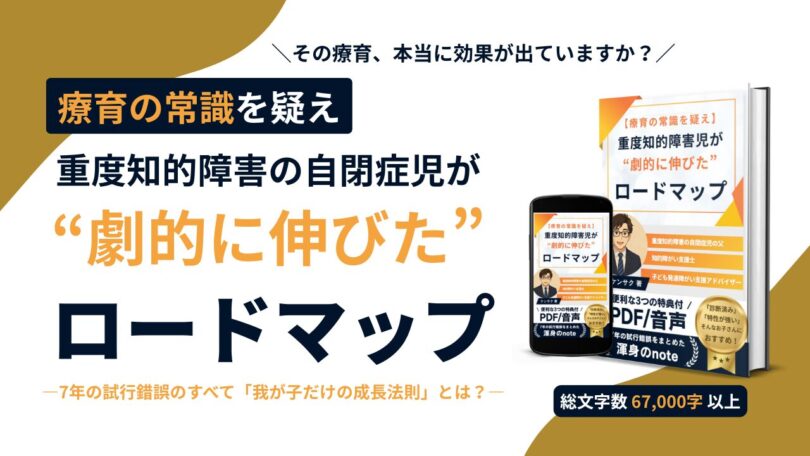「妊娠中だけど、もし障害のある子が生まれたらどうしよう……」
「障害児が生まれたら、私たちの生活はどうなるの?」
そんな、言葉にしづらい、でも切実な不安を抱えていませんか?
私は発達障害(重度知的障害を伴う自閉症)の長女と、定型発達(健常児)の二女を育てる父親です。
このブログ記事では、私たち夫婦の経験と専門知識に基づき、「障害児が生まれたらどうしよう」という、誰もが抱える可能性のある不安に向き合います。
- 障害児が生まれることへの不安は、自然な感情
- 障害のある子が生まれたときに、その日から始めること
- 利用できる公的な支援制度や相談窓口(申請方法のヒントも)
- 家族(父親、きょうだい児、祖父母)との関わり方
- 妊娠中にできること、不安を減らすための選択肢
- 障害児育児を乗り越えるための心構えと希望
大切なのは、正しい情報を知り、利用できるサポートを理解すること。
そうすれば、漠然とした不安は具体的な行動へと変わり、前向きな一歩を踏み出すことができます。
この記事を読めば、もし障害のある子が生まれた場合の具体的なステップも、妊娠中にできる後悔しないための備えも、両方わかります。

※本記事にはプロモーションが含まれています。
目次
「障害児が生まれたらどうしよう……」その気持ちは自然なこと

「障害児が生まれたらどうしよう……」
「できることなら、健常児を産みたい……」
妊娠中の方や、これから親になることを考えている方。
このような気持ちは決して特別なものではありません。
むしろ、ごく自然な感情だと思います。
私たち夫婦も、発達障害のある長女を育てる中で、本当に、本当に大変な思いを経験してきました。
だからこそ、これからお子さんを望む方が「健常児が欲しい」と願う気持ちは、痛いほど理解できます。
この記事をご覧の方の中にも、ご自身やご家族、身近な方に障害があって、苦労された経験があるかもしれません。
「障害があることの大変さ」を知っているからこそ、
「自分の子どもには同じ思いをさせたくない」
「自分たちが育てていけるだろうか」
と、不安になるのは当然のことです。

もちろん、障害を持つ方を否定するつもりは一切ありません。
しかし、我が子の将来、そして家族の未来を真剣に考えたとき、
「もし障害のある子が生まれたら、育てていく自信がない」
と感じてしまう気持ちも、決して責められるべきではありません。
「健常児が欲しい」私たち夫婦もそう願った日々
私たちには、発達障害の長女、定型発達の二女、そして三女がいます。
三女を妊娠した当時、長女の育児は相変わらず手がかかり、二女もまだ幼く、目が離せない時期でした。
そこに3人目が加わることになり、もしその子が重い障害を持って生まれてきたら……
正直なところ、私たち夫婦だけでは育てていく自信がありませんでした。
決して障害のある子を否定するわけではありません。
ただ、当時の長女、二女、そして妻……家族みんなのことを真剣に考えた結果、
「今回の妊娠に関しては、もし重い障害があった場合、今の私たち家族では支えきれないかもしれない」
そう判断したんです。
具体的な対策は?
私たち夫婦は、二女(健常児)・三女の妊活・妊娠中に以下のようなことに取り組みました。
- 健康的な生活を送る
- 葉酸サプリを活用する
⇒おすすめ「【BELTA】厚生労働省推奨の葉酸サプリ」「【makana(マカナ)】」 - NIPT(新型出生前診断)を受ける
⇒おすすめ「平石こどもクリニック」 - 臍帯血を保管する
>>【実体験】臍帯血は保管しないと後悔する?|保管すべき理由
詳細は後述しますが、以下の動画でもポイントをまとめています。
障害児が生まれる確率と原因

では、実際に障害のある子どもが生まれる確率はどのくらいなのでしょうか。
統計*によれば、何らかの先天性疾患を持って生まれる子どもの割合は約3~5%とされています。
これは20~30人に1人という計算になり、決して他人事ではない数字です。
(*参考:日本産婦人科医会 先天異常, 難病情報センター)
障害の原因は様々で、完全に解明されていないことも多くあります。
以下、主な要因をまとめました。
- 遺伝的要因:
親から子へ受け継がれる遺伝子の変化によるもの。 - 染色体異常:
ダウン症候群(21トリソミー)など、染色体の数や構造に変化があるもの。
母親の年齢上昇と関連する一部の染色体異常もあります。 - 環境要因:
妊娠中の感染症(風疹、サイトメガロウイルス等)、特定の薬剤、放射線、母体の病気(糖尿病等)、栄養状態など。 - 原因不明:
上記のいずれにも当てはまらず、原因が特定できない場合も少なくありません。
特に発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)は、多くの要因が複雑に関与すると考えられています。

大切なのは、障害は「誰のせいでもない」ということです。
「これをすれば絶対に防げる」という単純なものでもありません。
不安を感じるのは自然ですが、ご自身やパートナーを責める必要は全くありません。
もし障害のある子が生まれたら?【具体的なステップと支援】

どんなに「健常児が欲しい」と願っても、障害のある子どもが生まれてくる可能性は誰にでもあります。
もしその現実に直面したら、どうすればよいのか。
パニックになったり、将来を悲観したりしてしまうかもしれません。
私たち夫婦も、長女の診断がついた日は強いショックを受け、涙が止まりませんでした。
でも、絶望しているだけでは何も始まりません。
ここからは、障害のある子どもの誕生という現実と向き合い、前へ進むための具体的なステップと、利用できるサポートについて解説します。
1. 診断を受けた直後の心構えと行動【親御さんへ】
「まさか自分の子どもが……」
告知を受けた直後は、頭が真っ白になり、何も考えられなくなるかもしれません。
悲しみ、怒り、戸惑い、罪悪感……様々な感情が押し寄せるでしょう。
感情を受け止める
どんな感情も否定せず、まずは受け止めましょう。
泣きたいときは思い切り泣いてください。
パートナーと気持ちを共有することも大切です。
私たち夫婦も、たくさん泣きました。
でも、二人で支え合い、「前を向くしかない」と少しずつ気持ちを切り替えていきました。
正確な情報を集める
不安は、情報不足から増大します。
医師や専門家から、子どもの状態、考えられる障害(ダウン症、自閉症、脳性麻痺など)、今後の見通しについて、正確な説明を受けましょう。
わからないことは遠慮なく質問してください。
インターネットの情報は玉石混交なので、信頼できる情報源を見極めることが重要です。
一人で抱え込まない
信頼できる家族や友人に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。
また、後述する相談窓口や、同じ境遇の親の会(ピアサポート)など、頼れる場所はたくさんあります。
完璧を目指さない
すぐにすべてを受け入れ、完璧な親になろうとしなくて大丈夫です。
ゆっくり時間をかけて、子どもと、そして自分自身の気持ちと向き合っていきましょう。

診断を受け止めるのはもちろん辛かったですし、
夫として、妻の悲しむ顔を見るのも辛かったです。
でも、父親として、家族を守らなければならない。
そう思って、必死で情報を集め、妻を支え、療育にも積極的に関わるようになりました。
つい一人で抱え込みがちですが、ぜひパートナーと協力し、弱音も吐きながら、一緒に乗り越えていってほしいです。

2. 利用できる公的支援・制度【申請方法・相談窓口】
障害のある子どもを育てる家庭には、様々な公的支援が用意されています。
これらを活用することで、経済的・精神的な負担を大きく軽減できます。
知らないと損をしてしまう制度ばかりなので、必ずチェックしましょう。

まずは、お住まいの地域の相談窓口(保健センターや市町村の障害福祉課など)に連絡してみるのが第一歩です。
どんな支援があるか、どう手続きすればよいか、丁寧に教えてくれます。
主な支援制度・相談窓口
以下に代表的な支援制度をまとめましたが、詳細や名称は自治体によって異なる場合があります。
- 経済的支援
- 特別児童扶養手当:
障害のある20歳未満の子どもを育てている保護者向け。(所得制限あり) - 障害児福祉手当:
重度の障害があり、常時介護が必要な20歳未満の子ども向け。(所得制限あり) - 医療費助成:
小児慢性特定疾病医療費助成、自立支援医療など、治療にかかる医療費の自己負担を軽減する制度。
- 特別児童扶養手当:
- 各種手帳(サービスの利用や割引に)
- 療育手帳(愛の手帳など):
知的障害があると判定された場合に交付。 - 精神障害者保健福祉手帳:
発達障害を含む精神疾患がある場合に交付。
- 療育手帳(愛の手帳など):
- 療育・教育支援
- 児童発達支援・放課後等デイサービス:
未就学児や学齢期の障害児が通う施設。
日常生活や集団生活への適応訓練などを受けられる。
利用料の大部分は公費負担。 - 保育所等訪問支援:
専門スタッフが保育園や幼稚園を訪問し、集団生活をサポート。 - 特別支援教育:
特別支援学校や小中学校の特別支援学級で、障害の状態に応じた教育を提供。
- 児童発達支援・放課後等デイサービス:
- 相談窓口
- 保健センター・子育て世代包括支援センター:
最も身近な相談窓口。
育児相談、情報提供、関係機関への紹介など。 - 児童相談所:
児童福祉に関する専門機関。療育手帳の判定なども行う。 - 発達障害者支援センター:
発達障害に関する専門的な相談支援。 - 相談支援事業所:
障害福祉サービスの利用計画(サービス等利用計画)作成などをサポート。
- 保健センター・子育て世代包括支援センター:
申請・利用のポイント
- まずは相談しましょう
どこに何を申請すればよいかわからない場合、まずは地域の保健センターや市町村の障害福祉担当課に相談しましょう。 - 早めに行動しましょう
手当やサービスには申請が必要で、認定までに時間がかかる場合もあります。
診断を受けたら、早めに情報収集と申請準備を始めましょう。 - 必要な書類は?
申請には医師の診断書や意見書が必要になることが多いです。
主治医に相談し、準備を進めましょう。 - 諦めないで活用しましょう
手続きが複雑に感じるかもしれませんが、相談窓口の担当者や相談支援専門員がサポートしてくれます。
使える制度は遠慮なく活用しましょう。
3. 地域による違いと情報収集のコツ
支援制度や相談窓口の名称、具体的なサービス内容は、お住まいの自治体によって異なる場合があります。
以下、確認しておきましょう。
- 自治体のウェブサイトを確認:
まずは、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトで「障害福祉」「子育て支援」などのキーワードで検索してみましょう。 - 広報誌や窓口で確認:
自治体の広報誌にも情報が掲載されていることがあります。
直接、担当窓口に問い合わせるのが確実です。 - 地域の「生きた情報」:
同じ地域で子育てをする先輩ママ・パパからの情報は非常に役立ちます。
地域の親の会や支援団体、SNSコミュニティなども探してみましょう。
4. 家族(夫婦間、きょうだい児、祖父母)との関わり方とサポート
障害のある子どもの育児は、並大抵のことではありません。
家族・親戚みんなの力で乗り越えていきましょう。
夫婦間のコミュニケーション
最も重要な土台です。
お互いの気持ちを正直に話し合い、育児や家事の分担、将来の不安などを協力して決めましょう。
どちらか一方に負担が偏らないように、意識的にコミュニケーションをとることが大切です。
きょうだい児へのケア
障害のある兄弟姉妹がいる子ども(きょうだい児)は、寂しさや我慢、親の注目が自分に向かないことへの葛藤などを抱えることがあります。

我が家の場合、長女(障害児)の存在が、二女(健常児)にとって「特別なこと」ではなく「当たり前の日常」になるよう意識しています。
大変な面も含めて、それが我が家の形なのだと、日々の関わりの中で自然に伝えていきたいと思っています。
同時に、きょうだい児自身が「自分も大切にされている」と感じられるよう、意識して一人ひとりと向き合う時間を作ることも重要だと感じています。

祖父母との連携
祖父母は心強いサポーターですが、障害に対する理解や価値観が異なる場合もあります。
子どもの状態や親の方針(療育方針など)を丁寧に伝え、理解と協力を求めましょう。
頼れる部分は感謝して甘え、一方で過度な干渉や価値観の押し付けには、やんわりと境界線を引く勇気も必要です。
親自身のケア
家族みんなが笑顔でいるためには、親自身の心身の健康が不可欠。
レスパイトケア(一時預かり)などを利用して休息をとったり、自分の時間を持ったりすることも大切です。
5. 先輩パパ・ママの声【体験談・乗り越え方】
「この状況、乗り越えられるんだろうか……」
そんな風に感じたとき、同じ経験をした先輩たちの言葉は、大きな励みになります。
私たち夫婦も、たくさんの先輩家族に助けられてきました。
SNSやブログ、地域の親の会などで、様々な家族のストーリーに触れてみてください。
共感できる悩みや、具体的な工夫、そして「大変だけど、幸せもある」というリアルな声に、きっと勇気づけられるはずです。

手軽に始められる情報交換の場として、無料のオンラインコミュニティ「ふぉぴす」もおすすめです。
LINEの友達登録だけで、先輩ママ・パパや専門家に発達の不安や困りごとを無料で気軽に相談できますよ。
6. 長期的な視点(教育、就労、親なきあと)
子どもの成長は嬉しいものですが、同時に新たな課題も出てきます。
少し気が早いと感じるかもしれませんが、将来を見据えて、長期的な視点を持つことも大切です。
- 教育:
通常学級、特別支援学級、特別支援学校など、子どもの特性に合った学びの場を選択します。
進路については、学校や専門機関と早くから相談を始めましょう。 - 就労:
一般就労、障害者雇用、福祉的就労(就労継続支援A型・B型など)といった選択肢があります。
ハローワークや就労支援機関がサポートしてくれます。 - 親なきあと:
親が亡くなった後や、高齢になって子どもの世話ができなくなった場合に備え、成年後見制度の利用、グループホームなどの入居、財産管理の方法などを検討しておく必要があります。

すぐに答えが出る問題ではありません。
でも、「いつか考えなければ」ではなく、「今のうちから少しずつ情報を集めておく」という意識が大切です。
相談支援専門員さんなどが力になってくれます。
妊娠中にできること【後悔しないための具体的な選択肢】

ここまで、もし障害のある子が生まれた場合の対応についてお伝えしてきました。
ここからは、「妊活中」「妊娠中」に戻し、不安を少しでも減らすためにできること、具体的な選択肢について見ていきましょう。
「できることなら、障害のリスクを少しでも減らしたい」
「生まれる前に、赤ちゃんの状態を知ることはできないの?」
そう考える方のために、私たち夫婦が実践したことや、検討した選択肢は次の4つです。
- 1.健康的な生活を送る
- 2.葉酸サプリを活用する
⇒おすすめ「【BELTA】厚生労働省推奨の葉酸サプリ」「【makana(マカナ)】」 - 3.NIPT(新型出生前診断)を受ける
⇒おすすめ「平石こどもクリニック」 - 4.臍帯血を保管する
>>【実体験】臍帯血は保管しないと後悔する?|保管すべき理由
それぞれ、詳しく紹介します。
1. 健康的な生活を送る【基本だけど大切】
様々な要因があるとはいえ、「妊娠前や妊娠中の母体(と父親)の健康状態」が、赤ちゃんの健やかな発育に関係する可能性は指摘されています。
*参考書籍:『薬に頼らず家庭で治せる発達障害とのつき合い方』
当たり前のことのようですが、健康的な生活は、お腹の赤ちゃんにとっても、ママ自身にとってもすべての基本となります。
以下、ポイントをまとめました。
- バランスの取れた食事:
特定の食品で障害を防げるわけではありませんが、母体の健康を保つことが大切です。
特に、葉酸、鉄分、カルシウム、ビタミンDなどを意識して摂取しましょう。 - 適度な運動:
無理のない範囲でウォーキングやマタニティ向けの運動を取り入れ、体力維持とストレス解消に努めましょう。 - 十分な休息と睡眠:
ストレスを溜めず、心身をリラックスさせることが、母体と胎児の健康につながります。 - 禁煙・禁酒:
喫煙やアルコール摂取は、胎児の発育に悪影響を与えるリスクを高めます。
妊娠がわかったら(できれば妊活中から)きっぱりやめましょう。
受動喫煙にも注意が必要です。 - 感染症予防:
手洗い、うがいを徹底し、人混みを避けるなど、基本的な感染症対策を心がけましょう。
(特に妊娠初期の風疹感染などは注意が必要です)

正直に告白すると……長女(障害児)の妊娠中、私たちは不健康でした。
夫婦ともに仕事が忙しく、食生活は乱れ、ストレスもMAX(ファストフードやコンビニ飯も日常茶飯事……)。
その反省から、二女(健常児)・三女の時は、できる範囲で健康的な生活を心がけました。
これが直接関係したかはわかりませんが、
「あのときできることをやっておけば…」
という後悔をしないためにも、基本は大切だと思います。

2. 葉酸サプリを活用する
葉酸は、赤ちゃんの脳や神経を作る上で非常に重要な栄養素です。
特に妊娠初期の摂取が大切で、神経管閉鎖障害(二分脊椎など)という先天性異常のリスクを低減することが科学的に証明されています。

また、いくつかの研究では、葉酸の摂取が自閉症スペクトラム障害のリスクを低減する可能性も示唆されています。
*参考:水上尚典(2009)葉酸摂取のすすめ, 国際オーソモレキュラー医学会ニュース
葉酸は緑黄色野菜やレバーなどに多く含まれますが、食事だけで十分な量を摂取するのは難しい場合も。
そのため、厚生労働省も、妊娠を計画している女性や妊娠初期の女性に対し、通常の食事に加えてサプリメント等で1日400μg(0.4mg)の葉酸を摂取することを推奨しています。
「知らなかった」「飲んでおけばよかった」と後悔しないためにも、葉酸サプリの活用は強くおすすめします。
私たち夫婦も、二女・三女の妊活・妊娠中は、意識して葉酸サプリを摂取しました。
ベルタ葉酸サプリ【妻が飲んでいたもの】

厚生労働省推奨の「モノグルタミン酸型酵母葉酸」480㎍をはじめ、鉄・亜鉛・ビタミンD・ビタミンB6など、妊娠・妊活中に必要な栄養素をバランスよく配合。無添加なのも安心です。
さらに、コラーゲン・ヒアルロン酸などの美容成分も入っています。
通常5,980円のところ、初回は1,980円の低価格で購入可能。定期購入なら2回目以降も33%オフです。
\公式HPで初回割引をチェック!/
【7年連続売上No.1!まずは試してみて】
また、私(夫)も二女(健常児)・三女の妊活中には葉酸サプリを摂取することにし、次に紹介する【makana(マカナ)】を飲んでいました。
makana(マカナ)【私(夫)が飲んでいたもの】

葉酸をはじめ、ビタミンB群やビタミンE、ビタミンCなどの身体に必要なビタミン類を豊富に配合。
鉄や亜鉛など、普段の食事では不足しがちなミネラル類も豊富。
それでいて無添加というのもポイント。
さらに、男性の妊活サポート成分として注目される「マカ」を高配合しているのが特徴です。
「妊活は夫婦で取り組むもの」という考えから、私もこちらを飲んでいました。
男性も葉酸や亜鉛などを摂取することは、元気な赤ちゃんを迎えるために大切だと考えています。
\公式HPはこちら/
【初回は40%オフで購入可能】

長女のときは、妻は妊娠してから葉酸を飲み始め、私は飲んでいませんでした。。
今となっては、「もっと早くから、夫婦でしっかり取り組んでいれば、何か違ったかもしれない」と感じることもあります。
葉酸サプリは、妊活を考え始めたらすぐに、できれば夫婦で飲むことを強く、強くおすすめします。
月数千円でできる、未来への投資です。
今思えば、もっと早く、夫婦で取り組んでいれば……
と感じることもあります。

3. NIPT(新型出生前診断)を受ける【不安解消の選択肢】
「生まれる前に、赤ちゃんの染色体異常のリスクを知りたい」
そう考える方のために、出生前診断(出生前検査)という選択肢があります。
様々な種類がありますが、母体への負担が少なく高精度な検査として注目されているのがNIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)です。
NIPTとは?
妊婦さんの血液を少量採取し、血液中に含まれる胎児由来のDNA断片を分析することで、胎児の特定の染色体異常(ダウン症[21トリソミー]、18トリソミー、13トリソミーなど)のリスクを調べる検査です。
メリット
- 非侵襲的である:
採血のみで行うため、羊水検査や絨毛検査のように流産・死産のリスクが極めて低い。 - 高精度の検査:
対象となる3つのトリソミーに対する精度は非常に高い(約99%)とされています。 - 早期に実施可能:
一般的に妊娠10週頃から検査可能です。
デメリット・注意点
- 確定診断ではない:
NIPTはあくまで「リスクが高いか低いか」を調べるスクリーニング検査。
陽性の場合、診断を確定するためには羊水検査などの確定診断(侵襲的検査)が必要。 - 検査項目が限られる:
基本的なNIPTでわかるのは主に3つのトリソミー。
他の疾患(発達障害含む)は対象外(施設にもよる)。 - 費用がかかる:
健康保険が適用されず、自費診療。
一般的に10~20万円程度かかる。 - 倫理的な問題:
結果次第で非常に重い決断を迫られる可能性。
検査前の十分な情報収集、夫婦での話し合い、遺伝カウンセリングが不可欠。
私たち夫婦のNIPT体験
三女の妊娠時、私たちはNIPTを受けることに決めました。
理由は、前述の通り「当時の家族状況では、重い障害のある子を育てる余裕がない」と考えていたこと。
そして「もし体が健康で生まれてきてくれるなら、たとえ発達障害があったとしても、療育でサポートしていける」と考えたからです。

確かに、NIPTでは長女のような発達障害のリスクまではわかりません。それでも私たちが受けたのは、「まず、命に関わるような重い疾患がないかを知ることで、漠然とした不安を少しでも減らしたい」という思いからでした。
「体さえ元気であれば、未来への希望が持てる」
そう考えたんです。
NIPTを受けるにあたり、様々なクリニックを比較検討した結果、サポート体制や利便性から平石こどもクリニックを選びました。

NIPT 平石こどもクリニック

検査は1回の来院で完了。
通常、検査結果が陽性だった場合はその後羊水検査を受けることになりますが、その費用を全額負担してもらえるのも魅力です。
年齢制限もなく、早期NIPTに対応(妊娠6週から検査可能)。
全国に提携クリニックがあるのも強みです。
NIPTの費用は決して安くはありません。
しかし、「もし障害があったら……」という不安を抱えながら妊娠期間を過ごす精神的な負担。
実際に障害のある子を育てる将来的な経済的負担。
それらを考えれば、安心を得るための投資として、決して高すぎるとは思いませんでした。

「障害児は産みたくない」
「できることは全部やっておきたい」
そうお考えのご夫婦にとって、NIPTは真剣に検討すべき選択肢だと、私たちは考えます。
ただし、NIPTは一般的に妊娠18週頃までに受けることが推奨されています。
もし検討される場合は、できるだけ早く情報収集を始め、夫婦で話し合い、クリニックへの相談を検討してみてください。
Webから簡単に予約や相談ができます。
\「不安」を「安心」に変える選択肢/
NIPTを受けるかどうかの判断
NIPTは、結果次第では非常に重い決断を迫られることもあります。
なぜ検査を受けたいのか、陽性だったらどうするのか。
ご夫婦で納得いくまで話し合いましょう。
また、遺伝カウンセリングの活用も必須です。
専門家である遺伝カウンセラーに相談することで、検査への理解を深め、夫婦の意思決定をサポートしてもらえます。

私たち夫婦がNIPTを受けると決めるまでの葛藤や、他のクリニックとの比較については、以下の記事で詳しく紹介しています。
>>出生前診断を受けなかったら後悔する?【NIPT体験談と後悔しない選択】
4. 臍帯血を保管する【未来への希望をつなぐ】
これは出産時の選択になりますが、「臍帯血保管」も、将来のお子さんの健康リスクに備えるための重要な選択肢の一つです。
臍帯血とは?
出産時に、赤ちゃんと胎盤をつなぐ「へその緒(臍帯)」や胎盤の中に流れている血液のこと。
この血液には、「幹細胞」という、体の様々な細胞のもとになる特殊な細胞が豊富に含まれています。
なぜ保管するのか?【臍帯血の可能性とは?】
将来、赤ちゃん本人や家族(兄弟姉妹など)が、白血病などの血液疾患、免疫不全、代謝異常、あるいは脳性麻痺や自閉症スペクトラム障害などの神経系疾患にかかった場合に、治療に役立つ可能性があるからです。
臍帯血移植は、骨髄移植と同様に、病気の治療法の一つとして確立されています。
また、近年では再生医療への応用も期待され、研究が進められているんです。
臍帯血は出産時にしか採取できない貴重なもの。
私たち夫婦は、二女と三女の出産時に、民間バンクでの臍帯血保管を選択しました。
「もしものときの備え」、そして「未来の医療への希望」として、家族の大きな安心材料になっています。
保管には費用がかかりますが、将来、お子さんや家族を救う可能性がある「命の保険」と考えると、その価値は計り知れません。
私たち夫婦は、「あのとき、保管しておけばよかった…」と後悔する可能性を考え、保管を決断しました。
臍帯血保管について、私たちの実体験や、公的バンクと民間バンクの違い、費用の詳細などは、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ一度、目を通してみてください。

>>【実体験】臍帯血を保管せず、本当に後悔しない? 自閉症児を持つ親が語る「保管すべき理由」
まとめ【できることから始めましょう】
「障害児が生まれたらどうしよう……」
その不安は、痛いほどよくわかります。
そして、その気持ちを抱えることは、決して悪いことではありません。
障害のある子を育てるのは、簡単ではありません。
私たち夫婦も、日々悩み、奮闘しています。
でも、絶望だけではありません。
そこには、想像もしなかった喜びや、深い愛情、そして子どもの成長という、かけがえのない希望があります。

長女は重度知的障害を伴う自閉症です。
でも2歳から療育を続けてきたことで、彼女なりに着実に成長してくれています。
言葉はなくても、意思表示ができるようになったり、身の回りのことが少しずつできるようになったり。
その一つ一つの成長が、私たち夫婦にとって何よりの喜びであり、希望です。
早期から適切なサポートを受ければ、子どもはその子なりに伸びていきます。

この記事では、「障害児が生まれたらどうしよう」という不安に対し、妊娠中にできる備えから、実際に生まれた後のステップ、利用できる支援まで、幅広くお伝えしてきました。。
もし、あなたが今、妊娠中で不安を感じているなら:
- まずは、健康的な生活を心がけましょう。
- 葉酸サプリの活用を検討しましょう。
- 出生前診断(NIPTなど)や臍帯血保管について、夫婦でよく話し合い、検討しましょう。
もし、あなたがすでにお子さんの障害と向き合っているなら:
- 一人で抱え込まず、利用できる公的支援や相談窓口を積極的に活用しましょう。
- 正確な情報を集め、子どもの特性に合ったサポート(療育など)を考えましょう。
- 家族や親戚と協力し、チームで子育てに取り組みましょう。
- そして、あなた自身の心と体のケアも忘れないでください。
どちらの状況であっても、大切なのは「正しい情報を知り、一人で悩まず、行動すること」です。
どんな状況であっても、道は必ずあります。
ご夫婦、ご家族でよく話し合い、皆さんにとって最善の道を選んでいってください。
最後に、この記事で紹介した主な選択肢やサービスをまとめておきます。
- ベルタ葉酸サプリ:
おすすめ、定番の葉酸サプリ。まずはこちらを検討してみることをおすすめします。
*公式HPはこちら⇒【BELTA】厚生労働省推奨の葉酸サプリ - makana(マカナ):
男性にもおすすめの葉酸サプリ。ご夫婦で飲む場合は、旦那さんはこちらがおすすめです。
*公式HPはこちら⇒【makana(マカナ)】 - NIPT平石こどもクリニック:
「障害児が生まれたらどうしよう……」という不安を解消するうえではとても有効な選択肢です。妊娠中(~18週)の方は、前向きに検討してみてください。
*公式サイトはこちら⇒平石こどもクリニックのNIPT - 臍帯血の保管:
自閉症や脳性麻痺など、現在治療法のない病気に備えることができます。
*詳細はこちら>>【実体験】臍帯血は保管しないと後悔する?|保管すべき理由
この記事が、あなたの不安を少しでも希望に変えるきっかけとなれば、心から嬉しく思います。