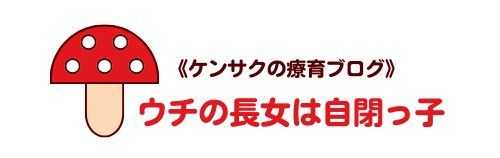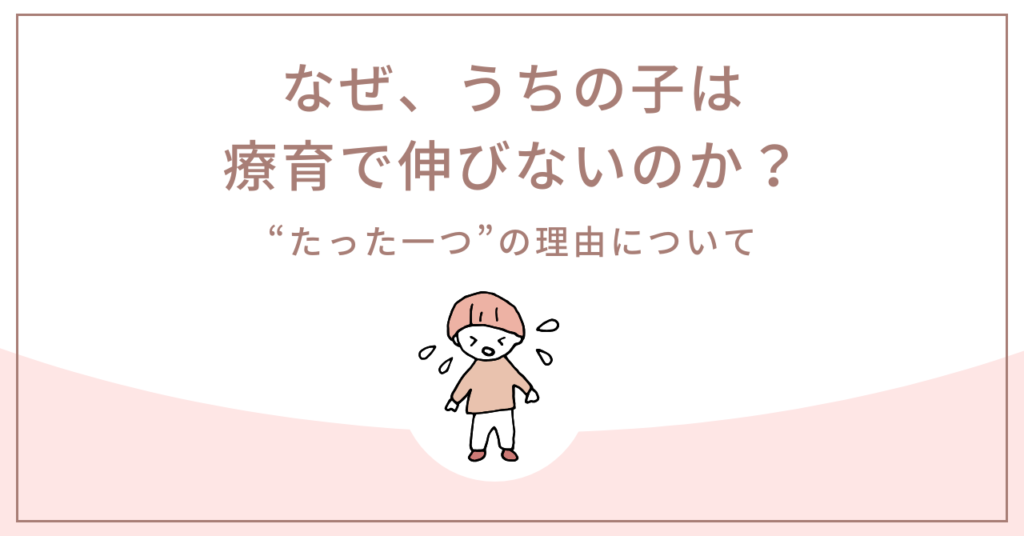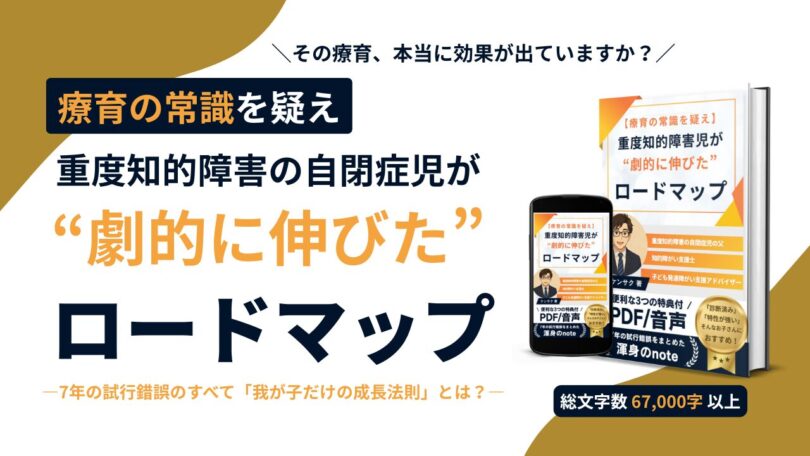「療育に通うかどうか迷っている……基準があれば知りたい」という親御さんへ。結論、療育に通う基準は明確にはありません。しかし、一般的な基準や、私の娘が早い時期から療育に通った経験から「こういう傾向があるなら通ったほうがよさそう」ということはお伝えできますので、ぜひ参考にしてください。
- 療育に通う基準
- 療育に通う方法
- 療育の選び方
このブログ記事を読めば、お子さんが療育に通うべきかどうかの基準がわかります。療育の通い方などについても紹介しますので、参考にしてください!

目次
療育に通う基準は?
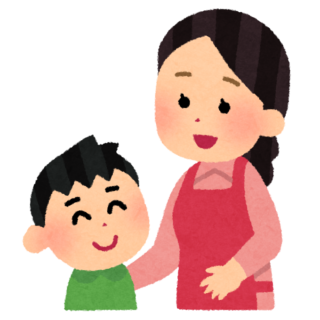
療育の通う基準は明確にはありませんが、まずは発達検査を受けるのが一般的です。主な発達検査には、以下のようなものがあります。
- 新版K式発達検査:
乳幼児期の発達を総合的に評価する検査 - WISC-IV知能検査:
6歳から16歳11ヶ月までの子どもの知的能力を測定する検査 - 田中ビネー知能検査:
幼児から成人までの知能を測定する検査
これらの検査では、子どもの発達年齢や知能指数などを測定し、同年齢の子どもと比較することで、発達の遅れや偏りの程度を客観的に把握。検査結果に基づき、医師や専門家が療育の必要性を判断します。

たとえば、発達年齢が著しく遅れている場合や、特定の領域に著しい偏りが見られる場合などは、療育が必要と判断されることがあります。
娘が療育に通うことになったきっかけ
冒頭でお伝えしたとおり、療育に通う基準は明確にはありません。発達障害の診断が出ているから通わせる、出ていないから通わせない、といったこともありません。
また、お子さんが現在何歳なのかにもよりますが、ここでは私の娘(知的障害を伴う自閉症)の例をご紹介します。

娘が療育に通い始めたのは2歳から。娘の場合、すでに1歳前後の時点で成長が遅く、まわりの子と比べてできないことが多い状況でした。具体的には、次のような傾向が見られました。
- 指差しをしない
- 発語がない
- 名前を呼んでも振り向かない
- 癇癪が多い
- じっとしていられない
こういう状況でしたので、当然1歳半検診のときに引っかかりました。。前述したように、検診の前の時点で成長が遅いのはわかっており、不安に感じていた私たち夫婦は、その後自治体の発達相談へ。結果、自治体の療育をおすすめされました。
自治体の療育へ
おすすめされたこともあり、2歳からは週1回、自治体の療育(言語療法[ST]や作業療法[OT])に通うことにしました。このときの様子や早期療育の効果などは以下の記事で紹介していますので、詳しく知りたい方はご覧ください。
おそらく、発達相談で「不安に感じている」「心配」ということを強く言わなければ、「とりあえずもう少し様子を見ましょう」で終わっていたと思います。。上記の記事のように、2歳からの療育でも確かな成長が見られたので、本当にはっきり言っておいてよかったと思っています。

もし、お子さんが1~2歳で成長に不安を感じている場合は、早めに自治体の窓口に相談してみましょう。2~3歳以降であれば、次項で紹介する児童発達支援の検討をすすめるのもおすすめです。
娘のように「指差ししない」「発語がない」などの傾向があるなら絶対、とは言えませんが、1つの参考にはなるはずです。
繰り返しになりますが、療育に通う基準はなくても、親御さんが違和感を感じていたり迷っているのであれば、すぐに検討してみることをおすすめします。
療育に通うには?

通所受給者証の取得
おそらくこの記事をご覧の親御さんは、娘のように自治体の療育というより、障害児通所支援の1つである「児童発達支援」を検討されている方が多いのではないでしょうか。
娘の場合も、3歳からは児童発達支援に通うようになりました。その場合、必要となるのが「通所受給者証」です。受給者証を使用することで、施設を1割負担で利用できるようになります。
受給者証は、住んでいる市区町村から交付されます。取得するには以下の手順を踏みます。
- 自治体の窓口で手続き相談をする
- 障害児支援利用計画(案)を作成する
- 障害児支援利用計画(案)の提出
- 審査 → 受給者証の交付
以下、もう少し具体的に見ていきましょう。
1.自治体の窓口で手続き相談をする
- 子育て総合支援センターや役所の保健福祉課などで、利用したいサービスの内容や計画の説明を聞きます。
- 申請書類を記入し、必要に応じて添付書類(障害者手帳や医師の診断書など)を準備します。
- 聞き取りや面接が行われる場合があります。
2.障害児支援利用計画(案)を作成する
- 利用したいサービスの種類や時間、目的などを記入します。
- 利用を検討している施設と相談しながら作成することができます。
3.障害児支援利用計画(案)の提出
- 前項で作成した利用計画(案)と申請書類を自治体に提出します。
4.審査 → 受給者証の交付
- 提出された資料や利用計画(案)に基づいて審査が行われます。
- 審査結果によっては、内容の変更や追加資料の提出を求められる場合があります。
- 審査が通れば、受給者証が交付されます。
児童発達支援(療育)の選び方

では、児童発達支援(療育)はどのように選べばよいのでしょうか。大きくは次の2つです。
- 個別指導か集団指導か
- 子どもの特性に合った体制かどうか
個別指導か集団指導か
児童発達支援には大きく、個別指導と集団指導の2つのタイプがあります。
個別指導はその名の通り、子ども一人ひとりの発達状況や目標に合わせて、支援員が個別に指導します。たとえば、言語聴覚士による言語訓練、作業療法士による運動機能や日常生活動作の訓練などが挙げられます。
集団指導は、数人のグループで活動したり遊んだりします。たとえば、リズム遊びや手遊び、絵本や紙芝居の読み聞かせ、工作やお絵かきなどを行います。

お子さんの普段の様子や、「このスキルを伸ばしたい」などの観点から、どちらがよいかを考えてみましょう。娘の場合は他者とのコミュニケーションや集団行動が苦手だったので、まずは集団指導から。その後、言語なども伸ばしていきたいと思い、個別指導にも通うようになりました。
子どもの特性に合った体制かどうか
前述したように、お子さんが苦手としているのはどのようなことか、または伸ばしていきたいのはどういったスキルなのか、事前に判断したうえで療育を選ぶ必要があります。
その際に重要なのが、療育の体制。たとえば、「言葉の遅れについて相談したいけど言語聴覚士の先生がいない」「歩き方が悪いので相談したいけど作業療法士の先生がいない」といった具合です。
事前にHPを確認したり資料請求してみたり、見学・体験などを通してじっくり選ぶことをおすすめします。

「具体的にどんな児童発達支援(療育)があるの?」という方は、以下の記事を参考にしてください。
まとめ
療育に通う基準は明確にはありません。しかし、もし迷っているのであれば早めに療育に通うことをおすすめします。
療育は早ければ早いほど効果が高まります。娘も2歳から療育を受け、結果的には知的障害を伴う自閉症であったものの、だいぶコミュニケーションが取れるようになり、確かな成長が見られています。
近くの児童発達支援など、検討する際はお子さんの性格や特性を十分に考えたうえで、どこに通うかを検討してみてください。
今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。