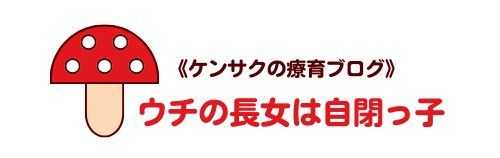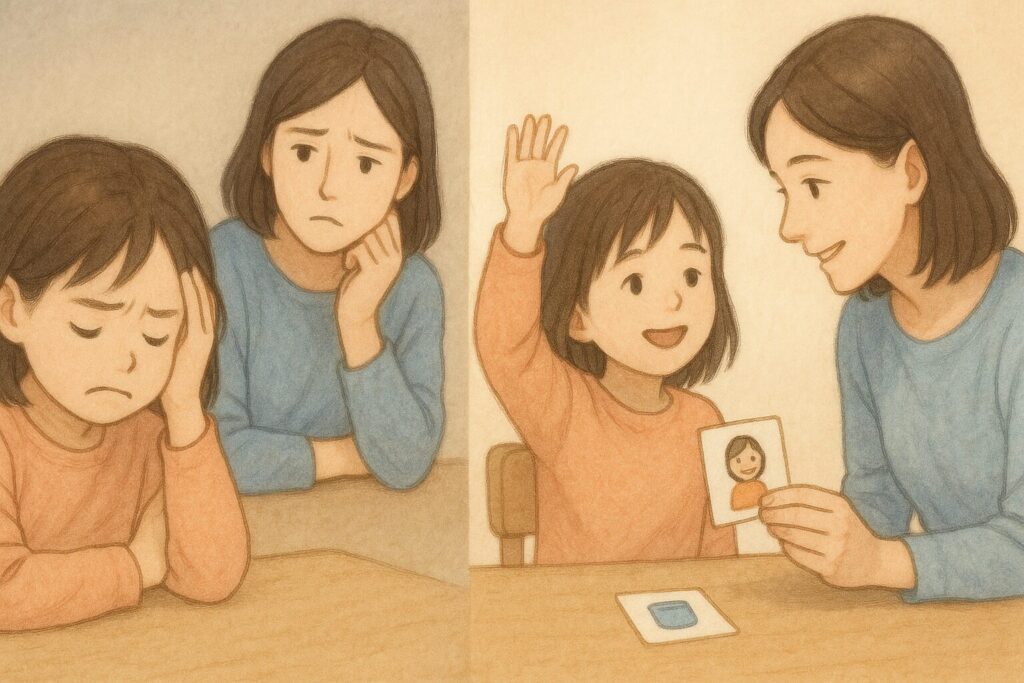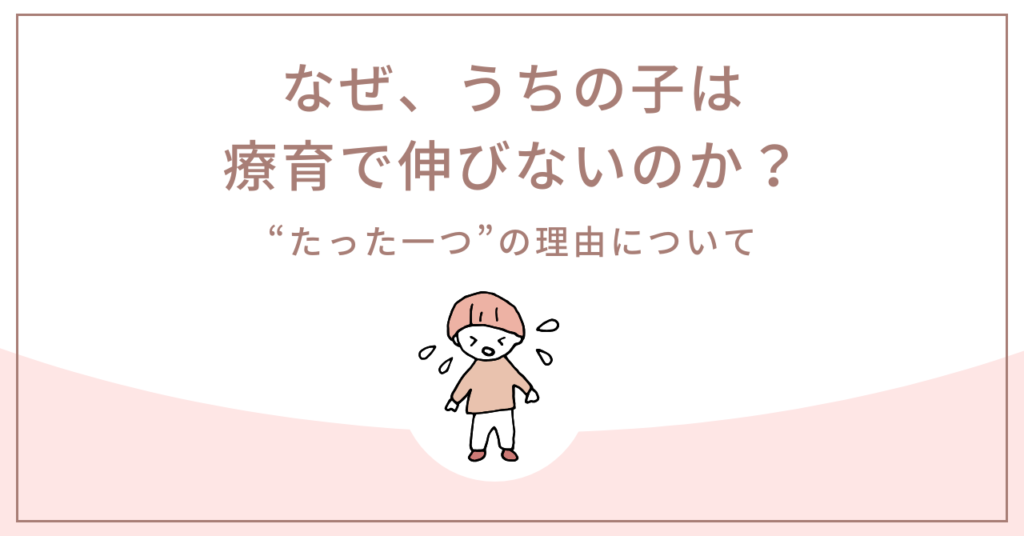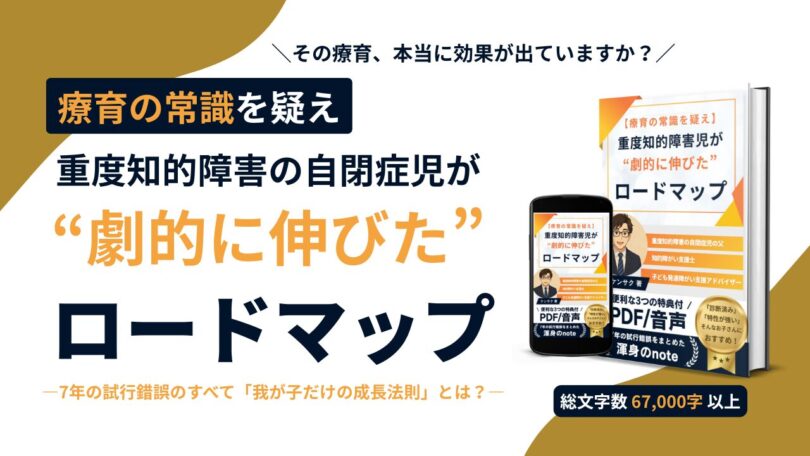「療育は意味がないのでは……」
そう不安になったことはありませんか?
子どもの発達に悩み、わらにもすがる思いで療育に通い始めたものの、目に見えた成果がなかなか出ない。
「本当にこの時間とお金に効果があるの?」と疑問を抱いてしまう。
そんな親御さんは、決して少なくありません。
「うちの子には必要ないのかも」
「ママ友は、通っても意味がなかったって言ってたし」
と、周囲の声やSNSの情報に心が揺れることもあるでしょう。
何を隠そう、私自身もかつては「療育は意味がないのかもしれない」と、何度も諦めかけた親の一人です。
このブログ記事は、自閉症の娘を2歳の頃から自治体の療育、そして民間の児童発達支援へと通わせてきた私の“本音”の体験談をもとにしています。
なぜ「意味がない」と感じてしまったのか、そして最終的に「何ものにも代えがたい、絶対に必要な時間だった」と心から思えた理由を、包み隠さずお話しします。
- 「療育は意味がない」と感じてしまう理由
- 療育の効果、療育の代替手段
- 療育を続けてよかったと思ったわけ
もし、あなたが「通っているのに効果が感じられない」「うちの子には合っていない気がする」「もう辞めたほうがいいのかも」と悩まれているなら、どうか最後まで読んでみてください。きっと参考になるはずです!

※本記事はプロモーションを含みます。
目次
療育は意味がない? 通った親の本音は「必要」

「療育に通っても変化がない」
「周りの子と比べて不安になる」
「効果があるのか分からない」
そんな悩みを抱えていませんか?
かつて私自身も同じように悩み、「療育は意味がないのでは」と心の中で何度もつぶやいたことがあります。
我が家も実際に通い始めた当初、娘の行動や話し方に目立った変化が見られず、期待していた効果が現れないことに落胆しました。
周囲の子が成長していくのを見ては「うちの子だけ何も変わらない」と感じ、通わせる意味を見失いそうになったんです。
しかし数ヶ月が経ち、ふとした瞬間に娘の表情が柔らかくなったり、「おいで」と呼んだら素直に寄ってきてくれたりする場面も増えてきました。
それは劇的な変化ではなく、小さくて気づきにくいものでしたが、明らかに以前とは違っていました。
「療育の意味は“結果”ではなく“過程”にもあるのかもしれない」と感じ始めたのはその頃からです。

通ったからこそ見えてきた、子どもの小さな変化と、その背景にある信頼関係の積み重ね。それが「療育は必要だった」と今でも感じている理由です。
次は、なぜ多くの親が「療育に意味がない」と感じてしまうのか、その背景を掘り下げていきます。
療育に「意味がない」と感じる理由とその背景

療育に通っている親御さんの多くが、一度は「これって、本当に意味があるのかな……」という壁にぶつかります。
私自身、出口の見えない不安に押しつぶされそうになったことは数え切れません。
その理由は、大きく3つに分けられると感じています。
- 効果が見えにくく、不安や焦りが募るから
- 子どもの特性と療育方法が合っていないと感じるから
- 周囲の声や情報に振り回され、自分の軸が揺らいでしまうから
これらの要因が複雑に絡み合うことで、「うちの子にとって療育は意味がないのかもしれない」という迷いが生まれると考えます。
でも、安心してください。
そう感じてしまうのには、ちゃんとした背景があります。
一つひとつ、私の経験も交えながら掘り下げていきましょう。
効果が見えにくいから焦りやすい
「こんなに頑張って通っているのに、どうしてうちの子は何も変わらないだろう?」
療育を始めてすぐの頃、私は毎日そう思っていました。
特に、2歳で自治体の集団療育に通い始めた当初、娘はまったく活動に参加できず、部屋の隅で一人でいるばかり。
周りのお友だちが楽しそうに先生と手遊びをしているのを見るたびに、胸がチクっと痛みました。
療育の効果は、風邪薬のようにすぐに効くものではありません。
特に発達に特性のある子どもの成長は、本当にゆっくり。
三歩進んで二歩下がることなんて日常茶飯事です。
だからこそ親は成果を実感しにくく、「療育なんて意味がないんじゃないか」という焦りを感じやすいんです。
でも、今振り返れば、あの頃の娘もちゃんと成長していました。
最初は泣いてばかりだったのが、泣かずにその場にいられるようになった。
それだけでも、彼女にとっては大きな一歩だったんです。
こうした小さな変化は、毎日一緒にいる親だからこそ見逃しがち。
でも、支援者の先生が「前はこうでしたけど、今はここまでできますよね!」とフィードバックをくれることで、ハッとさせられることが何度もありました。

成果は、ある日突然ではなく、薄紙を一枚ずつ重ねるように積み上がっていくもの。
そう知るだけでも、親の心はずいぶん楽になります。
子どもの特性や療育方法が合っていないケース
「うちの子、なんだか療育を楽しめていないかも……」
そう感じたら、それは「療育が意味がない」のではなく、「今のやり方が合っていない」というサインかもしれません。
たとえば、聴覚からの情報処理が苦手な子に、口頭での指示ばかりの集団療育は苦痛かもしれません。
逆に、一対一の緊張感が苦手な子もいます。
私の娘の場合、最初は自治体の集団療育からスタートしましたが、言葉の成長を促したいという目的が明確になってきた年中からは、個別指導に強みのある療育などを掛け持ちすることにしました。

すると、集団では見せなかった集中力を発揮。
先生との信頼関係の中で、まれにですが音声模倣が見られるようになったんです。
もしお子さんが療育を嫌がったり、通い始めてから癇癪が増えたりした場合は、一度立ち止まる勇気も必要です。
「集団から個別へ」「今の事業所は合わないから、別のところを見学してみる」など、柔軟に環境を見直してみましょう。
療育は、子どもが安心して「自分」を出せる場所であることが、何よりも大切ですから。
周囲の声や期待値に流されやすい親の心理
「Aちゃんのママは、あそこの療育は意味ないって言ってたよ」
「SNSで『療育やめたら、逆に落ち着いた』っていう投稿を見た」
発達に悩む親は、時に孤独です。
だからこそ、他の親の体験談やネットの情報に強く影響されてしまいます。

私も「本当にこのままでいいの?」と、何度も検索しては一喜一憂していました。
また、「療育に通わせているんだから、早く“普通”に近づけなくちゃ」という、無意識のプレッシャーも「療育は意味がない」と感じさせる一因です。
期待値が高すぎると、小さな成長に気づけず、「こんなものか」と失望してしまうんです。
一番大切なのは、「他の誰か」ではなく「我が子」を見ること。
他の家庭と比べるのをやめて、「昨日の我が子と比べて、今日は何ができたかな?」という視点を持つこと。
そう意識するだけで、周囲の声に振り回されず、心穏やかに子どもと向き合える時間が増えていきました。
【実体験】療育を続けたからこそ見えた景色と娘の成長

「療育なんて意味がないかも……」と悩みながらも、なぜ私たち親子は療育を続けたのか。
そして、その先にはどんな景色が待っていたのか。
ここでは、私たちが「辞めないでよかった」と思えた瞬間や家庭での工夫について、ありのままをお話しします。
「辞めないでよかった」と思えた、奇跡の瞬間
療育を続けていても、劇的な変化はなかなか訪れません。
でも、ある日突然、神様からのプレゼントのような瞬間がやってくることがあります。
それは、個別の療育(リタリコジュニア)に通い始めてしばらく経った日のこと。
それまで一度も意味のある言葉を発したことがなかった娘が、「みどり」という音声模倣をしたのです。

「ああ、療育は意味がないなんて嘘だ。続けてきて、本当によかった」と、心の底から思えた瞬間でした。
奇跡は、それだけではありません。
- 名前を呼んでも無反応だった娘が、初めて手を挙げた日。
- 自分の思い通りにならないと大声で泣き叫んでいた娘が、自分で気持ちを落ち着かせることができた日。
- ペンすら持てなかった娘が、ぐるぐると丸が描けるようになった日。
一つひとつは、定型発達の子どもなら当たり前にできることかもしれません。
でも、私たち親子にとっては、どれもが金メダル級の、かけがえのない成長の証です。
この小さな成功体験の積み重ねこそが、療育がもたらしてくれた最大の宝物だと、私は確信しています。
家庭が「第二の療育の場」に変わる
療育の効果を最大化する鍵は、「家庭での連携」にあります。
療育は週に数時間。
それ以外の時間をどう過ごすかが、子どもの成長を大きく左右します。
家庭での支援グッズは、たとえば以下のようなものです。
- 視覚支援カード:
「朝起きたら、顔を洗う→着替える→朝ごはん」といった一日の流れをイラストカードで示すことで、見通しが立ち、癇癪の抑制につながります。 - 切り替えカード:
遊びを終えるときに「おしまい」のカードを見せ、「あと5分だよ」とタイマーをセットすることで、スムーズに次の行動に移れる効果が期待できます。
「療育施設に任せきり」にするのではなく、親も一緒に学ぶ姿勢を持つこと。
療育で学んだことを家庭で実践し、できたことを先生にフィードバックする。
このサイクルが回り始めると、子どもの成長は驚くほど加速します。

「療育は意味がない」どころか、家庭での関わり方まで教えてくれる、最高の道しるべになります。
療育の効果を実感するための3つの視点

もし今、あなたが「効果が感じられない」と悩んでいるなら、少しだけ視点を変えてみませんか?
私が試行錯誤の末にたどり着いた、効果を実感しやすくなる3つのポイントをご紹介します。
1. 目的を「高望み」から「現実的」へ再設定する
療育を始めた頃の私の目標は、正直に言うと「他の子と同じように話せるようになってほしい」という高いものでした。
でも、それだといつまで経っても目標は達成できず、「やっぱり意味がない」と落ち込むだけです。
そこで、療育の先生と相談し、目標を再設定しました。
- 長期目標:
自分の気持ちを何らかの形で伝えられるようになる。 - 短期目標(3ヶ月):
嫌なときに「いや」と首を振る、嬉しいときに笑う。
このように、具体的で、達成可能な小さな目標を立てることで、「今週はこれができたね!」と親も子も達成感を得やすくなります。
高すぎる期待を手放すことが、小さな成長に気づくための第一歩です。
2. 「他人と比べず、昨日の我が子と比べる」と心に決める
発達支援の鉄則ですが、これが一番難しく、そして一番大切です。
「〇〇ちゃんはもうお喋りできるのに……」という焦りは、親にストレスを与えます。
比べるべきは、周りの子ではありません。
1ヶ月前の、半年前の、そして昨日の我が子です。
また、「前はできなかったこれが、できるようになった!」という小さな発見を記録するのもおすすめ。
見返してみると、いかに我が子が自分のペースで着実に成長しているかが分かり、「療育は意味がない」なんて気持ちは吹き飛んでしまいますよ。
3. 「家庭でできること」を積極的に取り入れる
先ほどもお話ししましたが、療育は魔法ではありません。
療育施設と家庭が車の両輪となって初めて、前に進む力が生まれます。
療育の先生との面談では、「家でできることはありますか?」と、積極的に質問してみましょう。
そして、教わったことを一つでもいいので家庭で実践してみる。
その積み重ねが、やがて大きな変化へとつながっていきます。
療育に代わる選択肢と教材・支援ツール

ただし、療育だけが発達支援のすべてではありません。
子どもの特性や家庭の事情によっては、別の支援方法やツールを選ぶことが、より良い成長につながることもあります。
ここでは、療育に代わる、もしくは補完する形で活用できる選択肢も紹介しておきます。
- 児童発達支援の種類と比較(通所型・訪問型・個別支援など)
- 全国展開の民間療育の事例
- 自宅で取り組める家庭学習教材の活用
療育の効果を最大化するためには、「合わないからやめる」のではなく、「他に合う方法はないか」を探す姿勢が大切です。
あなたの子どもに合った支援を見つける参考にしてください。
児童発達支援の種類と比較
「療育って一種類だけじゃないの?」と思っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には児童発達支援には様々な形態が存在し、子どもの特性や家庭の事情に合わせて選ぶことができます。
たとえば、定番の通所型(施設に通うタイプ)のほかにも、訪問型(自宅に来てもらうスタイル)や個別支援(マンツーマン対応)、親子参加型、グループ活動中心の場など多様です。
それぞれにメリットとデメリットがあり、「集団が苦手」「送迎が難しい」「親も一緒に学びたい」などのニーズに応じた選択が可能です。
まずは、自分たちの生活スタイルと子どもの性格を照らし合わせながら、「今より合った支援方法はないか」を探してみてください。
選択肢を知ることで、支援への不安が和らぎ、前向きな気持ちに変わっていきます。
全国展開の民間療育の事例
全国展開の民間療育サービスで最も有名なのが「リタリコジュニア」。
個別から集団まで、多様な支援スタイルが選べる点で注目されています。
利用者の声には、「先生との信頼関係ができたことで、子どもが療育を楽しむようになった」という本音が多数です。

私の娘もリタリコでお世話になりました。
先生がじっくり関わってくれたおかげで、自己表現が本当に増えた実感があります。
実際の支援の様子や親の感想、費用などは以下の記事で詳しく紹介しています。
また、リタリコ以外の民間療育については、以下の記事で詳しく紹介しています。
自宅で取り組める家庭学習教材の活用
オンラインで学べる、発達障害児向けの家庭教材の筆頭は「すらら」。
発達障害の子どもと相性が良いと、口コミでも高い評価を得ています。
一人ひとりの理解度に合わせた学習の進め方ができるため、家庭学習の“療育的補完”として活用しやすい点が魅力です。

たとえば、漢字や計算といった基礎を無理なく学べる仕組みがあり、子どもが自分のペースで操作できる工夫が随所に散りばめられています。
家庭で「すらら」を使い始めてから、自分から机に向かう習慣が少しずつついたという親の声もあります。
また、保護者向けの理解サポートが充実しており、「子どもの発達段階に応じた声かけ方法」や「つまずきポイント」の理解に役立つ情報を得られる点もメリットです。
以下の記事で、すららを始めとした発達障害児向けの教材について詳しく紹介しています。
よくある質問|「療育は意味がない?」と迷う親御さんのQ&A

療育について不安や疑問を抱えるのは、どの親御さんにとっても自然なことです。
ここでは、特によく寄せられる質問に対して、実体験と支援者のアドバイスをもとに回答していきます。
Q
療育をやめても大丈夫?
A
「このまま続けて意味があるのか分からない」「辞めたらどうなるのか心配」——療育をやめるかどうかの判断は、親にとって非常に悩ましいものです。結論から言えば、やめること自体が“悪い選択”ではありません。ただし、何も支援を受けない状態が長く続くことには注意が必要です。
発達に課題のある子どもは、適切な関わりやサポートがないまま過ごすと、苦手なことがより強化されたり、困りごとが増えていく可能性があります。療育をやめる選択をする場合でも、「別の支援に切り替える」「家庭で支援する体制を整える」といった“代替手段”を考えておくことが大切です。
また、「辞める前に一度相談する」ことも重要なポイントです。支援者や市区町村の子育て支援センター、通っている療育施設に「今の支援が合っていない気がする」と正直に伝えてみましょう。環境の変更や、子どもに合わせた支援の見直しができることもあります。

やめる・続けるに正解はありません。大切なのは「子どもと家庭にとって、今何が必要か」を冷静に見極める視点です。
Q
療育に効果を感じないときはどうすれば?
A
「何ヶ月も通っているのに、まったく変化が見えない」——このように感じると、「うちの子には意味がないのかも」と不安になるのも無理はありません。ですが、効果がないと感じたときは、まず“何が効果として期待されていたのか”を振り返ることが大切です。
実際には、療育の成果が「わかりやすい言葉の変化」や「行動の改善」として現れるとは限りません。子どもが笑顔で通えるようになった、支援者に心を開くようになった、家庭での癇癪が減った——こうした「内面的な変化」も十分に大切な成果です。
それでも納得できない場合は、以下の対応を検討しましょう。
- 担当者との面談を行い、目標設定や支援内容を見直す
- 他の療育機関の見学やセカンドオピニオンを受けてみる
- 家庭での接し方や支援の工夫について支援者に相談する
効果が見えないときこそ、立ち止まって支援の方向性や子どもの状態を見直すチャンスです。焦らず、現状に合ったアプローチを見つけることで、再び前向きに取り組めるようになります。
Q
療育に通わせなくても、家庭だけで補える?
A
「もう通わせなくても、家でなんとかできるんじゃないか」——そう思う親御さんも多いでしょう。確かに、家庭で実践できる支援方法はたくさんあります。絵カードやタイムスケジュール、感情のコントロールを学ぶアイテムなど、日常生活に取り入れやすい工夫が多く存在します。
しかし、家庭だけで補おうとすると、次のような課題も生じます。
- 子どもの状態を客観的に評価するのが難しい
- 親の負担が大きくなり、精神的に追い詰められる
- 正しい対応方法が分からず、誤った関わり方をしてしまうリスク
また、支援のプロである療育機関のスタッフは、子どもがどの場面でどのような支援を必要としているかを見極め、計画的に取り組みを行うスキルを持っています。家庭と支援機関が連携し、双方で子どもをサポートする形が理想的です。
無理に一人で抱え込む必要はありません。「家庭でもできること」と「専門家に任せること」のバランスを取ることで、親子双方の負担を軽減し、より効果的な支援が実現します。
まとめ:「療育は意味がない」と思った、そのときに読んでほしい
かつての私と同じように、「療育は意味がないのかもしれない……」と悩み、先が見えない不安に押しつぶされそうになっているお母さん、お父さんへ。
その気持ち、痛いほど分かります。
でも、どうか一人で抱え込まないでください。
療育は、すぐに結果が出る特効薬ではありません。
時には遠回りをしたり、立ち止まったりしながら、子どもと親が一緒に歩んでいく、長い旅路のようなものです。

だからこそ、「意味がない」と感じたときは、「やり方を変えるチャンス」だと捉えてみてください。
今の場所が合わないなら、別の場所を探せばいい。
集団が苦手なら、個別を試せばいい。
大切なのは、「通い続けること」ではなく、「あなたのお子さんが安心して成長できる、最適な環境を見つけてあげること」です。

私の娘は療育と出会ったことで、自分の世界を大きく広げることができました。
あのとき、諦めずに続けて本当に良かったと、心から思っています。
この記事が、あなたの迷える心に寄り添い、再び前を向くための小さなきっかけとなることを、切に願っています。
あなたとあなたのお子さんの未来が、温かい光で満たされることを、心から応援しています。